丁度いい「ひんやり感」を増幅させて脳に届ける仕組み - ナゾロジー
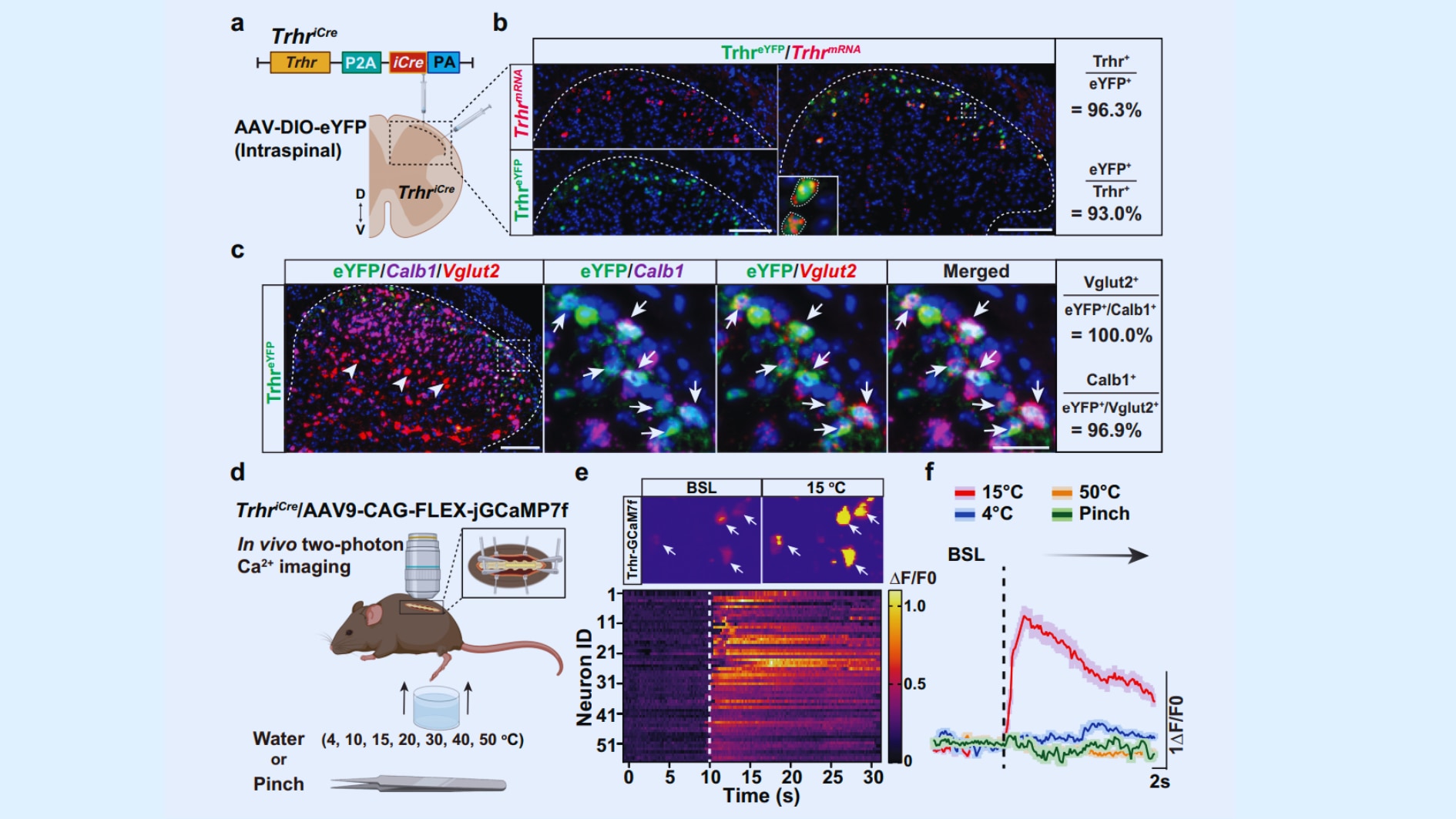
生物学のニュースbiology news
もっと見る
恋愛の自由を捨て、遺伝子も断捨離して「究極の社畜帝国」を手に入れた生物がいた

東京のスズメは大胆だった――逃げラインは東京4.2m、茨城11.1m

人間1人=3.2万kcal、それでも「人肉食」が損な理由が数式で示された

人が人を絶対に食べてはいけない「科学的な理由」

4億年前の巨大キノコ、内部構造と成分を分析したら「植物でも菌でもない何か」だった
注目の科学ニュースpick up !!

ヘビが1年間「何も食べず」に過ごせる理由が判明

水を弾くことで浮力を得る「沈まない金属」が作られた

脳の認知機能を低下させる「朝食」が明らかに