日本社会に埋め込まれた“引きこもり”の種

日本の引きこもり問題の特異性を語るには、まず他国の状況と比較して考えていく必要があります。
欧米諸国でも、不登校や若者の社会的孤立、いわゆる「ニート(NEET)」と呼ばれる就学・就労していない若年層は存在します。 また韓国や中国にも、社会に出ることを避けて自宅にこもる若者が一定数いることが報告されています。
しかし、それらの多くは「一時的な状態」であり、数年以内に再び社会とつながるケースが大半です。しかも年齢層は若年に集中しており、40代以上で10年以上引きこもっているような例は極めて少数派なのです。
例えば、単純な引きこもりの数を比較した場合、国民に対する引きこもりの割合は
-
日本:約1.2%
-
韓国:約2.3%
-
香港:約1.9%
-
イタリア:約1.2%
と別段日本が特別高い値を示しているわけではないとされています。むしろ韓国や香港の方が数の上では深刻に見えます。
しかし、内閣府の調査(2016年)によれば、日本の15歳~39歳の引きこもり経験者の約35%が7年以上引きこもり状態にあると報告されており、さらに40歳以上の中高年層の引きこもりが増加傾向にあるといいます。
佐賀県の調査(2017年)では、引きこもりと認識された644人のうち、40歳以上が全体の70%以上を占めていました。
一方で、韓国の引きこもりの平均年齢は20代前半であり、長期化するケースは少ないとされています。イタリアでも引きこもりは未成年者が主な対象であり、長期化や高年齢化の問題はあまり報告されていません。
つまり、日本の引きこもり問題は、年齢・持続期間において“世界でも異常”といえる状況にあるのです。
では、なぜこのような差が生じたのでしょうか? その答えを探るには、日本に特有の“社会構造の癖”を見ていく必要があります。
まず、背景にあるのが高度経済成長期に形成された成功モデルの固定化です。
1950年代から70年代にかけて、日本は世界が驚くような経済発展を遂げました。そして社会に根づいたのが「良い学校に入り、安定した企業に就職し、定年まで勤め上げる」という1本道の人生ルートです。
このルートを外れた者は、「失敗者」「社会不適合者」というレッテルを貼られがちになり、やがて社会的な沈黙を選びます。
つまり、日本は世界的にも稀な“奇跡的な成功”を体験してしまったがために、人々の人生における「やり直し」や「別ルート」を選択するという社会構造を失ってしまったのです。
さらに、欧米が宗教的な倫理観や個人の良心をベースにした「罪の文化(内面の反省)」なのに対し、日本では「他人にどう見られるか」が行動規範となる「恥の文化」が土台となっています。
これは、古代から続く日本の“村社会的構造”に根ざしたものだと言えます。
日本は自然災害が多く、稲作中心の生活を維持するためには、近隣住民との協力と秩序が不可欠でした。 この環境では、集団との調和=生存条件であり、「周囲から浮かない」「迷惑をかけない」ことが重要視されてきました。
その結果、社会的ルールやモラルは「法律」よりも「周囲の目」によって維持されるようになり、他人の視線を常に気にする行動様式が文化として定着したのです。
これにより、人前での失敗や社会からの逸脱は「恥」とされ、社会から一度外れると再び外に出ることが難しくなる心理を強化してしまいます。
加えて、日本社会には“家”を単位とする家族主義が色濃く残っています。
江戸時代から続く「家制度」では、家業を長男が継ぎ、家族が同じ屋根の下で暮らし続けることが当然とされてきました。
現代でもその名残は強く、親が成人後の子どもを支えることが当たり前という文化が引きこもりを長期化させる要因となっています。
対照的に欧米諸国では、18歳を過ぎれば子どもは親元を離れ、経済的・生活的に自立することが一般的です。親もまた、「子どもは独立すべき存在」と捉えており、成人後も親が生活を全面的に支えるという発想自体が非常にまれです。
そのため、引きこもりのような状態が日本ほど長期化しにくいのです。
このように、高度経済成長期の成功モデル・恥の文化・家制度という三つの要因が、日本社会において「引きこもり」という現象を助長する構造を作ってしまっていると考えられるのです。















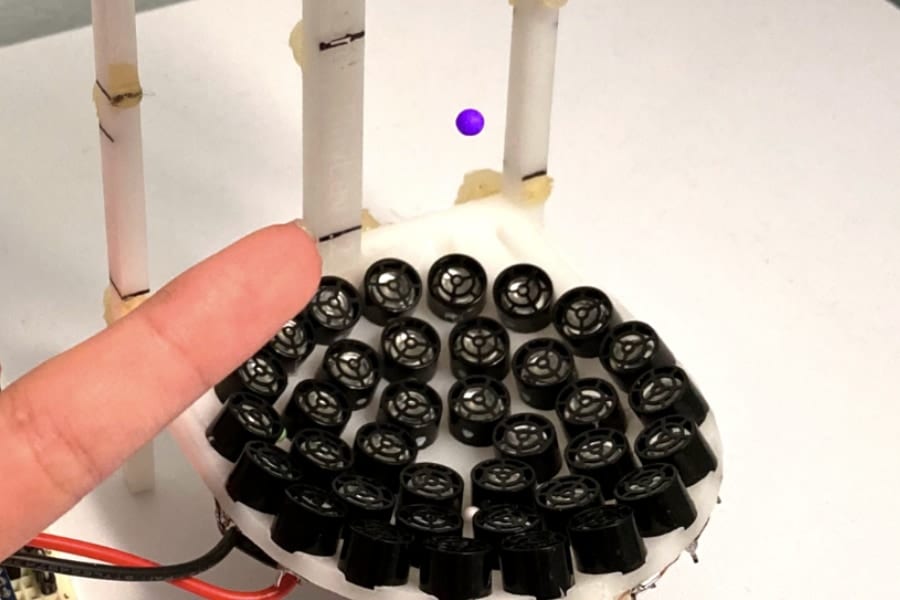
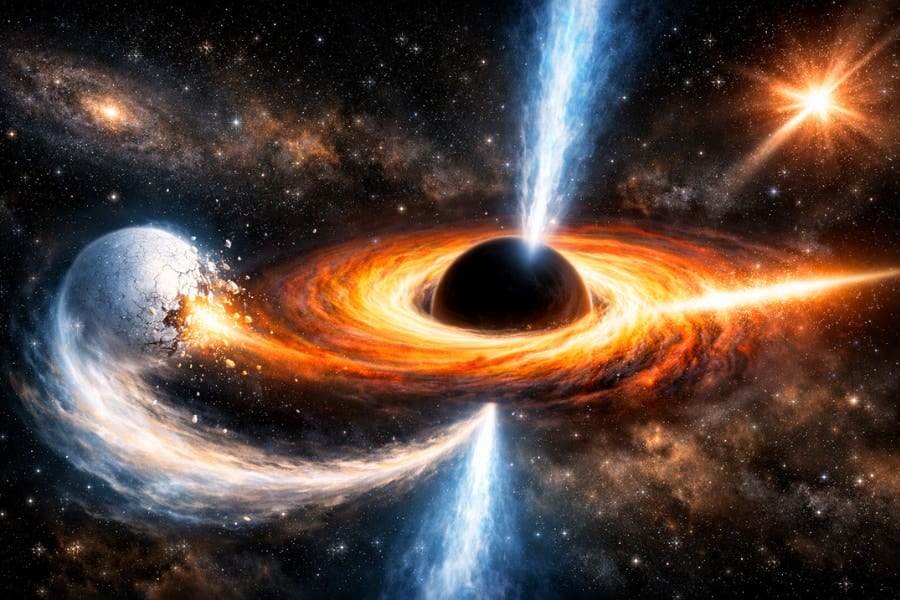














![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























