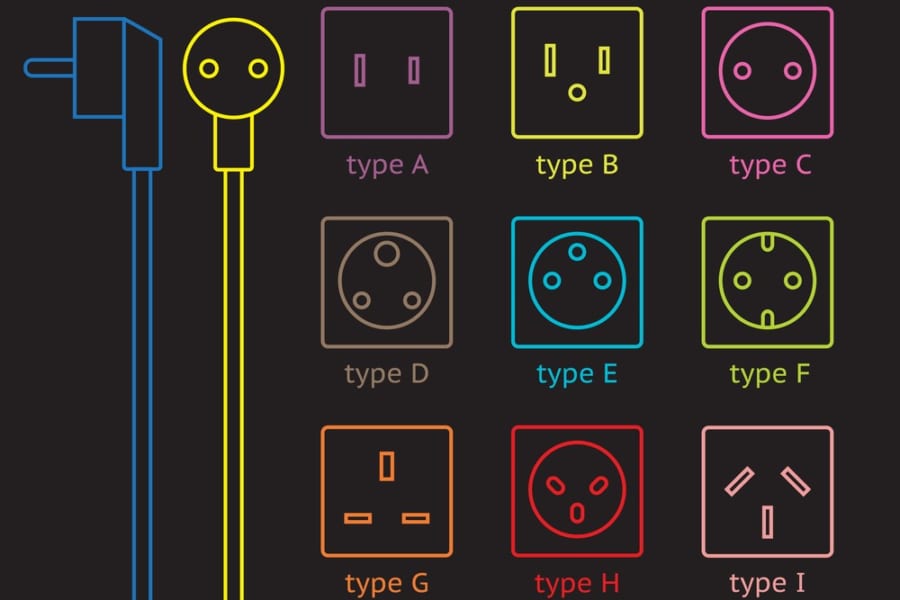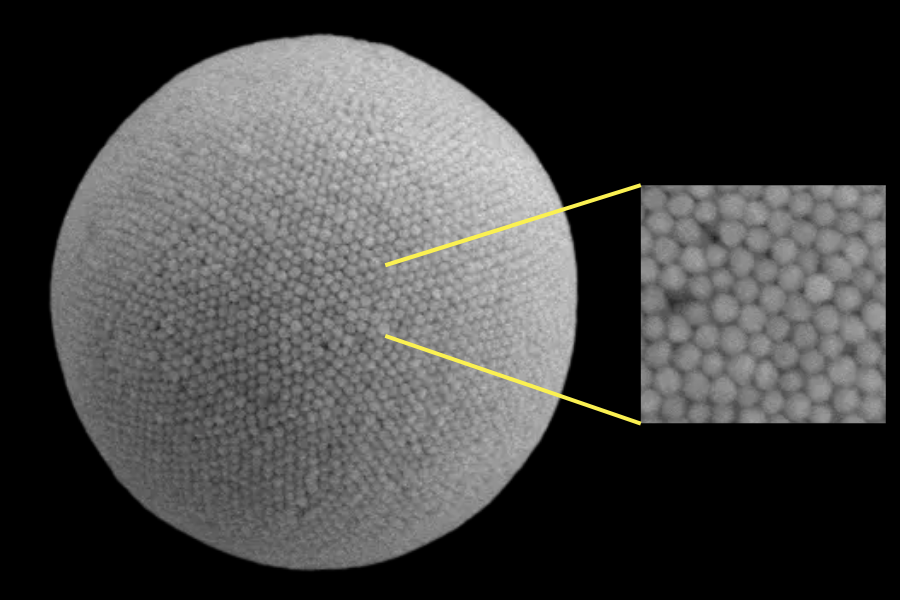極地の海で見つかった氷の管

現在「死のつらら(brinicle:ブライニクル)」として知られるこの現象が、初めて科学的に報告されたのは1970年のことです。
南極・マクマード湾での観測中、アメリカの海洋生物学者パウル・デイトン(Paul K. Dayton)と物理海洋学者スティーブン・マーティン(Stephen Martin)が、海氷の下に中空の氷の管が垂れ下がっている構造を発見しました。
そしてこの発見は、翌1971年に科学雑誌『Journal of Geophysical Research』で発表されました。
当初、この現象は形状が鍾乳石に似ていることから「sea-ice stalactite(海氷鍾乳石)」と呼ばれましたが、後にその成長メカニズムが鍾乳石とはまったく異なることが判明し、「brinicle(ブライニクル)」と呼ばれることになります。
これはこの氷の管が、塩水(brine)が流れ出す過程で形成されたつらら(icicle)のような構造であることから、作られた造語です。この語は科学論文でも定着し、現在では正式な用語として使用されています。
この構造の本質は、氷点下でも凍らない濃い塩水が、周囲の海水を凍らせながら下降し、筒状の氷構造を形成するというものです。
ブライニクルという現象が広く一般に知られるようになったきっかけは、2011年にBBCが放送した自然ドキュメンタリー番組『Frozen Planet』だと言われています。
この番組では、南極の浅海域において、氷の下から海底に向かって伸びていく氷の管がはっきりと映像に記録されました。
その映像には、ブライニクルの先端が海底に達し、そこにいたウニやヒトデなどの底生生物が凍結されていく様子も含まれており、視聴者に大きな印象を与えました。
ウニやナマコなどの底生生物は移動速度が遅いため、低温の塩水による凍結から逃げ切れず、この現象から逃れられず凍結して死ぬことがあるのです。
この映像により、「brinicle」という科学用語は「death icicle(死の氷柱)」という呼び名とともに一般にも認知され、注目を集めることになったのです。
最近発売されたゲーム「DEATH STRANDING 2」の中にも、ステージの演出としてこの現象が登場していたので、そこでこの自然現象を知ったという人もいるかもしれません。

では、この不思議な現象はどのような原理で起きているのでしょうか?
















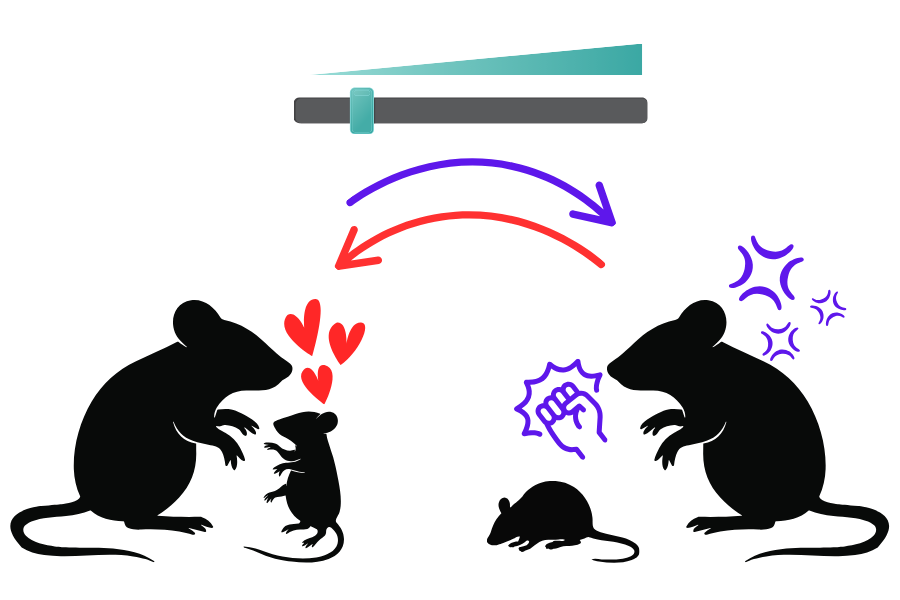
















![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)