忘れた記憶が「勘」となって私たちを助けている
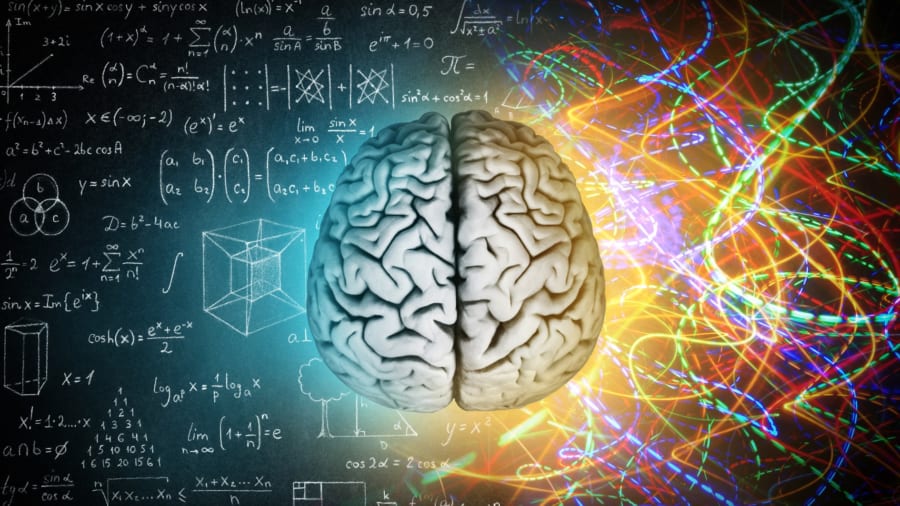
今回の研究結果は、「忘れる」という現象を新しい視点で捉え直すものです。
人はある出来事を忘れてしまっても、その記憶の痕跡は脳から完全に消去されるわけではありません。
むしろ見えない形で脳内ネットワークに潜み続け、場合によっては私たちの行動に無意識的に影響を与え続けていることが示されました。
今回の研究は、マウスで得られていた知見をヒトでも高精度に示した例のひとつです。特に7テスラという最新鋭のMRI技術を用い、高精細な脳活動パターンを捉えることで、海馬に「忘却エングラム」が残っている証拠が得られた点は画期的でした。
海馬に残る痕跡は、意識的に思い出す役割だけではなく、無意識の行動や選択と関係している可能性が高いことも示唆されています。
ではなぜ脳は記憶を完全に削除せず痕跡を残すのでしょうか?
考えられる理由の一つは、再び似た状況に出会ったとき、素早く対応するためではないかと研究者らは考察しています。
たとえ今は不要でも、経験の痕跡が残ることで再学習するより簡単に直感で適応可能だからです。今回も、忘れた記憶が直感的な選択の向上として行動に表れていました。
また、記憶を意識できるかどうかには海馬から新皮質への移行プロセスの違いが関係しています。
覚えていた記憶では新皮質へ展開が進んでいましたが、忘れた記憶ではそれがなく、海馬にとどまっているため意識から外れていると考えられます。
「忘却とは記憶が消えるのではなく、アクセスが一時停止された休眠状態」であり、脳は不要な情報を「完全に捨てる」のではなく、「一時停止フォルダ」に保管しているとも言えます。
勘の正解率が高くなる時に海馬が特徴的な活性化をするという結果は、これを脳科学的に示しています。
さらに、将来的な応用面でも興味深い示唆があります。
たとえば認知症や健忘症の患者では、記憶が失われたように見えても、痕跡そのものは残っている可能性があります。
もしそれを再活性化できれば、失われた記憶を取り戻す助けになるかもしれません。
研究グループは今後、磁気や電気による非侵襲的な脳刺激によって、海馬内に潜む無意識記憶の痕跡を意識上に引き上げられるかどうか、検証を検討しています。
また、同じグループは睡眠中に学習させた内容を目覚め後に思い出す実験や、健忘症で残った記憶能力を高める介入も模索しており、今回の「忘却エングラム」の発見は記憶障害の新たな診断・治療法開発に道を開く基盤となる可能性があります。
記憶は本当に不思議で奥深いものです。一度は忘れたと思った体験も、脳には見えない形で痕跡が生き続けていて、気づかぬうちに私たちの意思決定や行動に影響しているのかもしれません。
脳は意識に不要な情報を隠し持ちながら、必要なときに備えて環境へ適応する優しい戦略をとっている――そんな気持ちになりますね。




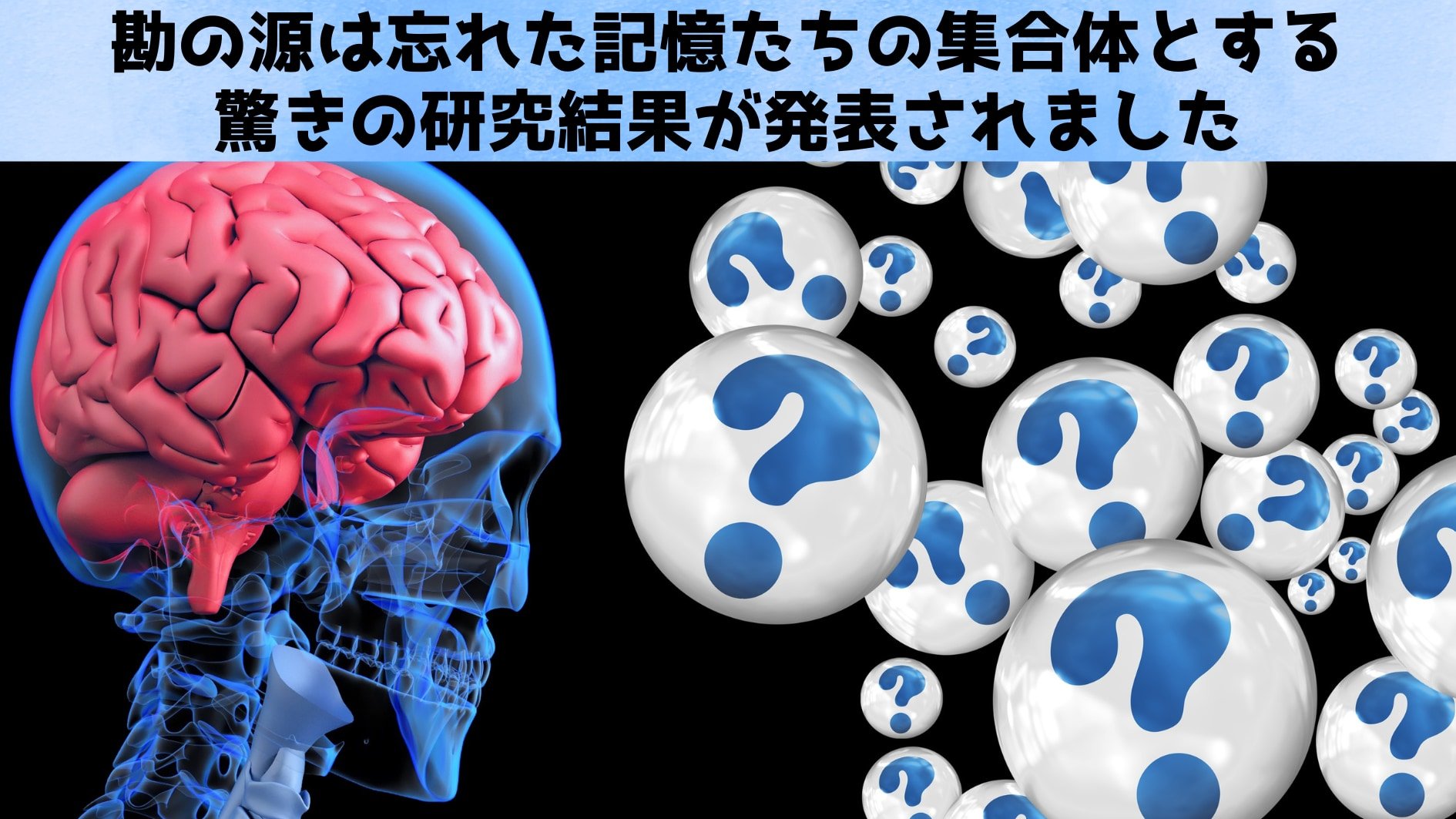


























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)





















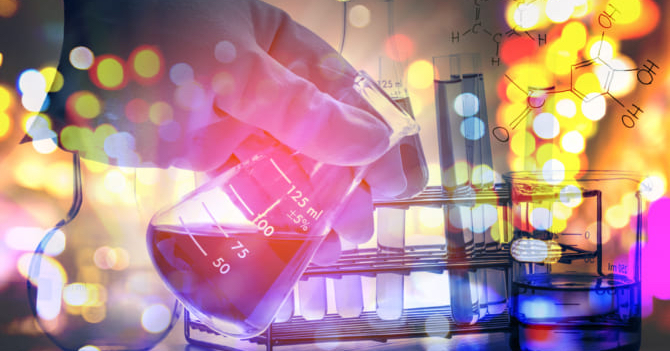






逆に考えると誤報や誤字やフェイクニュースを見てしまうと
それが意識してなくても脳内に残って
影響を受ける可能性があるということなのでしょうか…?
これは面白い発想だと思います。記憶する対象に正誤は関係ないので,偽情報でも同じように記憶されるはずです。昔,極短時間の記憶が無意識に残るサブリミナル効果が話題となり,その後,実証できなくてく否定されましたが,この記事にあるような7テスラのfMRIを使えば,確認できるかもしれませんね。
人は産まれてからの記憶を全て覚えているって聞いたことがあるけど、これは納得できる裏付けに思えてしまうかも
テスト前の一夜漬けでも、なんとなく選んだ答えが当たりやすくなる程度の効果はありそう。
海馬にしか残っていない情報が短期間で失われるなら、テストが終わったらすぐ忘れてしまう理由の説明にもなるかも。
確かに日常生活で無意識にやっている選択とか知らぬ間に身に付いた習慣を辿っていくと、「ああ、あのシーンか」「あれか、あのときの言葉か」って昔の思いもよらない記憶やエピソードが元になっていることがよくある。のは僕だけかなw
あるー
興味深いですね。ただ結論としては当たり前っぽくも感じる。というよりそこも含めての記憶というか、記憶というのはとても長い尻尾を持っているということかなと。つまりは、支配したければ忘れさせろということだ。私たちは忘れなければその手品に対抗ができる。みなさんがんばりましょう!