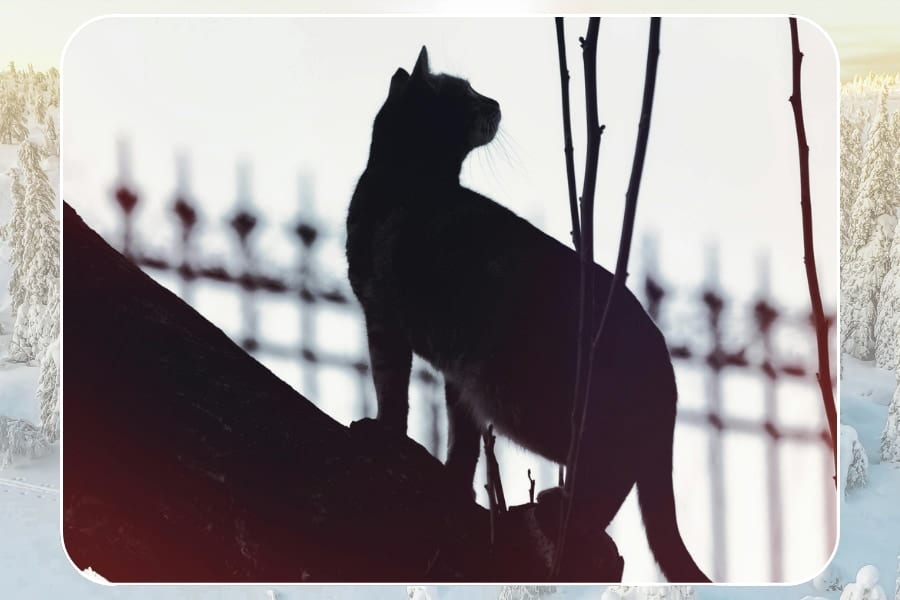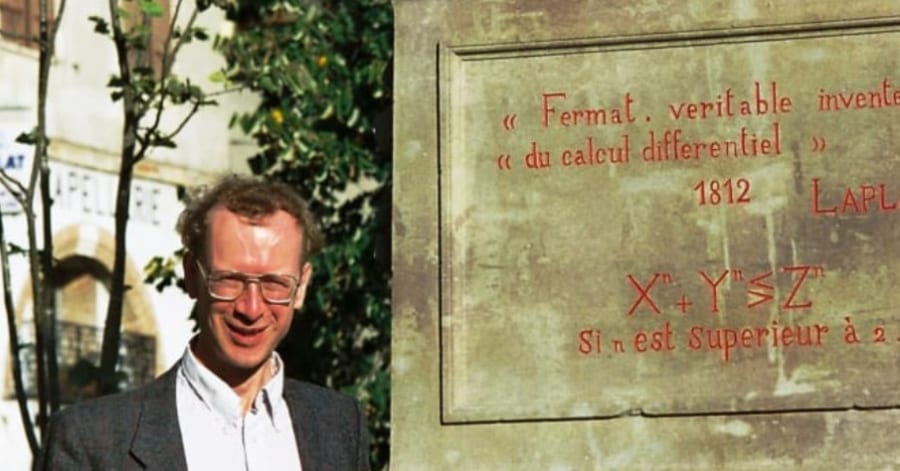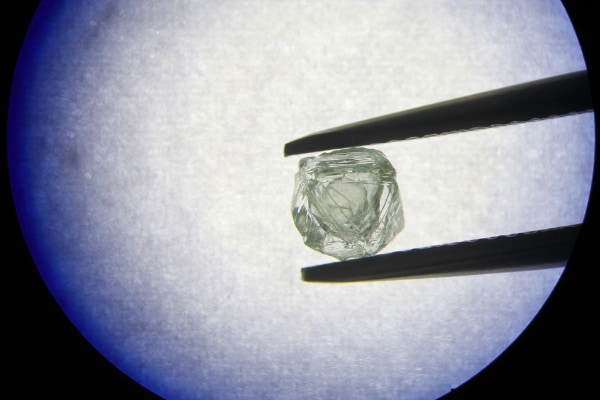ヒゲワシの驚くべき「コレクション癖」
ヒゲワシ(学名:Gypaetus barbatus)は、ヨーロッパやアジア、アフリカの山岳地帯に生息する大型のワシの仲間です。
骨を好んで食べることから「骨食いワシ」とも呼ばれ、スペインではピレネー山脈などが主な生息地となっています。
彼らの生態で特にユニークなのは、「崖の洞窟や岩陰に巣を作り、同じ巣を何世代にもわたり再利用する」という点です。
安全な場所であれば、その巣は100年、場合によっては数百年も使われ続けることもあるのです。

今回スペイン南部で調査された12か所の歴史的ヒゲワシの巣も、そうした「長寿な巣」でした。
研究チームは2008年から2014年にかけて、保存状態の良い巣を厳密な考古学的手法で1層ずつ掘り進めました。
その結果、合計2,483点もの遺物が見つかりました。
その多くは、動物の骨や卵の殻、獲物の蹄(ひづめ)や毛、ワシ自身が集めてきた巣材です。
しかし驚くべきことに、約9%にあたる226点は「人間が作った」または「加工した」人工遺物だったのです。
巣に紛れ込んでいたのは、草で編まれた靴やバスケットの一部、羊皮の装飾片、クロスボウの矢、エスパルト草(イグサの一種)で作られた投石器やロープ、木製の槍など、まさに中世ヨーロッパの生活や文化を物語るアイテムたちでした。
ヒゲワシは、巣の補強や装飾のためにさまざまなものを集めてくる習性があります。
これらの人工遺物も、ワシ自身が興味を持って拾い集めたものと考えられます。
そして巣が何世代にも渡って使われることで、ワシたちの「コレクション」は時代を超えて積み重なっていったのです。































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)