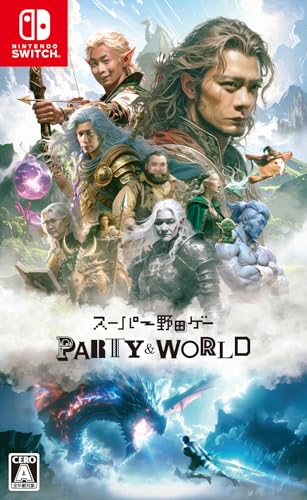生理前のADHD女性が抱える「見えない困難」
ADHD(注意欠如・多動症)は、「落ち着きがない」「じっとしていられない」といった多動のイメージが強く、かつては子どもや男性の病気と思われてきました。
しかし実際には、大人になっても症状が残る人が多く、女性のADHDも決して珍しくありません。
ただし、女性の場合は「注意が散漫」「忘れ物が多い」などの“不注意”症状が中心となりやすく、子どもの頃から周囲に気づかれず、診断も大人になってからやっと受けるケースが多いと言われています。
さらに、女性には「月経」や「ホルモンの変動」といった特有の身体リズムがあり、これがADHD症状や気分の変調とどのように関係するのか、実はこれまでほとんど研究されてきませんでした。
女性の月経に関わる辛い問題には、月経前症候群(PMS)や月経前不快気分障害(PMDD)があります。
PMSは月経(生理)が始まる2週間前ごろから心身で生じる不安定な状態を指します。
そしてPMDDは、その中でも心の不安定さがより際立って出てしまう場合に診断されます。
強い抑うつ・不安・イライラ・情緒不安定といった“こころの症状”が現れ、日常生活に大きな支障をきたすのです。
症状が現れる時期は「月経が始まる直前」だけで、月経が始まるとスーッと消えるのが特徴ですが、その期間は本人も家族も非常に苦しい思いをします。
PMDDはPMSよりもはるかに重く、重症の場合には「死にたい」という気持ちさえ生じさせる深刻な疾患です。
しかし、本人が「性格の問題」と受け止めてしまったり、周囲が気づきにくい「見えないつらさ」になりやすいことも特徴です。
ロンドン大学クイーン・メアリーの研究では、近年関係性が指摘されている「ADHDを持つ女性は、PMDDになりやすいのではないか?」という疑問を、科学的に明らかにしようとしました。
調査はイギリス国内の18~34歳の女性715人を対象に、オンラインで実施されました。
まず、「医師からADHDと診断された女性」「質問票でADHD傾向が強く出た女性(診断歴がなくても)」「ADHDの診断がない女性」をバランスよく選びました。
PMDDの診断も、医学的に広く使われている質問票(PSST)を用いて、月経前にどんな症状がどれだけ強く出るかを詳しくチェックしました。
また、うつ病や不安障害の診断歴も同時に尋ね、他の心の病気が重なっていないかも検討されました。









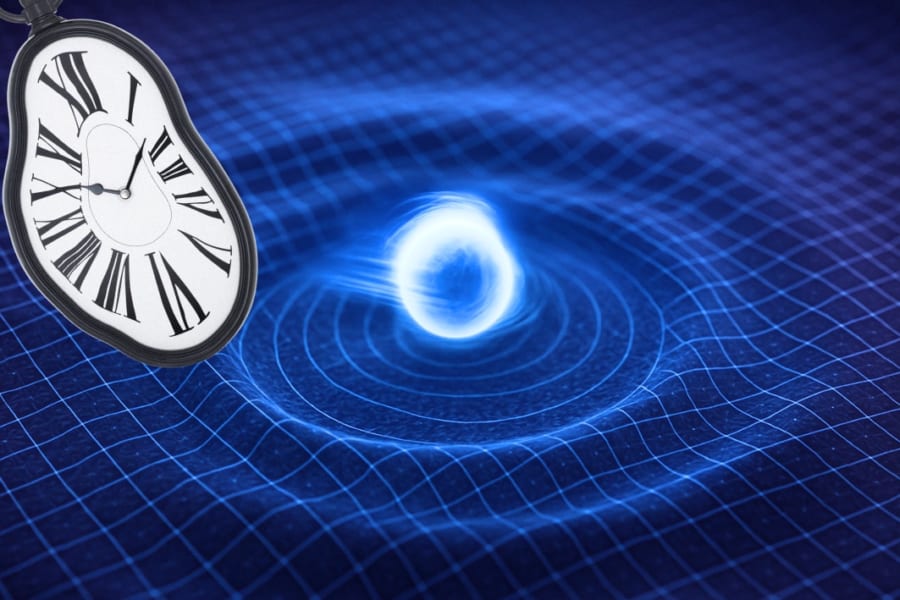

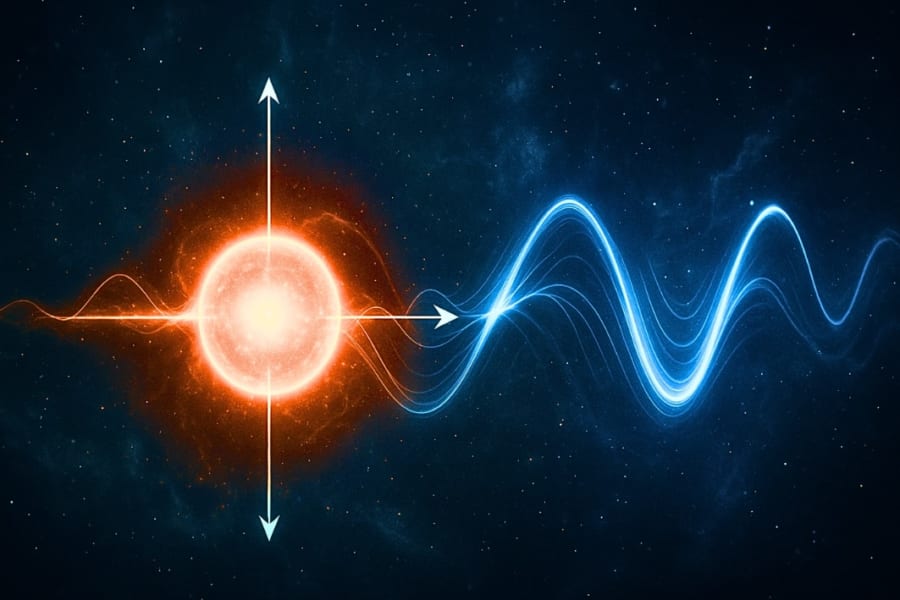


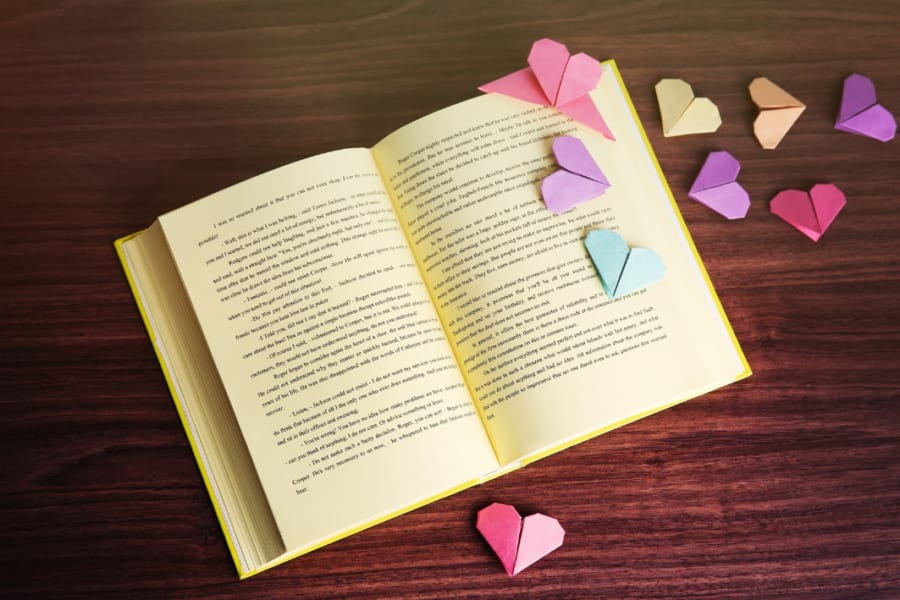








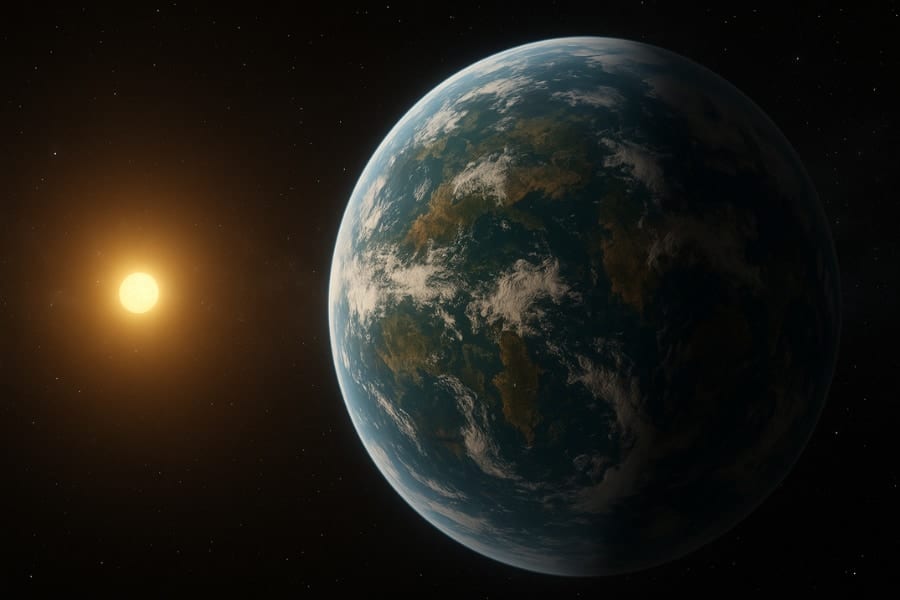




![ラボン(Lavons) 柔軟剤 特大 シャイニームーン[フローラルグリーン] 詰め替え 3倍サイズ 1440ml](https://m.media-amazon.com/images/I/41ze0Blp9fL._SL500_.jpg)