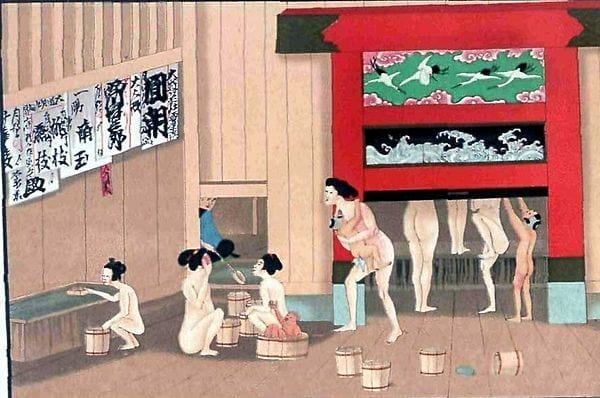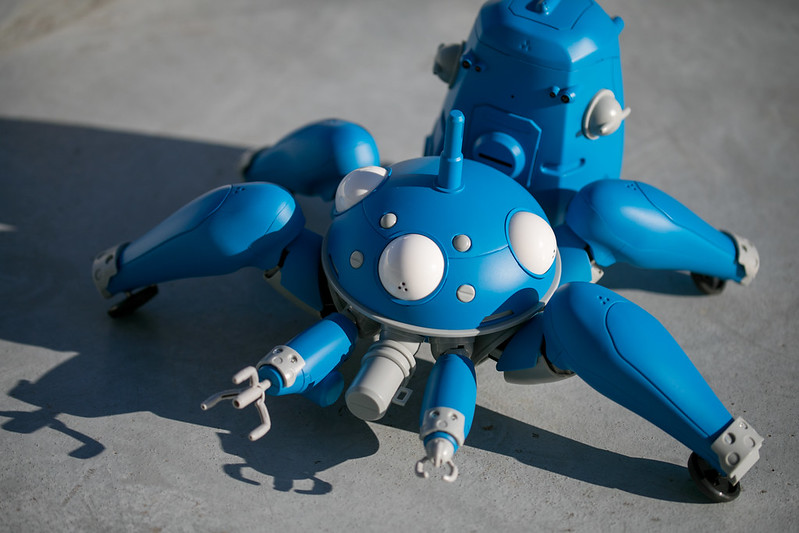破壊工作から情報収集までなんでも行っていた忍者

戦国時代の忍びが放火や城の乗っ取りを行ったという事例は、いくつかの史料に記されています。
その一例が1553年、信濃(現在の長野県)での出来事です。
武田信玄が村上義清(むらかみよしきよ)を追放した後、越後の長尾景虎(ながおかげとら、後の上杉謙信)が義清を支援し、武田軍と激戦を繰り広げた第一次川中島の戦い。
この戦いの中で、武田方の忍びが景虎軍の占拠する麻績城(おみじょう、現在の長野県東筑摩郡麻績村)に放火し、敵軍に混乱をもたらしました。
夜の闇に紛れて行われた火攻めは、景虎軍の士気を動揺させ、撤退に追い込むほどの影響力を持っていたのです。
また、永禄8年(1565年)の肥後(現在の熊本県)では、ある国人が相良家の小川城(現在の熊本県宇城市)に忍びを送り込み、放火を試みたといいます。
この時は幸いにも放火は未遂に終わったものの、忍びの存在が城方に与える緊張感は計り知れません。
発見された忍びを捕らえようと追いすがるも、「かめ坂」という地で逃げられた様子が『八代日記』に記録されています。
この出来事は、戦国時代の城にとって忍びがいかに大きな脅威であったかを物語っているのです。
さらに、織田信長の書状にも、忍びの潜入や放火にまつわる記述が登場します。
信長が家臣に与えた感状には、岐阜城内に忍び込んだ敵を発見し撃退した功績が記されています。
特に興味深いのは、信長がその状況を神妙な行動と称賛したことです。
この「忍びを撃退した」という記録から、戦国の世では城を守る側もまた、忍びに対して高度な警戒を怠らなかったことが窺えます。
なお作品の中では忍びが派手な戦闘を繰り広げる場面が描かれることもしばしばありますが、実際の忍びは出来るだけ戦いを避けていたということもあり、派手な戦闘はあまり行いませんでした。
忍びの活動は単なる破壊工作だけにとどまらず、情報収集や敵の攪乱といった戦術的役割も担っていました。
真田昌幸(さなだまさゆき)が「目付」を派遣して敵の動きを探らせた事例や、武田家が村人を動員して「地下かまり」と呼ばれる伏兵を組織した話もその一環です。
これらの活動は、敵地に潜り込み、夜闇に紛れて動く忍びたちの姿を浮かび上がらせます。
戦国の世における忍びの役割は、時に幻術めいた逸話として語り継がれ、また時に冷徹な記録として史料に残されているのです。
その姿は、夜闇に溶け込み、火と混乱を操る影の軍団そのものです。
歴史の奥深くに潜む彼らの実像を追うと、そこには戦国という時代の荒々しさと、忍びたちが織り成す闇の物語が、鮮烈な筆致で描かれているように思えるのです。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![シルバーバック かわいい海の生きもの CUBE 2X2 キューブ ツーバイツー|海の生き物デザイン 立体パズル スピードキューブ 5cm 子ども〜大人向け 知育 ギフトに最適 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/41EJOOLgGXL._SL500_.jpg)