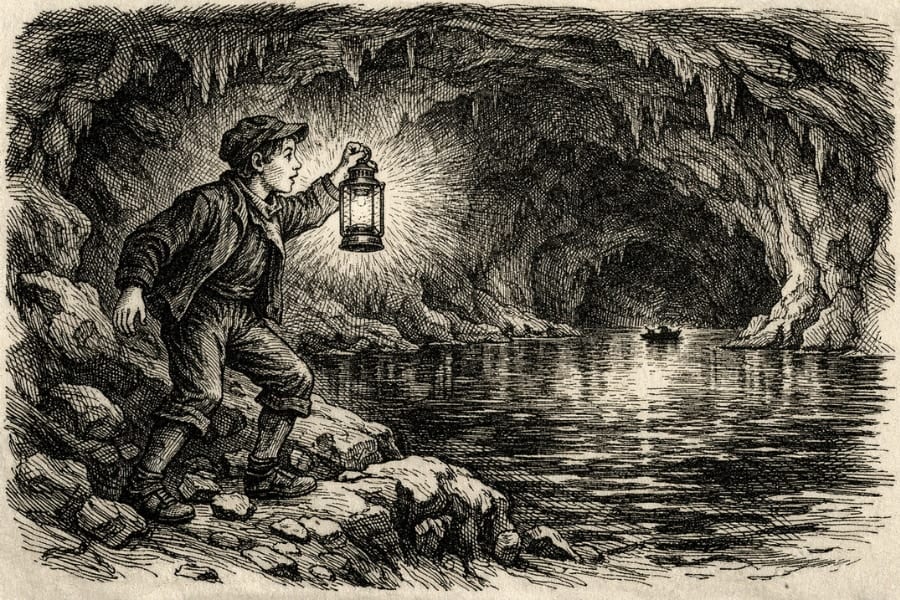チューイングガムの正体は「白樺タール」
今回の発見は、ヨーロッパ・アルプス地方の新石器時代遺跡から出土した30点の「白樺タール(カバノキ樹皮タール)」に対する最新の有機化学分析と古代DNA解析に基づいています。
白樺タールは、樹皮を乾留して作る粘着性のある黒い物質で、石器の柄付けや土器の修理、さらには装飾品や薬用、そして作業中に噛むための「ガム」として噛むといった、実に多様な用途に使われていました。
特に今回調査された12点のタール片には、はっきりと「歯型」が残されており、人が噛んだことが物理的にも確認されています。
【こちらはアルプス周辺で発見されたガムの画像】
なぜ人類はタールを噛んだのでしょうか?
一つには、タールに天然の抗菌成分が含まれていることから、口内の健康や歯磨き代わり、あるいは薬用として噛まれていた可能性が挙げられます。
また、冷えて固くなったタールを噛むことで柔らかくし、接着剤として使いやすくする目的もあったと考えられます。
ただし、唾液が混じると接着力が一時的に落ちるため、実際に接着に使う前には再加熱が必要だったようです。
化学分析の結果、ほとんどのサンプルから白樺タール由来の有機化合物が検出され、一部からは松脂(マツ科樹脂)が混合されていることもわかりました。
これは接着剤としての性能を高めるため、古代人が工夫していた証拠です。
さらに驚くべきは、これらのガム片から“噛んだ人の口腔内マイクロバイオーム(口内細菌群)”や、“食事に由来する植物や動物のDNA”までもが良好な状態で保存されていたことです。
例えば、アマ(亜麻)、エンドウマメ、ケシ、ハシバミ、オオムギ、コムギなど、多様な栽培植物のDNAが発見され、当時の人々が何を食べ、どんなものを生活に取り入れていたのかが直接分かる“タイムカプセル”になっていました。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)