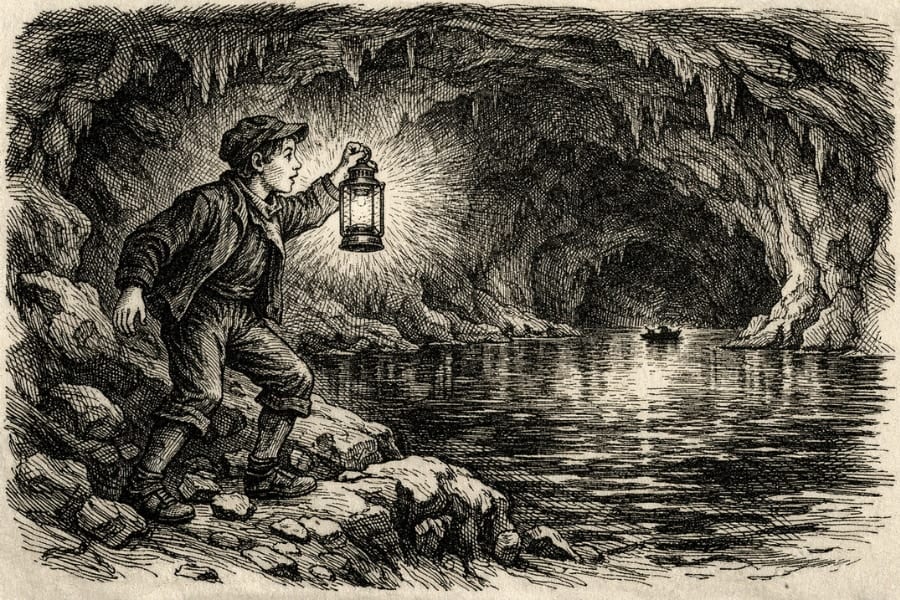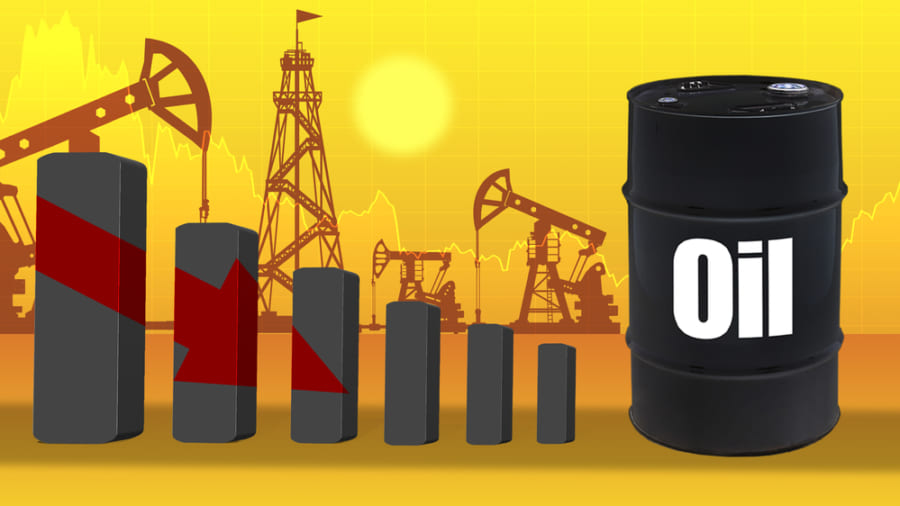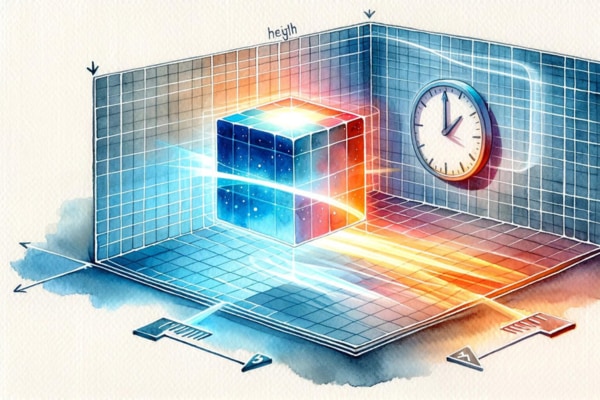遺跡から見つかった骨の加工
これまで良渚文化の遺跡では、整然と埋葬された墓地や副葬品が数多く発見されてきました。
しかし今回の発見は、従来のイメージを覆すものでした。
考古学チームが調査したのは、良渚遺跡の運河や堀から発掘された計183点の人骨。
そのうち52点(約3割)に「加工痕」がありました。
頭蓋骨を水平に切断して椀状にした「頭蓋骨カップ」をはじめ、顔の部分を仮面のように切り抜いた頭骨、小皿のような頭骨片、穴を開けた頭骨や下顎骨、四肢の骨を削ったものまで、多種多様な加工が認められました。
【こちらは実際に加工されていた人骨の画像です】
特に注目されるのが「頭蓋骨カップ」です。
これは頭蓋骨を上から水平にカットし、内側や縁を磨いた“器”のようなもので、現代人の感覚ではかなりショッキングなアイテムと言えるでしょう。
しかし驚くべきは、その多くが未完成だったこと。
加工途中で投げ捨てられた「失敗作」や、形を整える前のものが、まるでゴミのように大量に運河や堀に捨てられていました。
まるで「骨のゴミ捨て場」が遺跡の都市部に存在したかのようです。
これまで人骨の加工は、戦争や儀式、祖先崇拝など、特別な場面で行われてきたと考えられてきました。
しかし良渚遺跡の場合、骨に暴力や解体の跡は見られず、殺された痕跡もありません。
死体が自然に分解した後、頭蓋骨や骨が集められ、道具や仮面に加工されていたのです。
また加工対象となった骨に、年齢や性別の偏りは見られません。
子どもも大人も、男性も女性も区別なく使われていました。
しかも、栄養状態が悪かった痕跡が多く、社会的に低い地位の人々だった可能性も示唆されています。
なぜ、こんな大胆な“骨のリサイクル”が生まれたのでしょうか。
その背景には「都市社会の誕生」があったと考えられています。



























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)