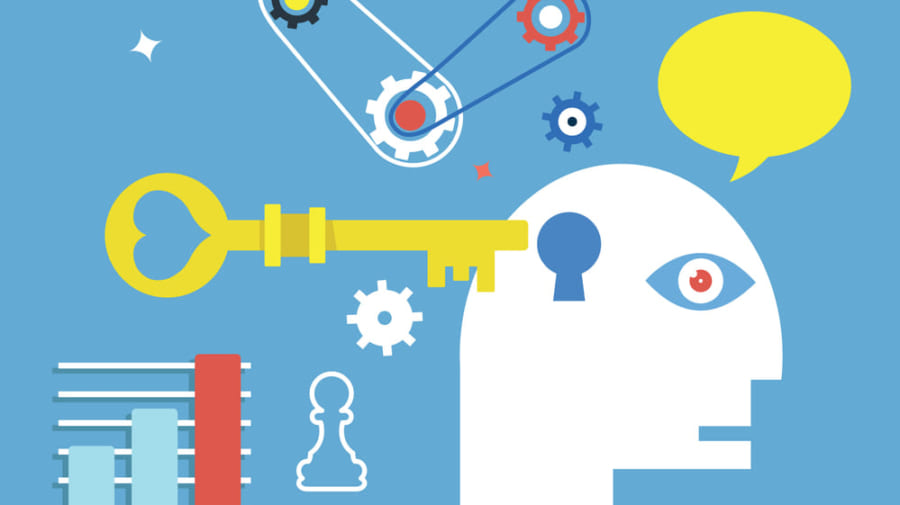三毛猫とサビ猫の毛色はどうやって生まれるのか?

「三毛猫」とは、オレンジ(または茶)、黒、そして白の3色を持つ猫を指します。
模様の出方はさまざまで、大きく分かれたパッチ模様の子もいれば、細かく散ったような柄を持つ子もいます。
この三毛模様は、実は「メスの猫」にほとんど限られる現象です。
オスの三毛猫は極めて珍しく、自然界では数万匹に1匹とも言われています。
一方、「サビ猫」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
サビ猫は、オレンジと黒の2色だけを持ち、白が入らない点で三毛猫と区別されます。
毛の色が混ざり合って、まるで錆びた鉄のような印象を与えることから、この名がつきました。
そしてこのサビ模様も、「メスの猫」にほとんど限られます。
どちらも見た目は個性的で、猫好きの間では人気のある柄です。

では、なぜ三毛やサビはメスに多いのでしょうか?
その鍵を握るのが「X染色体」と呼ばれる性染色体です。オス猫はXY、メス猫はXXの染色体を持っています。
実は、オレンジと黒の毛色を決める遺伝子はX染色体上に存在しています。
そして三毛とサビの背後には、「X染色体の不活性化」という仕組みが関係しているかもしれません。
これは、メスの細胞内で2本あるX染色体のうち1本がランダムに機能を停止するという、1961年に英国の遺伝学者メアリー・ライオン博士が提唱した仮説です。
猫の毛色は、細胞ごとにどちらのX染色体が活性化されているかによって決まり、それがパッチ状の模様として現れるというわけです。
この仮説は長年広く受け入れられてきました。
しかし、60年以上たった今でも、「オレンジ/黒の毛色を決める遺伝子」の正体やその働きについては明らかになっていませんでした。
そこで九州大学の研究チームは、オレンジ色の毛を持つ猫と持たない猫のDNAを比較する大規模な解析を行いました。
まず18匹の猫を対象にDNAを解析し、さらに国内外の50匹以上のデータも追加で検証しました。
ではその分析の結果、どんなことが見つかったのでしょうか。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)