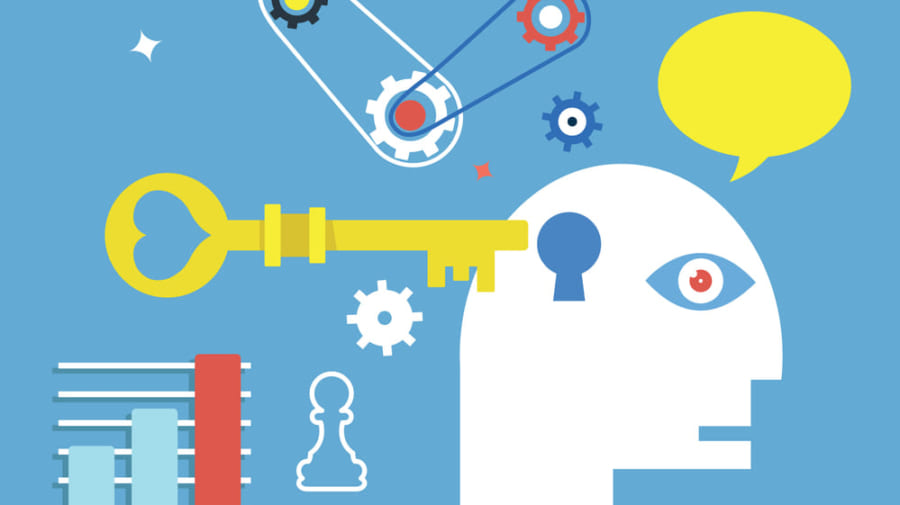氷=固体”は本当に正しいのか?
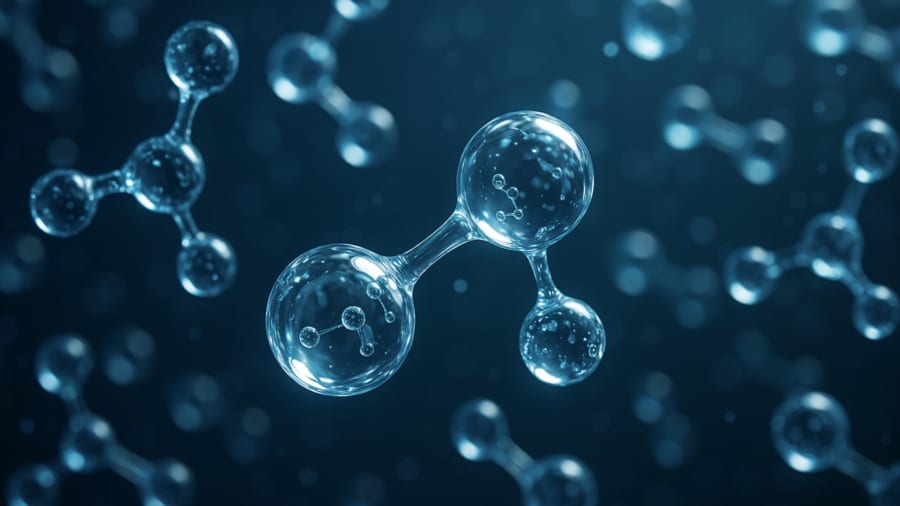
水ほど身近でありながら、その正体が完全には解明されていない物質は他にあまりないでしょう。
私たちは水が固体(氷)・液体(水)・気体(水蒸気)の三つの姿をとることを知っていますが、水にはそれ以外にも驚かされる顔があります。
例えば、氷は0℃未満では固い固体になりますが、その表面近くでは分子の結びつき(水素結合)が氷の内部よりゆるくて、不規則な動きをする薄い(液体に近い)層が形成されることが指摘されています。
つまり氷の表面には、氷と液体のあいだのような状態が既に身近な現象として存在しているのです。
子どもの頃に抱いた「氷=いつも完全に固体」という考え方は、教育上の簡略化であって、現実の氷は必ずしもそうではありません。
また、氷の表面で見られる「水のような状態」は、氷の滑りやすさの一因とされています。
コラム:スケートで滑れるのは圧力で氷が溶けているからではない
かつてスケートなどで氷の上を滑れる理由として「スケートブーツの刃の圧力によって氷が溶ける」とする圧力融解説が知られていましたが、現在では刃の圧力だけで氷を溶かして滑れるようにするには、必要な圧力や条件が現実的ではない(選手個人の体重程度では無理)ということが指摘されています。
では、「氷でも水でもない状態」とはいったい何なのでしょうか?
近年の複数の研究でも、中間状態の正体を解き明かそうと様々なアプローチが試みられてきました。
たとえば、コップの水を冷凍庫に入れて凍らせると、水分子はかなりしっかりと固定された氷になります。
一方、常温のコップの水では分子が自由に動き回る液体です。
しかし、ごく狭い場所に閉じ込められた水ではこの単純な二択が崩れることがあります。
ナノメートルサイズという極めて小さな空間に入った水は、周囲の壁との相互作用が強く影響し、普通の水とは異なる振る舞いを示すのです。
たとえば、壁に近い水分子は壁の原子とより強く結びつき/中心付近の水分子とは異なる動きをします。
結果として、壁に近い層・中間の層・中心部の層という三つの層が形成され、水分子クラスター(WMC)の内部に“小さな階層構造”ができあがります。
しかし、このような階層構造や氷と液体が入り混じったような状態を直接観察するのは非常に困難な挑戦でした。
その理由は、X線や中性子などを使った解析では、溶けかかって動いている水分子の細かな構造や運動を捉えるのが難しいためです。
では、研究者たちはこの“隠れた水の状態”をついにとらえることに成功したのでしょうか?




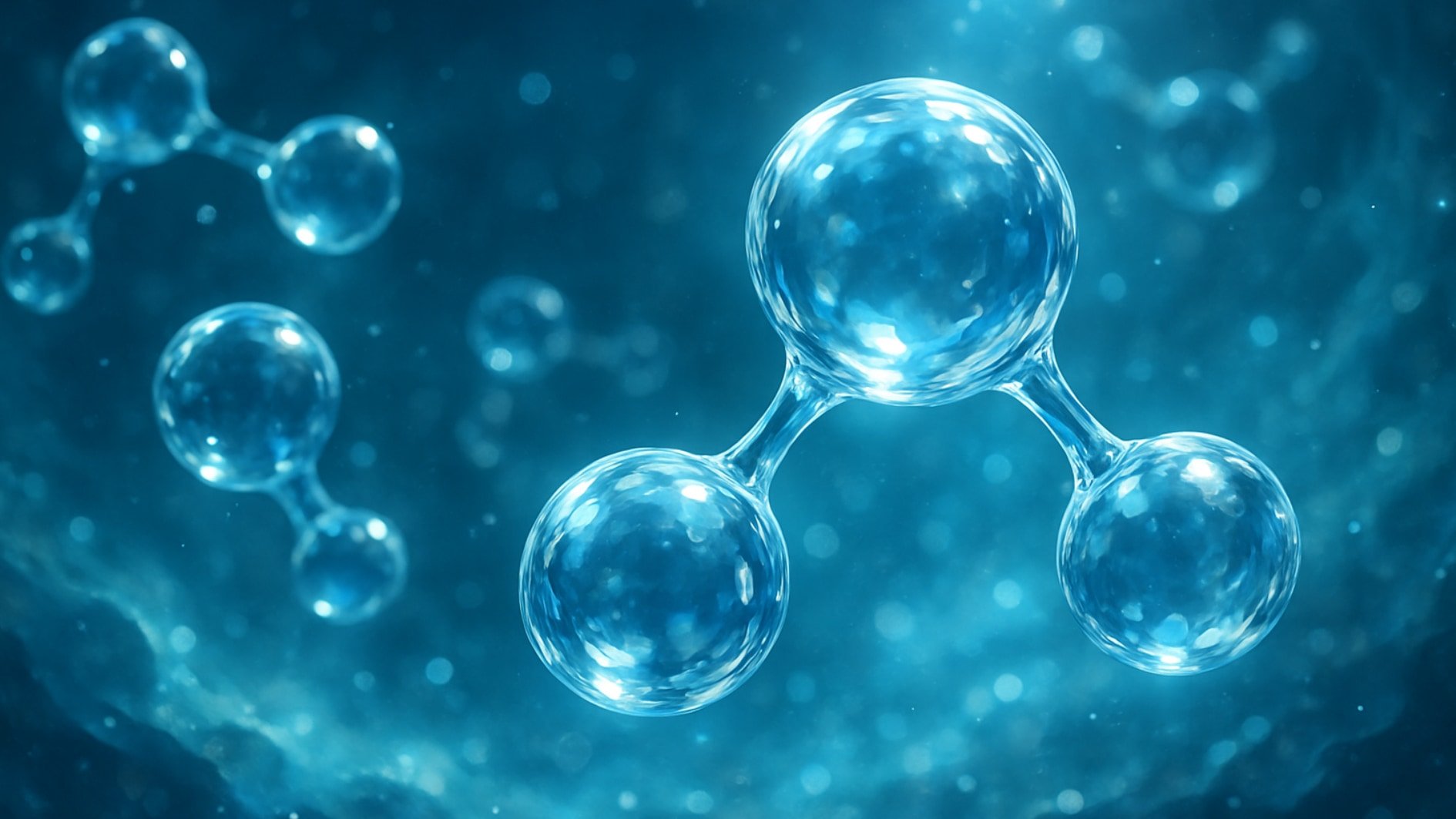























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)