日常のストレスと睡眠の関係を追跡
同じようにストレスになりそうな問題を抱えていても、ぐっすり眠れる人と、頭が冴えて一晩中眠れない人がいます。
この違いを説明する鍵として、研究者たちは「睡眠反応性(Sleep Reactivity)」という性質に注目しました。
これはストレスがかかったときに睡眠がどれほど乱れやすいかを示す指標で、いわば「寝つき悪さ」を数値化したものです。
この値が高い人ほど、少しの不安や緊張でも睡眠が乱れやすく、慢性的な不眠に発展しやすい傾向があります。
従来の研究では、この「ストレスと睡眠の関係」を“過去1か月”や“過去1年間”を振り返るアンケートで調べることが多く、試験前、仕事の締め切り、友人とのトラブルなど、日々の小さなストレスがその日の眠りに与える影響を細かく捉えることは困難でした。
そこで研究チームは、“日常のストレスが眠りに与える影響をリアルタイムで追跡する”という新しいアプローチを取りました。
14日間にわたり、日常生活の中で自然に起こるストレスの変動を観察し、ストレスが「思考の活性化」や「睡眠の乱れ」とどう関わるかを検証したのです。
特に、ストレスに敏感な人(高反応群)とそうでない人(低反応群)を比較することで、「眠れない夜」が生まれる仕組みを探りました。
対象は大学生264人で、事前テストにより睡眠反応性の高い人と低い人を各30人ずつ抽出しました。
参加者はいずれも健康で、睡眠障害やうつ病などの診断歴はありません。
2週間、腕時計型の睡眠計(アクチグラフィ/Actiwatch)で「寝つくまでの時間(入眠潜時/SOL)」「眠った長さ(総睡眠時間/TST)」「夜中に起きた回数」を記録し、指輪型のセンサー(Oura Ring)で「寝る直前の脈」を測りました。
また毎晩、その日に感じたストレス要因(人間関係、経済問題、学業など)とその強度(0〜100点の自己評価)を就寝前にスマホに入力してもらい、翌朝目覚めてから昨夜の“寝つきづらさ”(入眠前の認知的覚醒/PSAS-C)について答えてもらいました。
こうして得られたデータは延べ840夜分(参加者60人を14日間追跡)にもおよび、ストレスと睡眠の変動を高精度で追跡することができました。
このように、毎日の実測データを取ったという点が本研究の最大の特徴であり、従来のアンケート調査では見えなかった「眠りとストレスの関係」を可視化することに成功したのです。












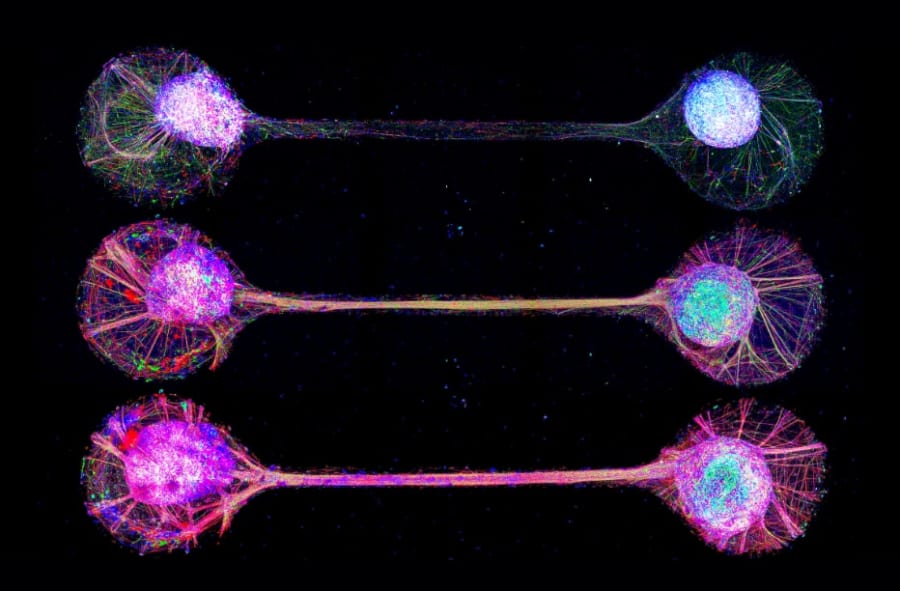


















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























