ストレスへの脆弱性とは「思考が止まらない」性質
こうしたデータを分析したところ、ストレスを強く感じた日の夜ほど、目が冴えて寝付きにくくなり、総睡眠時間を短くする原因となる傾向が示されました。
これは当たり前のことを報告しているように聞こえますが、注目すべきは、この影響が心拍数などの生理的高ぶりではなく、就床前の“思考の暴走”で主に説明できた点です
つまり、この研究が明らかにしたのは、「ストレス」から最も強く影響を受けるのが心や身体ではなく、睡眠の乱れであるという事実です。
そしてその原因として、「思考の止めづらさ」がカギである可能性が示されました。
興味深いのは、この「思考が止まらない脳の動き方」の個人差です。
研究チームは、日常的なストレスの影響を受けやすい人ほど、発想や思考を長く持続させる傾向が強いことを見いだしました。
つまり、ストレスに敏感な人は、単に心が弱いのではなく、思考を深める力が高い分、脳が休みづらいという特性を持っていたのです。
そのためストレスに弱く見える人は、問題を深く考え抜いたり、豊かな発想を生み出したりする力がある人なのかもしれません。
ただ、ストレスに対してはその力が悩みを反芻させ、心配事が止まらなくなり睡眠を阻害してしまいます。こうして起こる不眠の症状が、ストレスによる心身の衰弱のように見えるのです。
研究者たちは、このような脳の働き方を理解し、思考のスイッチを上手に切り替える方法を身につけることで、寝付きやすくなればストレス反応を軽減できる可能性があると述べています。
具体的には、認知行動療法(CBT-I)やマインドフルネス瞑想などが有効な手段とされています。
認知行動療法というのは、簡単に言えば、寝なければ行けないという脅迫的な考えをやめることです。
重要なのは、気になる問題に対する思考が止まらないという問題を自覚して、考えを逸らして自然に眠れる状態を作ることです。無理に布団に入って寝ようとすると、考えが収まらなくなってしまいがちです。
例えば「○時だから寝る」ではなく、実際に眠気を感じてから布団に入るようにする。20分以上眠れなければいったん布団を出て、静かにできる軽い行動(読書、深呼吸、照明を落としたリビングでお茶を飲むなど)をする。時計を見て時間を気にしないようにする。などです。
ストレスに弱いというと、なにか心理的な弱さに起因した問題に感じがちですが、実際は思考し始めると止まらないという性質に原因があるようです。
自分はストレスに弱いと感じる人は、自分のそんな脳の性質を理解することで、改善の道が見えてくるかもしれません。












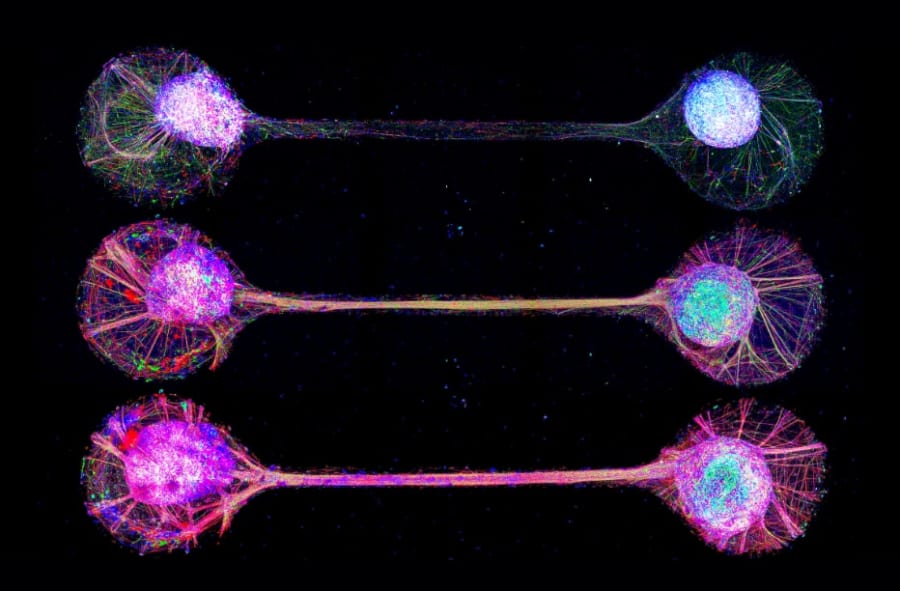


















![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




























寝る前の妄想が一番楽しいのに…。
書いてる同人小説とかネタは全部それ由来ですよ。
ハイテンションになると、朝まで眠れない これも一種の地獄だな
>例えば「○時だから寝る」ではなく、実際に眠気を感じてから布団に入るようにする。20分以上眠れなければいったん布団を出て、静かにできる軽い行動(読書、深呼吸、照明を落としたリビングでお茶を飲むなど)をする。時計を見て時間を気にしないようにする。などです
これで朝まで寝られないんですよね
ほんとにそれ。
で、翌日辛くなって負のループに。
睡眠に関して問題があると自覚されているタイプのかたは、
何でもいいですが手に職をつけて、社会の時間に左右されず働けるようなスタイルに持っていけると、生活がとても楽になりますよ。
フリーランス、個人事業主とか、そういうものです。
自分も布団に入ってから6時間寝れないとかザラで、長年困っていましたが、
今は、好きな時間に寝て好きな時間に起きれば良いので、毎日のストレスが激減しました。
みなさんの「眠れない悩み」というものは、
無理に社会の時間に自分を押し込めるから出るものです。
長生きは出来ないのかもしれませんが、
自分が快適に過ごせていけるなら、何時に寝て何時に起きたって良いと自分は考えます。