習慣が支配する私たちの日常
調査の結果、行動の「始まり(発端)」は65%が習慣によって引き起こされていました。さらに一度行動を始めると、「続ける・やり遂げる実行段階」は88%が習慣に依存していたのです。
つまり、私たちは自分で考えて行動を選んでいるように見えても、その大部分は自動的に進んでいるのです。
では私たちは基本的に自分の意思ではなく、無意識に支配されて行動しているということになるのでしょうか?
研究では一日の行動のうち76%は自分の意図に沿った行動であり、そのうちの46%が習慣によってはじまっていることが示されたと報告されています。つまりこの点を考慮すると私たちの行動は完全に無意識に支配されているわけではなく、多くの場合、習慣と意図が協力して働いていることがわかります。
さらに興味深いことに、運動のような行動では「始めるきっかけは習慣で決まる」一方で、「実際に続けるかどうか」では習慣の力が弱まるという特徴が見られました。
今後の課題
今回の研究は7日間と調査が短期間なため、長期的に習慣がどのように変化するかまでは明らかにできていません。また、参加者が自分で答える形式だったため、完全に無意識の行動を正確に測定できているかどうかには限界があります。
今後はより長期間にわたる追跡や、異なる文化や生活環境での比較研究が必要でしょう。行動の種類によって習慣化しやすいものとそうでないものがある点についても、さらに詳しい検証が期待されます。
習慣は敵ではなく味方
今回の研究結果は、私たちがほぼ“自動操縦”で生きていることを示していますが、それは必ずしも悪いことではありません。
むしろ、習慣は目標を助ける仕組みになり得ます。朝の歯磨きや寝る前の読書のように、望ましい行動が習慣化すれば、努力しなくても自然に継続できます。
「自由意志が失われている」と考えるより、「習慣が意図を支えてくれている」と考えた方が建設的です。
研究チームは、日々の行動を変えるには「やる気」だけでなく、“起動スイッチ(きっかけ)”を設計することが重要だと示唆します。
例えば「退勤後に10分歩く」「朝のコーヒーの前にストレッチ」など、同じ状況に同じ行動を重ねると、内蔵の“オートパイロット”が働きやすくなります。逆にやめたい習慣は、引き金になる状況を避ける・置き換えるのが近道です。
イラストや小説、楽器の演奏など創作的な活動をしたいのに最後までやり遂げられないというような人も、意思の弱さより習慣化が上手く出来ていないことの影響のほうが大きいかもしれません。
ある程度作業すると、スマホを弄りだしてしまうということが習慣化しているようなら、その習慣を見直す。作業自体始められない場合は、なんらかの習慣化するスイッチを作るということを意識すれば、無理なく目標を達成できるようになるかもしれません。
「自分の意思で決めている」と思っている日常行動の多くは、実は過去の経験で形作られた習慣が主導していました。しかし、それは私たちが無力という意味ではありません。習慣を味方につければ、むしろ人生を自分の望む方向に大きくデザインできる可能性が広がるのです。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















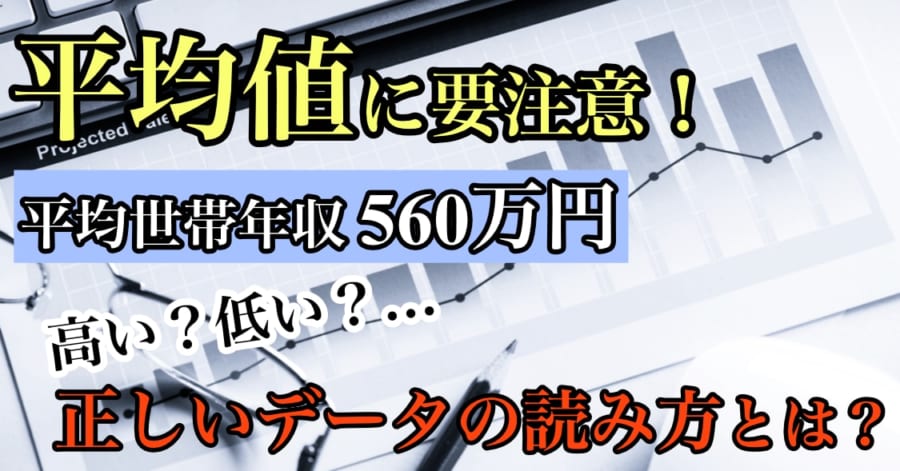
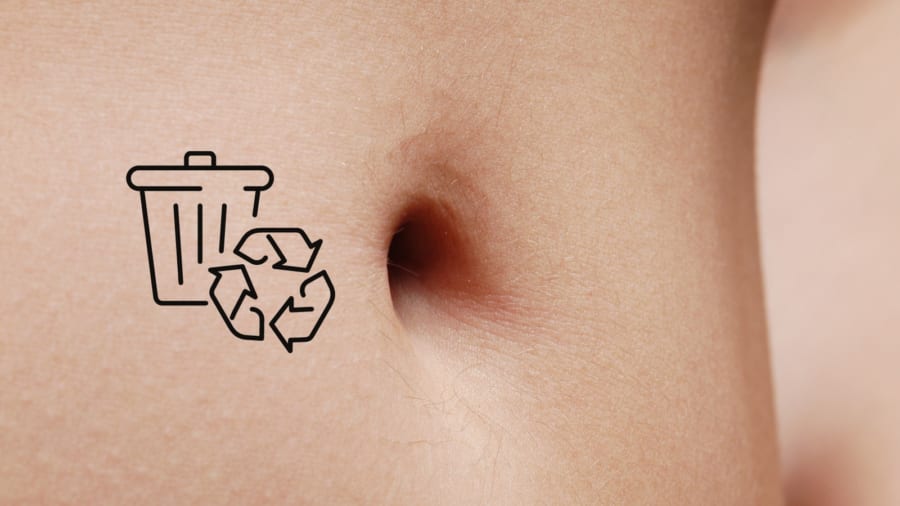






とりあえず着手してみるのがお勧めです。
着手してみると意外とスムーズに事が運ぶなんてことも多いですから。
習慣を刷り込みに置き換えてみると一目瞭然ですね。我々は些末な日常茶飯事を一々考えて処理しているわけではない。日常茶飯事の無数に及ぶ手順は、無意識的に処理されているし、そうでなければ日常生活に重大な支障をきたしてしまう。そこから少し高度な段階の決定も、類型パターンとして処理しょうとする。買い物、お出かけ、ありきたりのご近所付き合いなど。
ほとんどの日常生活上の習慣的な刷り込みで我々は生きている。そうでなければ大変なことになってしまいます。つまり精神の病。
やる気スイッチどこに有るんやろ思ってケツの辺り探したりしたけど見当たらんかったんや、起動スイッチ探さんとやる気スイッチ見つからんかった訳やね、納得。
ハミガキ、スマホ、英語、筋トレ…
習慣は、つまり動機の強弱、により定着化するものでしょうか…?
定着させるならまず「何をトリガーにするか」じゃないかな
「こうなったからこうしよう」が自動操縦なので、起きたらコーヒー飲もうとか何時には寝ようとか自然とトリガーと行動が連携するようになったら定着完了
一つのトリガーには一つの行動のみを繋げるようにすれば定着早いと思うし、何しようかどうしようか(選択肢複数)って悩むようだと自発的な行動選択が必要になって定着しないと思う
動機の強さそのものより、トリガー決めたらそのまま考えずに動くことが習慣化に繋がると思うよ。動機強ければ自然とそうなるだろうけど
確かに、一切運転を意識することなく、いつの間にか目的地に着いてる時とかが稀にありますが、これもそうなんですかね。
意識してないので、安全運転だったかどうかはわからないのですが(ーωー;)
あと、ノイズキャンセラーのスキルも何気に備わってますよね。
カエルの大合唱でやかましいはずなのに、その騒音に慣れすぎてて気づいてなかったりって記事見て、あぁ確かに経験あるわ〜ってなりましたね。
これは田舎限定かな?
まぁとりあえず、FF12のガンビット意識したら良さそうですね。
〔退勤した自分〕+〔10分歩く〕
〔邪状態の自分〕+〔たたかう〕
〔ドッグランにいる自分〕+〔デコイ〕
〔力仕事中の同僚〕+〔ブレイブ〕
〔会議中の同僚〕+〔フェイス〕
とかですかね?
以下は失敗例です。
〔目の前の階段〕+〔10往復〕
この組み合わせで熊本県の釈迦院に行ってしまうと、ほぼ確実にゲームオーバーです。
〔同僚1人〕+〔リポビタンD〕
この組み合わせだと、近くにいる同僚にリポデーを渡し続けます。
もはや威力業務妨害です。
もしガンビットをセットする場合は、よく考えてから組み合わせましょう。
自由意志もクソもねえ