「視覚」や「聴覚」より訴えが多い「認知」の障害
「物忘れ」や「集中力が続かない」といった問題は、これまで高齢者の課題と考えられてきました。実際に認知症などの病気は高齢期に多く見られるため、多くの人が「若いのにそんな悩みがあるなんて珍しい」と感じるかもしれません。
ところが最近の大規模調査では、状況が変わりつつあることが示されました。
アメリカでは「認知に関する障害(cognitive disability)」が、視覚や聴覚の障害を上回り、もっとも多く報告される障害となっています。ここでいう認知障害とは、病院で診断される認知症そのものではなく、「物忘れがひどい」「集中が難しい」「判断に迷うことが多い」といった日常生活での自覚的な困りごとを指します。
この事実は、認知における障害が多様な原因から生じる非常に広範な問題である可能性を示しています。しかし、こうした調査は横断的(人種や所得、教育の格差などを比較した一時的な調査)なものが中心で、長期的な変化を追った調査というものはあまりありません。
そこで今回の研究チームは、長期間実施されている大規模調査データを統合的に解析し、この問題の変化のパターンを見てみようと考えたのです。
研究チームは、CDCが毎年実施している全国規模の電話調査「行動リスク要因調査システム(Behavioral Risk Factor Surveillance System, BRFSS)」のデータを用いました。この調査は、全米の成人を対象に健康状態や生活習慣を尋ねるもので、信頼性の高い公衆衛生データとして広く活用されています。
解析の対象となったのは2013年から2023年まで(2020年は調査の混乱のため除外)の回答で、規模は約450万件にのぼります。対象は18歳以上の一般成人で、自分で「うつ病がある」と答えた人は除外されました。これは「気分の落ち込み」からくる記憶力の低下と、純粋な認知の問題を区別するためです。
研究者たちは統計モデルを用い、年齢や人種、所得、教育水準、さらには高血圧や糖尿病といった慢性疾患の有無まで幅広く分析しました。こうして「誰に」「どのような背景で」物忘れや集中の困難が増えているのかを丁寧に探ったのです。
すると予想外の傾向が見えてきました。なんと、若い世代で認知の障害を訴える人たちがほぼ倍増していたのです。















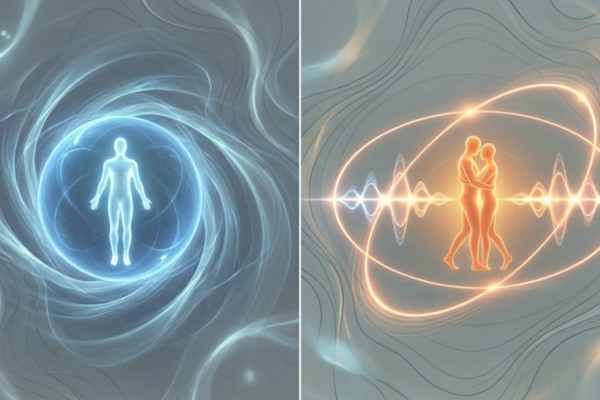




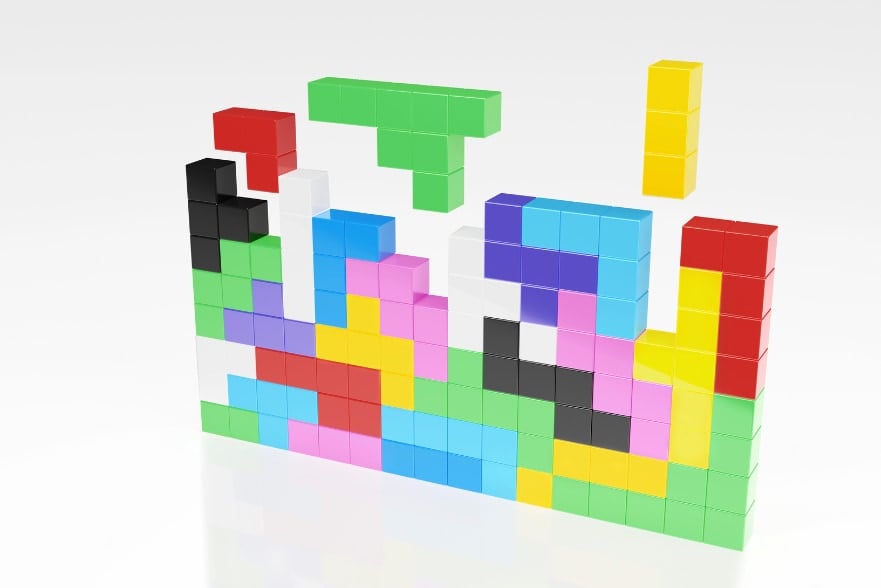









![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)



























