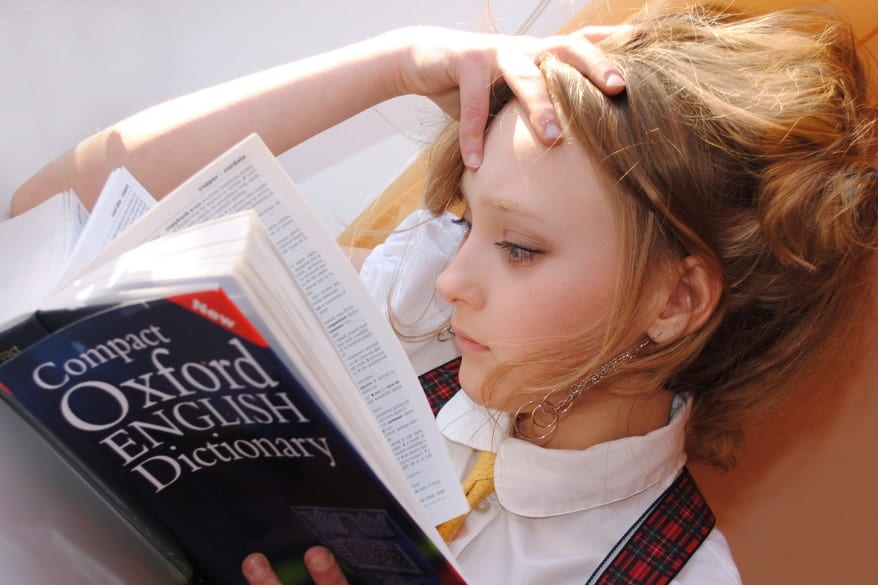脳のエネルギー源は「糖」だけではないのか?
人の脳は、体重の2%ほどしかないのに、全身のエネルギー消費の20%以上を占める「エネルギー大食い器官」です。
そんな脳のエネルギー源について、従来は「ブドウ糖(グルコース)を主な燃料として使っている」とされてきました。
糖分が切れると集中力が落ちる、頭が回らない――漫画などで知能の高いキャラクターがそんなこと言ったりしますが、これは実際科学的な報告に基づいているのです。
とはいえ、筋肉や肝臓など多くの細胞は、ブドウ糖だけでなく脂肪も燃料にしてエネルギーを作ることが知られています。
なぜ長い間、脳の神経細胞については、「脂肪を燃料にできない」と考えられていたのでしょうか?
その理由にはいくつかありますが、ひとつは、脳が極端にブドウ糖依存だという点です。この事が一般の人にもイメージしやすい事例として、低血糖になると人間はすぐに意識を失ったり朦朧としてしまうという問題があります。
1980年代の研究では、神経細胞に脂肪酸を与えてもほとんど利用されないように見え、脂肪を燃やす酵素の働きが極めて弱いと報告されていました。
そして脂肪を燃やすときに生じる活性酸素は不安定な分子で、DNAやタンパク質、細胞膜を酸化して傷つけてしまいます。多くの細胞はダメージを修復したり新しい細胞に置き換わったりできますが、神経細胞は再生が難しく、脂質の多い構造を持つため、特に活性酸素の被害を受けやすいと考えられてきました。
特に脳は全身の酸素の約20%を使う「酸素大食い器官」です。酸素を多く使う分、活性酸素が生じやすい環境にあります。そのため「神経は脂肪を燃やすのを避けているのではないか」と考えられるのです。
こうした背景から、脳は糖しかエネルギーとして利用しないという理解が定着してきました。
しかし1980年代の実験では、測定技術の限界もあり、脂肪の利用を検出できていないだけの可能性があります。
脳が糖しか利用しないといのは、完全に証明された問題ではありません。
こうした疑問点について、今回の研究チームは遺伝性神経疾患のある報告に目を向けました。それは遺伝性痙性対麻痺54型(Hereditary Spastic Paraplegia type 54, HSP54)と呼ばれる病気です。
全く聞き馴染みのない長い病名ですが、この病気では脚の筋肉が突っ張って硬くなり、歩きにくくなるといった症状が現れます。そしてその原因が脳の神経細胞の中にあるDDHD2という遺伝子の変異だとされているのですが、DDHD2は、細胞の中で脂肪を“燃料として使える形”に変える働きを持つ遺伝子なのです。
なぜ、脳内の神経細胞にある脂肪を燃料として利用するための遺伝子に異常が起きると、神経伝達に問題が起きるのでしょうか?
ここから研究者たちは「脳の神経細胞は実は脂肪も燃料にしているのではないか?」という疑いを抱くようになったのです。
そこで、クイーンズランド大学の研究チームは、この疑問を確かめるためにマウスの神経細胞を使って実験を行いました。
研究者たちが注目したのは、DDHD2という遺伝子が働くと細胞の中で作られる飽和脂肪酸(ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸)です。これが細胞にとってはエネルギーの材料になります。
研究者たちは、この飽和脂肪酸が神経細胞のエネルギー工場であるミトコンドリアに取り込まれ、燃やされてエネルギーにあたるATPを生み出しているのかどうかを調べました。
さらに、脂肪を取り込めないようにする薬を使って、エネルギーが減るかどうかを確認しました。もし脂肪が燃料になっているなら、この薬でエネルギーの産生が落ちるはずです。
逆に、外から「燃料としてすぐに使える形の脂肪」を補ってやると、DDHD2が働かずエネルギー不足になっていた細胞でも、再び元気を取り戻すのかどうかも調べました。




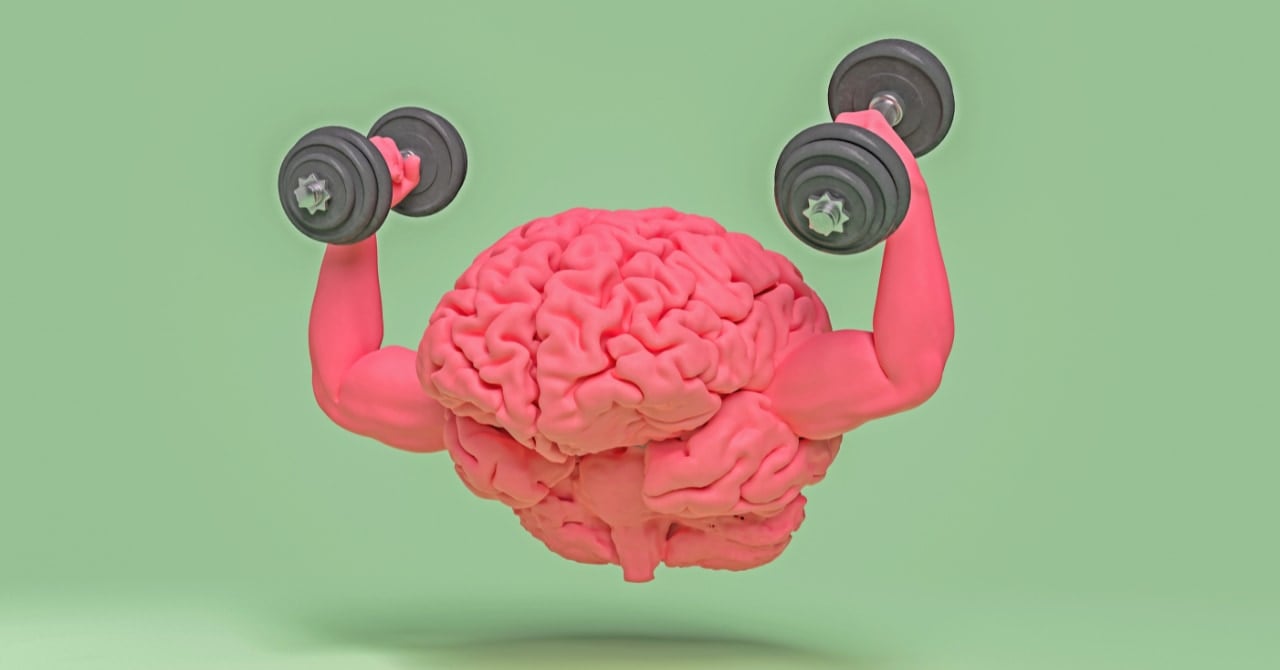





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)