脳は”脂肪”も燃やしていた
実験の結果、脳の神経細胞は、DDHD2という遺伝子の働きによって生み出される飽和脂肪酸を、ミトコンドリアに送り込んで燃やし、ATPと呼ばれるエネルギーを作っていることが明らかになりました。
これによって神経のエネルギーを支え、シナプスの機能維持にも寄与していることが確認されたのです。
この発見は、「脳は糖だけを燃料にする」という単純な考えを更新するものです。
研究チームがこの実験においてマウスの大脳皮質ニューロンでDDHD2が脂肪酸から得られるエネルギーを計算したところ、細胞が安静時に必要とするエネルギー量(基礎代謝)のおよそ20%に相当することがわかりました。この数字は培養細胞での実験から推定された割合のため、実際の脳が脂肪によるエネルギーをそれだけ利用しているとは言えませんが、脳の神経細胞が糖だけでなく脂肪も利用している可能性を示す重要な証拠となります。
また、脂肪を取り込めないようにするとエネルギーが目に見えて落ち、逆に“すぐ使える形の脂肪”を少量補うと、弱っていた細胞のエネルギーやシナプスの働きが回復することも示されました。
こうした報告を聞いて、一般人として気になるのは、「頭をフル回転させると痩せるのか?」という疑問です。
しかし残念ながら、今回示された脂肪の利用は、”予備電源”のような役割であり、体重が目に見えて減るほどの消費量ではありませんでした。
「頭を使うとお腹が減る」という感覚があるとしたら、それはストレス反応や心理的な要因など複数の仕組みが関わった現象と考えられ、この研究は特にその現象を直接説明するものではありません。
また本研究は、実際に体内で脂質がどのように神経細胞に届くかを完全には再現していないという限界があります。
実験では培養された神経細胞に脂肪酸を直接与えるという方法を使っており、血液脳関門を通る脂質の供給経路を模した実験ではありません。
血液脳関門では液体に溶けにくい大きい分子は通ることができません。脂質は溶けにくい物質のため脳関門を通過できないのです。
つまり、この研究は「神経細胞が脂肪酸を燃料にできる可能性」を示す重要な証拠ですが、それが体内で実際にどのように行われているかを確定させるには、さらなる実験と検証が必要です。
さらに、今回の研究はマウス実験であり、この仕組みが人間の脳でも同じ規模で働くのかは、臨床研究で慎重に確かめる必要があります。
まとめると、脳は状況に応じて糖と脂肪を使い分ける柔軟なエネルギー戦略を持っており、糖のみに頼っているわけではない可能性がある、というのが今回の報告の重要な点です。
そのため頭がいい人には痩せてる人が多い、とか難しいこと考えるとお腹が減る、という感覚を抱く人がいるとしたら、それは今のところ、たまたまとしか言えないでしょう。
しかし今回の知見は、神経の病気や老化に関わる新しい治療のヒントになるかもしれません。




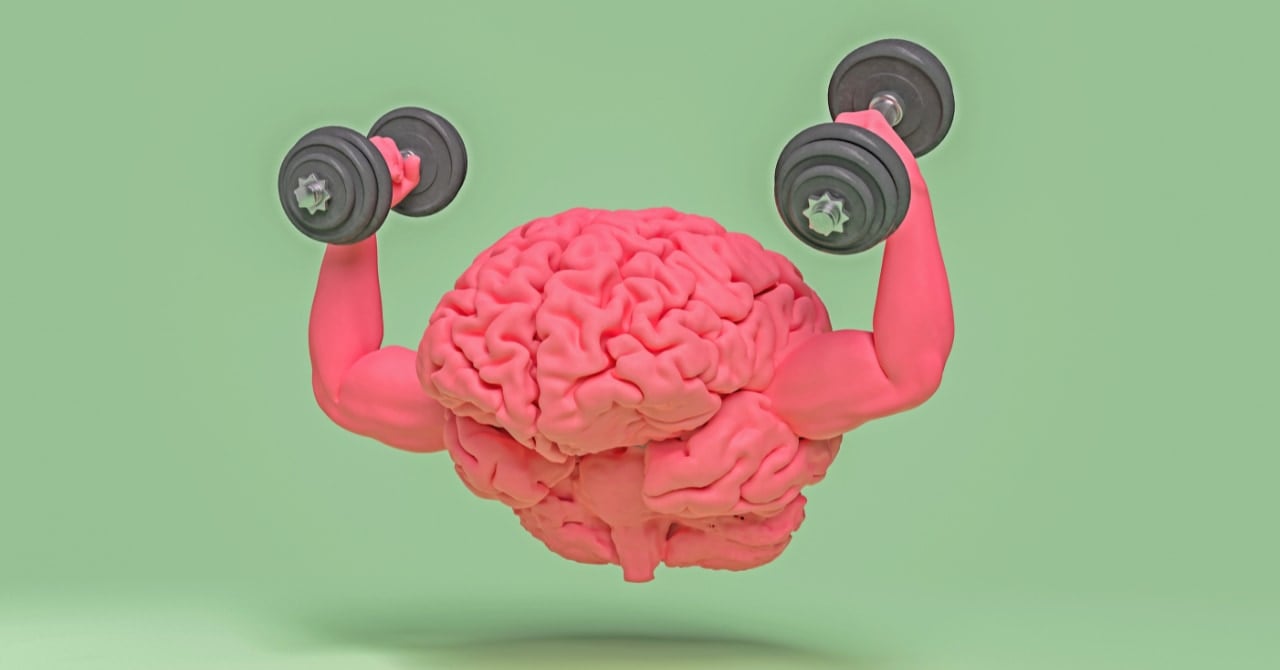






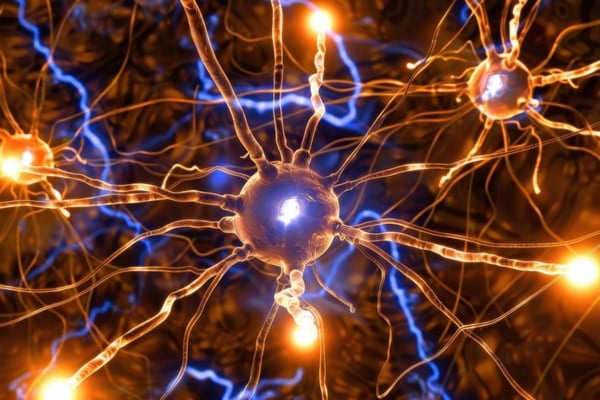
















![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)





















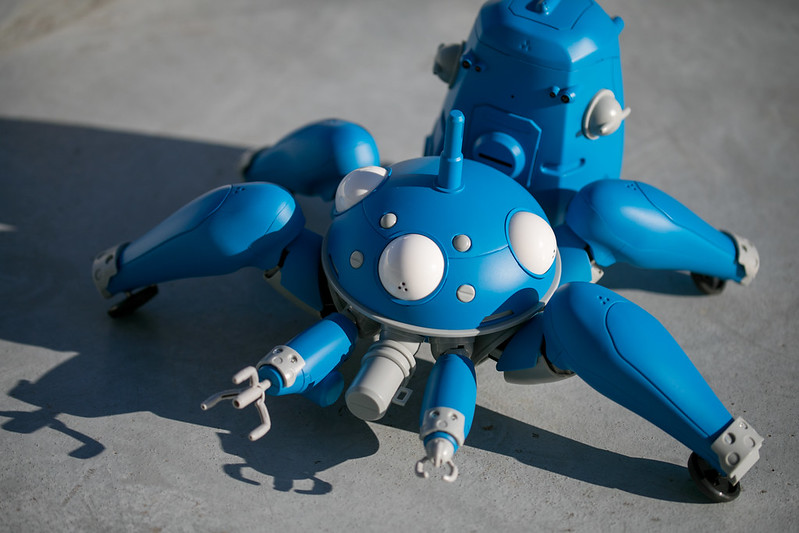






普段は通れないけど脳の細胞そのものは脂肪もエネルギーにできるのなら、何か緊急の事態が起きてエネルギーが必要だというときには直接脳内に脂肪放り込めばとりあえずはその場をしのげるということですね。
救急医療とかでは出番あるのでは?
脂肪酸の分解によって生じるケトン体が脳のエネルギー源になることは以前から知られていますね。
糖尿病が進んで糖代謝が障害されて補償的にケトアシドーシスになっている方でも、普通に暮らしてらっしゃる方も多く、そういうことだろうと思ってました。