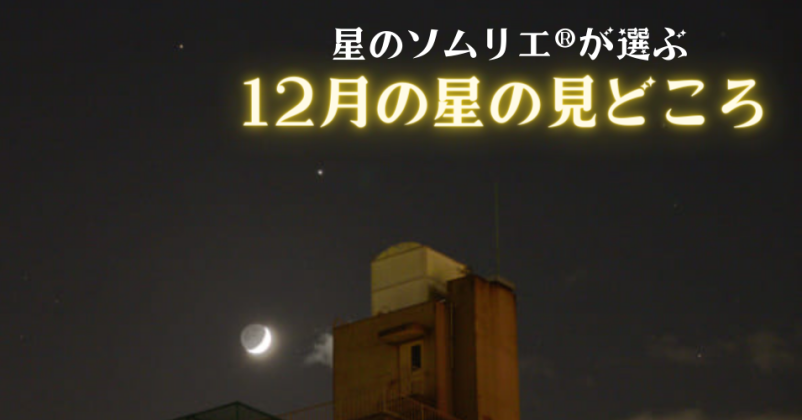「あんなに目立って大丈夫?」派手な魚の疑問
日本周辺の海では基本魚は地味な色をしています。
しかし透明度の高い南国の海にいる熱帯魚は、小魚までが非常に色鮮やかです。
なぜ同じ魚なのに、これほど色彩や模様が異なるのでしょうか?

大きな要因の1つは、南国の海は、太陽光が強く、水も澄んでいて光が深くまで届くため、水中でもさまざまな色がはっきり見える環境が広がっているからです。
深海や寒帯の濁った海では光が届かず、色の違いが意味を持ちません。
とはいえ普通に考えると、小さな魚が目立つ派手な色彩をしていることは生存に不利に働くように思えます。
「これほど目立っていたら、捕食者に狙われやすくなるのでは?」というのは、ごく自然な疑問です。
これについては、透明度の高い海なら派手になるというわけではなく、実際は隠れる場所が多いから目立っても大丈夫という理由があります。
例えば、アマゾンは比較的濁っていますがそこに棲む淡水魚ネオンテトラは、派手な色をしています。これは群れで生活しており比較的近距離で仲間を見つけるのに派手な色が役立つからだと考えられています。
一方、イワシなどは捕食圧が高いため、透明度の高い外洋に群れで集まって生活していても海中で見つけやすい色には進化していません。
そのため、熱帯の海に生きる魚たちは、サンゴ礁などの複雑で入り組んだ隠れ場所に支えられながら、目立つリスクを上回るだけの利点があるから派手なのだと考えることができます。

また、南国の透明な海は人間の目には美しく生命に満ちた楽園のように感じられますが、科学的に見ると「栄養が乏しい海」でもあります。
植物プランクトンの成長に必要な栄養塩は、通常陸地から川を通じて海に注がれるため、大陸から遠く離れた太平洋の真ん中は極端に栄養不足の状態です。
こうした場所では食物連鎖の出発点が限られているため、実は魚たちにとっては厳しい環境で、生き残りをかけた競争はとても激しいのです。
そうした環境では、通常の海とは異なる戦略が必要になってきます。色彩で「目立つこと」も、魚たちの重要な生存戦略の1つであり、仲間とのやりとりや、敵との駆け引きに繋がっているのです。
では具体的に、派手な体色はどんな戦略を生むのでしょうか?




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)