透明な海で進化した魚たちの色彩戦略
まず透明な海では色彩が水中のコミュニケーション手段として機能しています。
たとえば、クマノミは縞模様の数を認識していて、同族かどうか区別しているという報告があります。
また、ミノカサゴのように毒を持つ魚は、派手な色によって自らの危険性を周囲に伝えることで、捕食されにくくなるという“警告色”の機能を果たしています。
さらにはこの有毒種にそっくりな色合いを真似ることで自らを守る“擬態”の戦術を取る魚たちもいます。
また他の魚の体表を掃除する「クリーナーフィッシュ」として知られるホンソメワケベラは、青と黒の縞模様が目印となっていますが、ニセクロスジギンポという魚はその姿と動きを模倣して、自分を掃除魚と誤解させることで捕食されるのを避けたり、勘違いして近づいてきた魚のヒレを食べるという行動を取ったります。

このように、海が透明で色が機能する世界だからこそ、それを利用した騙し合いも進化しており、水中の色彩は単なる美しさを超えた複雑な意味を帯びているのです。
すべては「見える」環境だからこそ成立する視覚に訴える戦略が、南の海では進化によって洗練されてきたのです。
さらに興味深いのは、ある種の魚たちが、成長とともに体の色を大きく変えていくことです。
たとえばスズメダイやベラの仲間には、幼魚と成魚でまったく異なる色を持つ種類が多く知られています。
幼い頃は周囲の群れや岩陰に紛れるような控えめな色合いで過ごし、やがて成熟すると、縄張りを持ち自己を主張する必要から、鮮やかな色彩へと変化するのです。
また、性別の変化に応じて色が変わる魚もいます。
ベラやブダイの一部の種類では、成長に伴って雌から雄へと性転換を行うことがあり、それにともなって体の色や模様も大きく変わります。
こうした色の変化は、その個体の社会的な立場や役割の変化を、周囲に伝えるための信号としても機能しているのです。
一方冷たい海や深海のように、光がほとんど届かない環境では、そもそも色を見せるという手段が使えません。そうした場所では、魚たちは目立つ必要もなく、地味な色を選び、視覚ではなく触覚や音、動きといった別の方法でコミュニケーションを取っています。
環境が変われば、使われる言語も変わります。もし熱帯魚が「カラフルな衣装をまとったパフォーマー」だとすれば、暗い場所の魚は「静かな舞台でしぐさを磨いた演者」と言えるのかもしれません。
派手な魚たちにとって、色は恋の武器であり、敵への警告であり、仲間への合図です。
透明な海と派手な魚――その裏にある静かな“生存のドラマ”を知れば、水族館や海の景色も違って見えてくるはずです。


























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)
























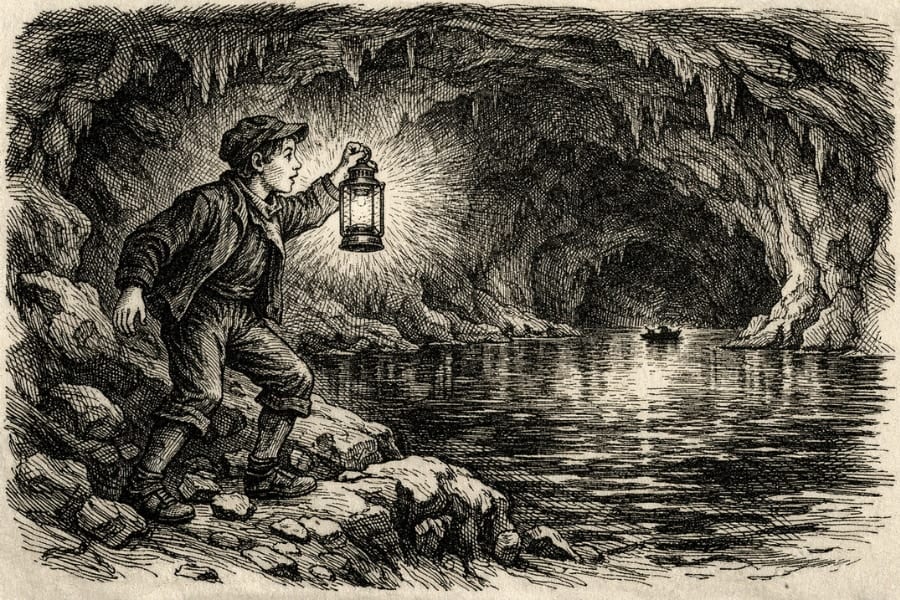



まず、あの派手な色は魚たちにはどう見えているのかを説明して欲しい。例えば蝶々は派手に見えて蝶々自身からは雌雄の区別しかできていない。
なるほど、いろいろ調べた中でもっとも納得のいく分かりやすい解説でした。