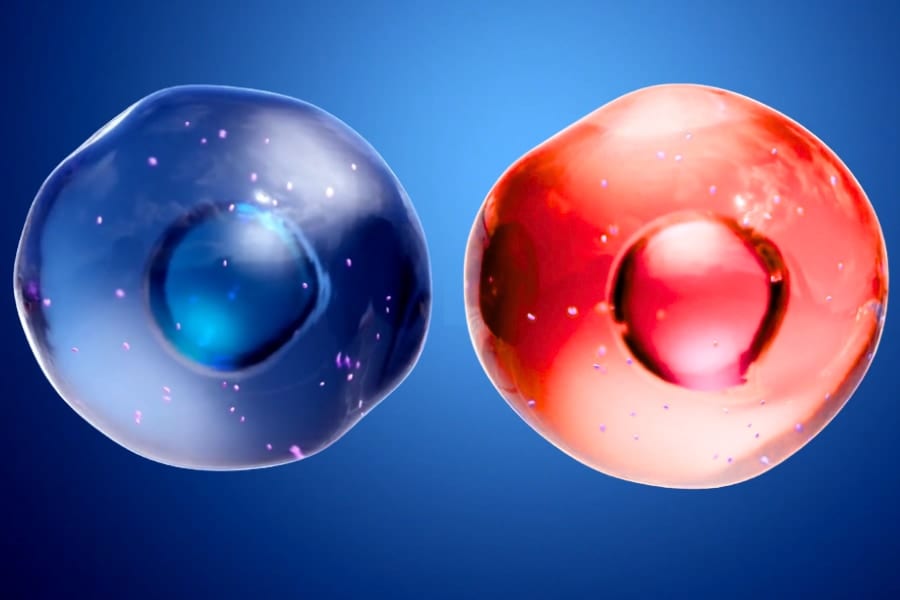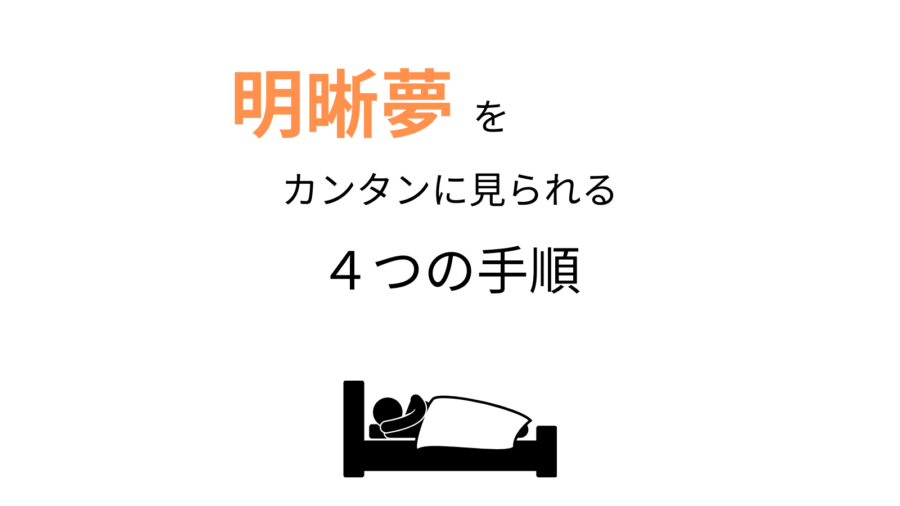病気なら動かないほうがいいのに・・・

病気なら体力を温存するためにおとなしくしているのが普通です。
私たち自身も、風邪やインフルエンザにかかると、体が重くなり、走るどころか階段を上るのもつらくなります。
動物にとっても「動かないこと」は、体力温存のための基本戦略に見えます。
しかし、その病気が致死的(死亡率ほぼ100%)だった場合はどうなるでしょうか?
実は両生類の世界には「カエルツボカビ症」という恐ろしい病気があります。
カエルツボカビ症はカエルなど両生類の皮膚に感染する真菌(菌類)による病気で、1990年代末の発見以来、世界中で多くのカエルを死に至らしめてきました。
皮膚に取り付くカビが呼吸や水分調節といった生命機能を阻害し、カエルは衰弱死してしまうのです。
致死率が極めて高いため、野生下で感染が広がれば集団が全滅する例も報告されています。
当然、病気に侵されたカエルは体力を奪われ、動きも鈍くなるのが通常です。
実際、この病気は500種以上の両生類で個体数減少を招き、少なくとも90種以上を絶滅させたとも報告されています。
コラム:日本のカエルが無事な理由
カエルツボカビ菌は、南米やオーストラリア、北米などでは、感染が広がったあとにカエルが大量死し、種ごと姿を消してしまった例もあります。それに対して、日本や韓国、中国などの東アジアでは、菌そのものは見つかっているのに、同じような大規模な絶滅ラッシュは、これまでのところほとんど起きていません。
この差を理解するカギが、「病原菌の地元で長いあいだ一緒に暮らしてきた種」と「遠く離れた場所からやってきた種」との違いです。ツボカビは、系統の調査から、東アジアを起源とする古い病原菌だろうと考えられています。つまり、日本や東アジアのカエルたちは、この菌ととても長い時間スケールで同じ土地を共有してきた「地元の住民」です。地元の住民と病原菌のあいだには、長い時間をかけて「共進化」という駆け引きが続きます。病原菌のほうが強すぎて宿主を片っ端から殺してしまうと、自分も増え続けることができません。逆に宿主のほうも、完全に無敵にはなれないにしても、「重症になりにくい」「うまく共存できる」ような体の仕組みを少しずつ身につけていきます。
一方、南米やオーストラリアのカエルたちは、もともとツボカビがいなかった世界で進化してきた「遠隔地の住民」であり、人間の移動やペット取引などを通じて、近年になって突然この菌を“押しつけられた側”だと考えられます。そのためカエルツボカビに対して免疫がなく100%近い死亡率や種の絶滅などが起きてしまったと考えられます。
オーストラリアに生息するベローアマガエル(Litoria verreauxii alpina)も1980年代以降に生息域が80%以上失われ、個体数も大きく減少し、初めての繁殖シーズンのあいだにほとんどが命を落としてしまう絶滅寸前の状態にあります。
しかし不思議なことに、このカエルは病気に感染すると繁殖行動が活発化する現象が以前から報告されていました。
ある先行研究によれば、感染したオスは未感染のオスよりも交尾の回数が約31%も増加したのです。
生物学には「終末期の繁殖戦略(ターミナルインベストメント)」という仮説があります。
これは、命の危機に直面した動物は生存や免疫よりも最後の繁殖にエネルギーを注ぐという戦略で、昆虫から鳥類、哺乳類まで様々な動物で報告されています。
つまりほぼ確実な死が待っているなら、今のうちに子孫を残そうとする本能的な選択です。
そこで今回研究者たちは、ベローアマガエルたちが病気にかかると、温度への強さやジャンプ力などの体の性能がどう変わるのかを調べることにしました。




























![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)