なぜ踊りと子守唄がないのか?
この意外な発見をきっかけに、研究者たちは一つの問いに向き合いました。
「もし本当に人類に普遍的な行動であれば、なぜ北アチェには踊りと子守唄が存在しないのか?」
そこで注目されたのが、文化的な伝承と人口動態の変化です。
北アチェは20世紀まで遊動的な狩猟採集民として暮らしてきましたが、度重なる外部からの迫害や感染症によって人口が激減し、その過程で貴重な文化の多くを失ったと考えられています。
実際、北アチェには弦楽器や集団音楽、思春期の通過儀礼、シャーマニズムなど、他のアチェ系集団に見られる文化がごっそり欠け落ちています。
つまり、踊りと子守唄もかつては存在したかもしれないが、人口減少の中で失われた可能性があるのです。

一方で本研究では、北アチェの成人たちに子守唄が存在しないものの、子どもをあやす際に「ふざけた口調」「変顔」「笑い」などを使うことが確認されました。
つまり、赤ちゃんをあやす必要性は北アチェにも存在していましたが、子守唄という形にはなっていなかったのです。
またダンスについても同様で、狩猟の合間や儀式の場面でも踊る姿は一度も見られませんでした。
研究者たちはこのことから「ダンスや子守唄は、生得的な行動ではなく、文化として発明され、共有され、伝承されるものだ」と結論づけています。
この結論は、音楽やダンスの起源を進化的に説明しようとする多くの理論にとって大きな示唆を与えます。
たとえば「笑顔」は生まれつき備わった反応であり、誰に教えられなくても自然とできるものですが、「火起こし」は学ばないとできません。
これを踏まえて研究者らは、ダンスや子守唄は笑顔ではなく、火起こしに近いもので、後天的に「学ぶべき文化」であると位置づけています。

今日のように、世界中で似たような音楽や子守唄の形式が見られるのは、本能ではなく「文化の収斂進化(しゅうれんしんか)」によるものかもしれない、と研究者らは指摘します。
(※ 収斂進化:別々のグループで独自に同じ形質が進化する現象のこと)
つまり、人々が似たような目的(赤ちゃんをなだめる、集団の団結を高めるなど)のために、独立して似たような手段を生み出してきたという考え方です。
そして今回の研究が示した最大の意義は「人類に普遍だと思われていた文化的行動も、失われることがある」という事実に他なりません。
ダンスや子守唄がない社会は、極めて稀かもしれませんが、そうした社会が存在したということ自体が人間文化の多様性と同時に、その脆さを浮き彫りにしています。
私たちが当たり前だと思っている行動も、実は学び伝えられた文化に過ぎない。 そのことを北アチェの静かな暮らしが教えてくれるのです。

































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)




















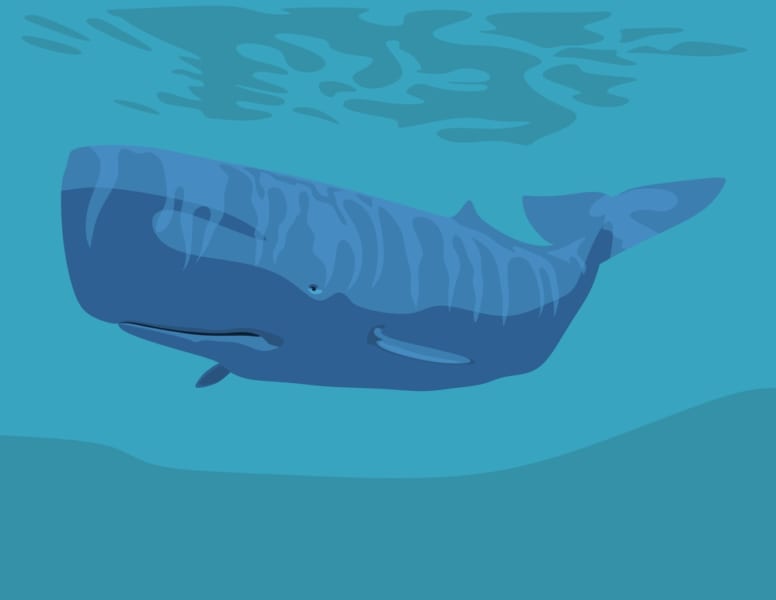







失われたら永遠に戻らないということもないでしょうから数千年後には彼らも踊ったり子守唄を歌ったりしてると思います。
そして数万年後にはそれらの行動が自然に起きるものだという仮説のもと、はるか昔強大な勢力を誇ったもののいつの間にか没落して文化のない暮らしをしている部族を調査して、新たな知見を得るのでしょう。
その部族っていうのは我々の子孫ですよ。