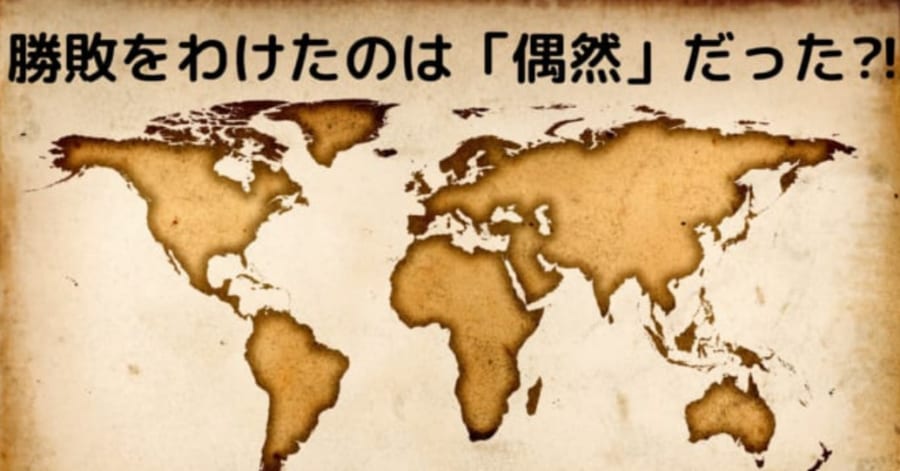一部の警告に慣れたドライバーは、「急ブレーキ」や「速度超過」が増えると判明
分析の結果、非常に興味深い傾向が浮かび上がりました。
まず、死角検知を搭載している車両では、急ブレーキの発生率が6.76%減少し、速度超過の発生率が9.34%減少していました。
これは、ドライバーの運転行動が穏やかで安全になっていたことを示しています。
一方で、前方衝突警告と車線逸脱警告を搭載している車両では、急ブレーキの発生率が5.65%増加し、速度超過の発生率も5.34%増加していました。
緊急性の高い警告では、使い続けるうちに急ブレーキの頻度が増加し、ドライバーの運転がより危険になる傾向があったのです。
さらに研究チームは、時間の経過とともに、ドライバーがこれらのシステムに慣れるにつれ、両方の影響が拡大していくことも発見しました。

なぜ一部のADASでは、ドライバーの安全意識が低下してしまったのでしょうか。
研究チームは、心理学の概念に基づき、「緊急の是正を求めるADAS」と「情報提供のみを行うADAS」が、それぞれ異なる思考モードを引き起こすと考えています。
前者の警告は、ドライバーに即座の無意識な反応を引き起こします。
このことが続くと、ドライバーは「警告してくれるから大丈夫だろう」と無意識に判断し、安全運転への注意を怠ったり、危険な状況でもシステムに頼ってしまったりするようになります。
結果として安全運転に対する学習が妨げられ、行動が悪化するのです。
一方、後者の死角検知のような情報提供のみを行うADASでは、瞬時の反応を必要とせず、ドライバーに対して、「見えないところに車があるということは……まずは確認して……」といった具合に、慎重かつ論理的な思考を生み出します。
そしてこの思考は、「自分の経験を振り返る」などの学習へと導き、それが安全運転へと繋がっていくのです。
同じADASでも、ドライバーに与える影響がここまで異なるという結果は興味深いものです。
しかしこれらの結果だけで、一部のADASが不要であると決めつけるべきではありません。
なぜなら、どちらのタイプのADASでも、衝突の低減には効果的だったからです。
今回の研究は、ADASの設計において「人間の心理的反応を無視できない」ということを明確に示しています。
警告の種類やタイミング、出力の仕方が、ドライバーの行動に大きな影響を与えるのであれば、単に音を鳴らせば良いという設計思想では、かえって危険を生むおそれがあります。
今後は、ドライバーの注意力を維持しながら学習を促す設計がより一層求められるでしょう。





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)