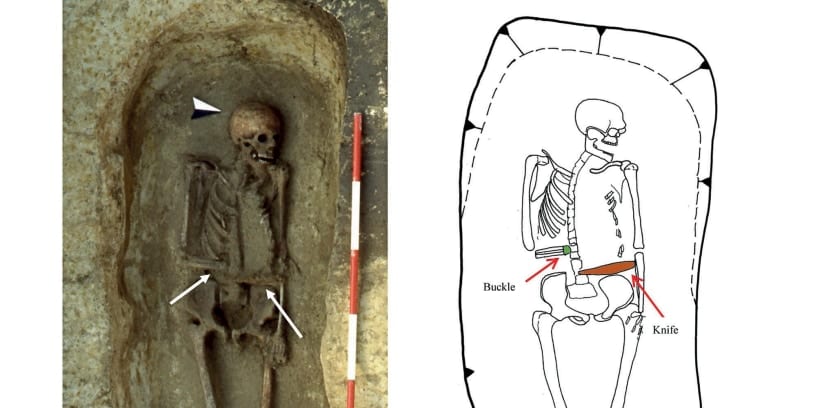東南アジアを結んだ古代貨幣ネットワーク
研究者たちは今回、東南アジア本土各地で発見された245枚の銀貨を精密に分析。
その多くは片面に「昇る太陽(Rising Sun)」、もう片面に「シュリヴァツァ(Srivatsa)」と呼ばれるインド古来の宗教シンボルが刻まれていました。
シュリヴァツァは、古代インドの宗教・神話に登場する文様で、繁栄や幸福の象徴とされます。
仏教やヒンドゥー教の初期遺物にも見られ、宗教的・文化的なつながりを示す重要なモチーフです。

これらの銀貨は「ダイ」と呼ばれる型を使った鋳造方式で作られました。
無地の金属円盤を型に押し当て、両面に模様を刻印する技術です。
この方法は同じ型を繰り返し使えるため、遠く離れた地域で同じデザインの硬貨が流通する可能性があります。
古代中国の史書には、紀元2世紀の段階で東南アジア諸国が近東から中国に至る交易ネットワークの重要拠点であったことが記録されています。
発掘調査でも、ローマのガラス器、インドの宝飾品、ペルシャや西南アジア、中国の陶磁器など、多様な輸入品が出土しており、広域的な交易の存在を裏づけています。
しかし、こうした銀貨は、ローマや中央アジアの古代通貨に比べて研究が進んでおらず、多くの場合、現代の国境を基準に分類されてきました。
そのため、本来の経済的・文化的ネットワークの全貌は見えていませんでした。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)