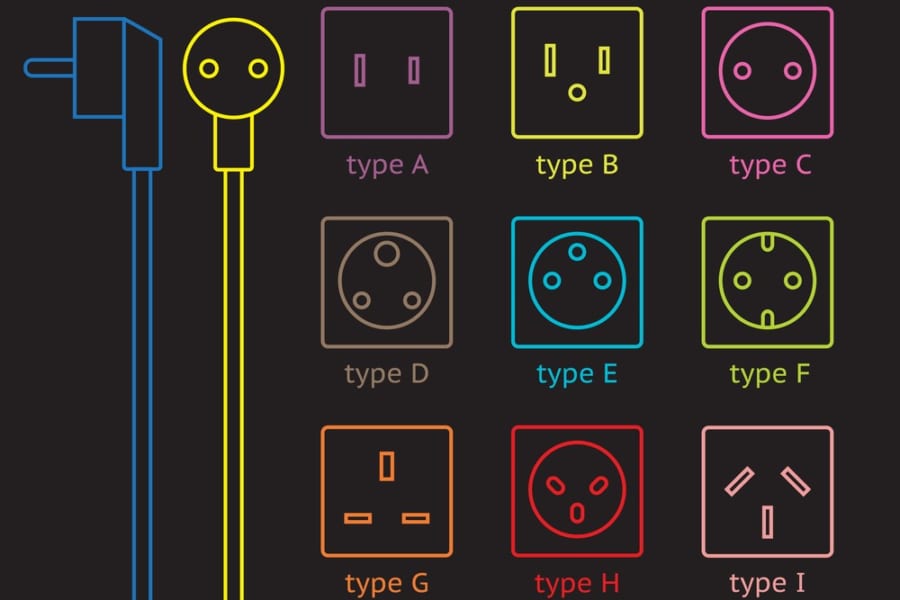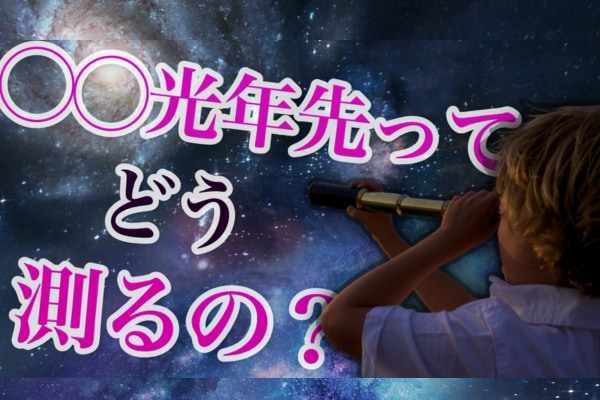かつて人類は「夜に2回眠る」のが普通だった
現代人にとって「睡眠はまとめて1回で取る」のが常識となっていますが、それは意外にも新しい習慣です。
歴史をひもとくと、人類の多くは何千年ものあいだ、1晩の睡眠を「2回」に分けてとる分割睡眠が当たり前でした。
この分割睡眠は「ファーストスリープ(最初の睡眠)」と「セカンドスリープ(2回目の睡眠)」と呼ばれ、まず日が暮れてから数時間寝た後、夜中に一度目覚めて1時間ほど過ごし、再び朝まで眠るというパターンが一般的でした。
この「夜中の目覚め」は何も特別な現象ではありません。
ヨーロッパ、中東、アフリカ、アジアなど、さまざまな地域の歴史記録や文献に「最初の眠りの終わり」「二度目の眠り」といった表現が登場します。
たとえば、古代ギリシャのホメロスやローマ詩人ウェルギリウスも「最初の睡眠の終わりの時刻」について記しています。
では、その“真ん中の時間”に人々は何をしていたのでしょうか?
ある人は火の番や家畜の世話など家事をこなし、またある人はベッドに横になったまま祈りや瞑想をしたり、直前に見た夢を振り返ったりしていました。産業革命以前の手紙や日記には「夜中に起きて本を読んだ」「静かに家族と話した」「隣人とこっそり会話を楽しんだ」といった記録も残っています。
さらに興味深いのは、多くの夫婦がこの夜中の覚醒タイムを親密な時間に使っていたことです。
夜を2回に分けることで、生活に自然なリズムと“区切り”が生まれ、特に冬の長い夜には「真ん中に明確な休憩」があることで、だらだらとした不安や孤独感を和らげていたと考えられます。
実際、人工照明も時計もない環境で生活する実験を行うと、多くの人は数日でこの「2回に分かれた睡眠」パターンに自然と戻ることが知られています。
2017年のマダガスカル農村の調査でも、電気のない集落の多くの人々が「夜中に一度起きてまた寝る」という伝統的な睡眠習慣を続けていたことが確認されています。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)