払う人と払わない人、その心理傾向の違い
心理学やメディア研究では、ガチャやスーパーチャットのような“効果や上限が不明瞭な消費”を行う人には、いくつか共通する傾向が見つかっています。
まず大きいのは「社会的な動機」です。
投げ銭や課金アイテムは、単なるお金の移動ではなく、相手との関係や自分の存在を可視化する行為です。配信者から名前を呼ばれる、特別な演出が表示される、視聴者コミュニティ内で注目されるなど、「人から認められる」ことが直接的な報酬になります。
ある調査では、投げ銭経験者の多くが「推しの活動を支える満足感」や「感謝される喜び」を消費の理由に挙げています。
次に目立つのは「即時の反応や偶然の報酬に敏感」なことです。
ガチャのように結果がランダムな仕組みは、心理学でいう「変動比率スケジュール」という強化パターンに似ており、予測できないご褒美が与えられると強く惹きつけられます。こうした偶然性への感受性が高い人は、刺激を求める傾向や衝動性も高いとされます。
ただ、ここまでのことは言われるまでもなく、やっている本人も自覚している部分でしょう。
そして、消費行動の差を明確に分ける重要な心理傾向が「マテリアリズム傾向(Materialism)」です。
これは、お金を単に貯めることには魅力を感じず、お金の使い方を外部に可視化することで自分の存在や成功をアピールし、他者からの評価や社会的地位を得ることに意味を感じる価値観を指します。
そのためマテリアリズム傾向が高い人は、ブランド品や高級体験などへの出費に価値を感じやすい傾向があります。

同様にデジタル空間で“可視化される支出”にも価値を感じやすく、投げ銭や課金アイテムを自己表現や地位獲得の手段として肯定的に捉えます。
そのためマテリアリズム傾向が高い人達は、自分にとってそれが必要か? その消費に意味があるか? という点にはあまり興味がなく、お金の使い方を外部に可視化できるという点が重要になってきます。
一方、マテリアリズム傾向が低い人は、他人からの評価よりも「自分にとって必要かどうか」を優先し、結果が不確実な消費を避ける傾向が強くなります。こうした人達は同じ金額を使うなら、確実な価値や将来の安定をもたらす支出を選びやすく、派手さや一時的な注目に魅力を感じにくいのです。
そのため、マテリアリズム傾向が低い人はガチャ課金やスパチャなどの消費行動に対し、意味のないお金の使い方だと批判しますが、消費することの意味づけがそもそも両者で異なっているので、議論がかみ合わないのです。
つまり、払う人と払わない人の違いは、単に「浪費家か節約家か」ではなく、承認欲求・刺激への感受性・お金の意味づけといった心理要素の組み合わせによって形づくられているのです。













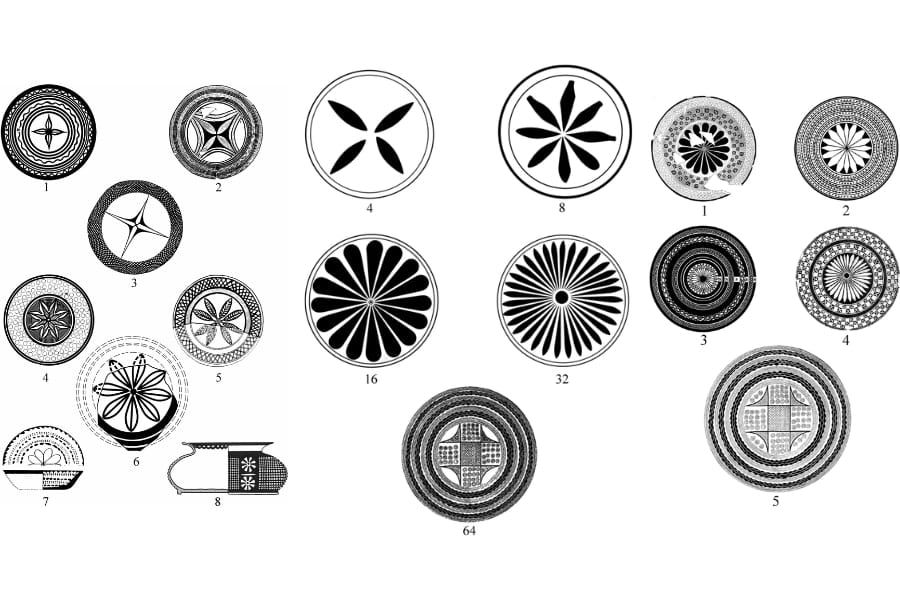


















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























