【まとめ】社会的順位から見える人の心
この研究によって、動物が集団の中で「勝ち組」と「負け組」のような順位に分かれる仕組みが、脳の働きという視点から詳しく明らかになりました。
これまでも、動物の群れでは力関係に基づく順位が自然にできることはよく知られていましたが、「なぜ順位ができるのか?」という理由を、脳の中の回路や分子の働きまで掘り下げて調べた例は多くありませんでした。
今回の研究チームは、マウスの脳を調べて、この疑問に対して明確な答えを提示しました。
まず、この研究で最も注目すべき発見の一つが、「TRPM3」という分子が社会的な行動や順位に影響を与えることが明らかになった点です。
TRPM3とは、細胞の表面に存在し、カルシウムというイオン(電気を帯びた小さな粒子)が細胞内に入る際の通り道として働く分子です。
脳の神経細胞が活動するためにはカルシウムが必要で、この通り道がよく開いているほど細胞が活発に働きます。
つまりTRPM3は、いわば脳の細胞を元気にするための「スイッチ」のような役割を持つのです。
今回の研究では、このTRPM3の働きが順位と深く関わっていることを、実験によって初めて明らかにしました。
強いマウス(勝ち組)の脳内にある神経細胞では、このTRPM3がたくさん作られており、その結果、脳の中でも特に「視床」という場所にある神経細胞が元気に活動していました。
視床は脳の中央に位置しており、さまざまな情報を集めて、それを脳の他の場所に伝える役割を持つ「連絡センター」のような存在です。
この視床が活発だと、脳内で「怖さ」や「不安」を感じる役割を持つ「前帯状皮質」という場所の活動が抑えられ、逆に積極性や意欲を生み出す「前頭前野」の活動が高まります。
つまりTRPM3がよく働いているマウスでは、「怖気づかず、積極的に戦える」ような脳の状態が自然に作られるわけです。
ただ、研究チームは同時に注意深く、このTRPM3だけが順位を決める全てではないことも指摘しています。
順位というのは複雑な行動なので、TRPM3以外にも同様の働きを持つ別の分子が存在する可能性があります。
つまり順位の決定は、「単独のスイッチ」ではなく、「いくつもの分子が協力して働く複雑な仕組み」であると考えられています。
また、この研究では脳内の回路構造についても詳しく調べ、順位決定に関係する複数の脳領域が協力し合う仕組みを明らかにしました。
順位決定に関わる脳の領域としては、「視床」だけではなく、「前帯状皮質」や「前頭前野」、さらには「眼窩前頭皮質(攻撃や積極性を伝える部分)」や「基底前脳(不安や抑制的な感情を伝える部分)」も重要です。
これらの複数の領域が、ちょうど電車が複数の駅を経由して目的地に情報を届けるように、協力して一つの行動を作り出しています。
このように脳が連携して働くことで、動物は自分の置かれた社会的状況に応じて、柔軟な行動を取ることができるのです。
さらに今回の研究結果は、これまでの理解とは異なる新しい事実も提示しました。
これまでの一般的な理解では、順位というのは「強い個体が攻撃的に振る舞うから勝ち、弱い個体は負ける」と考えられることが多かったのです。
しかし実験から分かったのは、実は「負ける側が怖気づき、戦意を失う」ことの方が、順位を決定する上でより重要だということです。
つまり順位は、「攻撃する側の強さ」よりも、「攻撃される側がどれだけ怖がり、防御的になるか」という「心理的な側面」の方が決定的な役割を果たしていたのです。
そしてもう一つ、脳の仕組みに関する新たな発見として、「前帯状皮質(不安を感じる脳領域)」と「前頭前野(やる気を起こす脳領域)」がシーソーのように逆の方向に働くことも示されました。
勝つときには前帯状皮質が静かになり、前頭前野が活発になる。
逆に負けるときには前帯状皮質が活発になり、前頭前野が静まる。
このように脳の中では、状況に応じて二つの領域が絶妙なバランスを取りながら行動を調整していたのです。
とはいえ、この研究はあくまでもマウスを対象にした基礎研究ですから、すぐに人間の行動や精神的な問題に応用できるわけではありません。
しかし脳の基本的な仕組みというものは、動物も人間も共通する部分が多いため、今回明らかになった仕組みが人間にも存在する可能性はあります。
実際に人間の社会でも、「地位」や「自信の有無」が心の健康や行動に影響を与えることはよく知られています。
もしかすると私たち人間の脳にも、「怖気づきを抑えて積極性を高める」ための回路が同じように存在し、そのバランスが乱れることで社会的不安やうつ病、自閉症スペクトラム障害などの問題が起きている可能性があります。
このように考えると、今回の研究は人間の精神疾患の治療法を開発するための、重要なヒントとなるかもしれません。

































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


















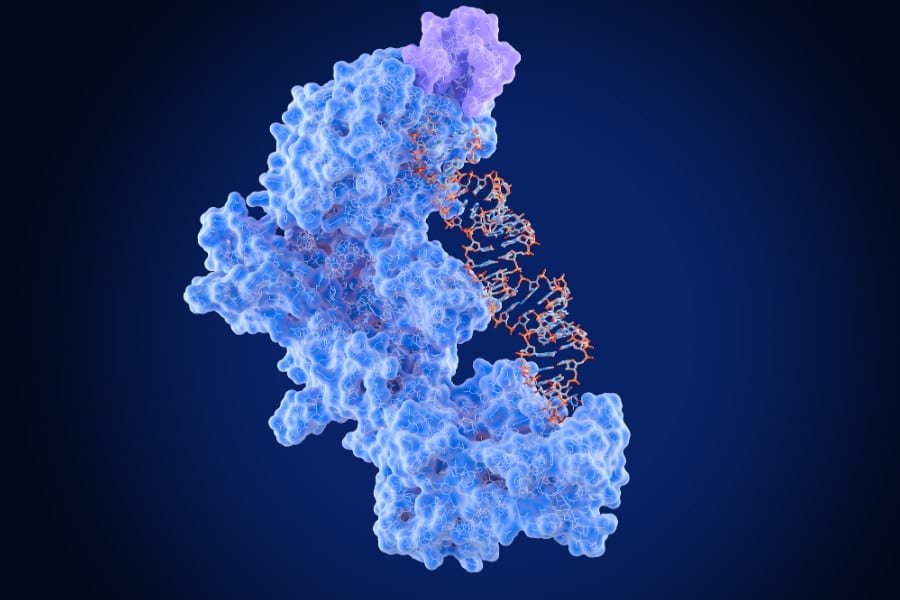









エンマコオロギを昔飼ってたとき不思議だったのが、喧嘩の強い個体と別のゲージの喧嘩の強い個体同士で喧嘩させて、負けたほうを元のゲージに戻すと負け癖がついて最弱の個体にもあっさり負けたりする。その最弱の個体に勝ち癖がついてトップになることもある
結局強いエンマコオロギの遺伝子を残そうとしてうまくいかなかったけど、昆虫の場合も脳の状態やイオンチャンネルの状態に似たような体内の分子の数が大きく影響してるのかなって色々考えたりできて面白かった
それは面白い実験ですね
人間でもそれまで調子良かったのに一度転んでダメになるやつも居ますもんね
やっぱり人生は才能運ゲーなんだな
自己啓発本に引用されるタイプの実験を引用される前に見てれ神
人間の世界は金持ち喧嘩せずだよ
この理論が適応されるのは、環境が選べないレベルで働かざるえない場合
人間だと発達障害の子は基底前脳にうまく信号が伝えられていなさそうだが、勝ち組は少なそう。人間の場合は良心によって自己中心な個体は孤立し、皆の益を求める個体がうまくいく。
動物でも眼窩前頭皮質の信号が強い個体は、自然界では順位以前に事故死してそう。
とはいえ、勝てない勝負は生存に直結するのだから、現場でのリアルタイムな彼我戦力の比較が分泌量に関連してるでしょ、どう考えても。
先天的というより、勝てる体格の個体は戦闘判断で退く結果が少なく、結果、分泌量が増えるというだけなんじゃないの。
生存に直結する判断回路が個々固定のプログラムと考えるほうが不自然。
ほんとに興味深い記事です。
脳内にはヘロイン=モルヒネすら越える強度のホルモンが分泌されるらしい。先程のホルモンは死の苦痛を緩和させる麻酔のようなもの.さて,人間の脳内から分泌されるホルモンの内. テストステロン:攻撃性を発揮.
アドレナリン:興奮状態にさせる.
※実際の戦闘時, 余計な事を考えいる暇はない.
一旦思考を最小限度にまで低下させ生命体の本能の持つ闘争本能を最大限に発揮させねばならない.
※→この為, アドレナリンの様な興奮状態にさせて
生命の野性的生存闘争本能を最大限に発揮させ得る、テストステロンが分泌されるらしい。
【別記】因みに、
その際、脳波も異なる事が判明している。