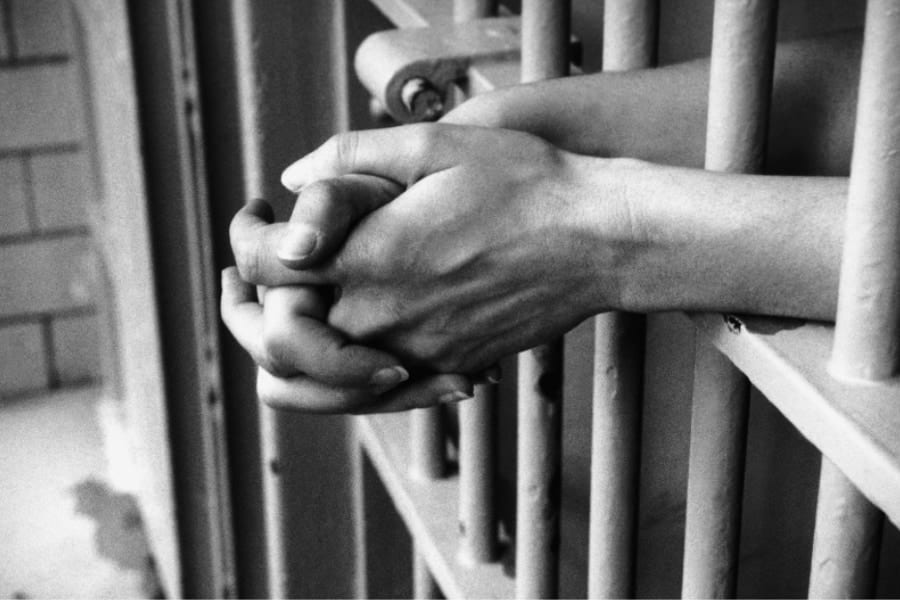南極の極寒が生んだ「透明な血」の秘密

地球の最果て、南極の海は水温が氷点下1.8℃から2℃ほどと、ほとんどの生物にとって過酷な環境です。
そんな環境に適応してきたのが、コオリウオ科(学名:Channichthyidae)と呼ばれる魚たちです。
体長は25〜50センチほどで、黒いものもいれば青白い半透明のものも存在し、その姿はまるで氷の彫刻のように神秘的です。
コオリウオの最大の特徴は、血液が無色透明であることです。
通常、私たち人間を含む脊椎動物の血液は「赤血球」の中にあるヘモグロビンという赤いタンパク質によって酸素を運んでいます。
しかし、コオリウオには成体になるとこのヘモグロビンが存在しません。
赤血球そのものもほとんどなく、わずかに残骸のような細胞が漂うだけです。
そのため、彼らは血液に直接酸素を溶かし込むことで体内に運んでいます。
ただしその効率は通常の硬骨魚の血液の10分の1程度しかありません。
では、なぜ生存できるのでしょうか。
鍵となるのは南極の環境です。
極寒の海は水温が低いため、酸素の溶解度が非常に高く、血液が赤くなくても十分な酸素を取り込めるのです。
このユニークな生理的特徴を補うため、コオリウオは他の工夫もしています。
血液の量は一般的な魚の約4倍に増え、血液の粘度が低い(=サラサラ)ので流れやすくなっています。
さらに心臓は非常に大きく、拍出量は他の魚の約5倍に達します。
心臓の心室はスポンジ状になっており、そこを流れる血液から直接酸素を取り込める仕組みまで備えているのです。
これらの進化によって、ヘモグロビンを失ったという不利な条件を見事に補い、氷の海でも力強く生き抜いています。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)