巨大な繁殖地の発見と進化の謎
コオリウオがいつどのようにして「白い血」を獲得したのかは興味深い謎です。
研究によると、数千万年前に南極大陸が急激に冷却され、海が氷点下の酸素豊富な環境になった際に、偶然ヘモグロビンを失う突然変異が起こったと考えられています。
通常であれば致命的な欠陥となるはずの変異ですが、南極の特殊な環境では逆に生存が可能となり、その結果「透明な血を持つ魚」という進化的に異例の存在が生まれたのです。
このユニークな適応は単なる生き残りにとどまらず、コオリウオが南極海に広がる生態系の中で繁栄することを可能にしました。
2022年、ドイツのアルフレッド・ウェゲナー研究所の調査により、ウェッデル海のフィルヒナー棚氷の下で驚くべき発見が報告されました。
そこには、直径0.75メートルにもなる巣が無数に広がり、なんとおよそ6,000万匹のカラスコオリウオが繁殖している、世界最大規模の魚の繁殖地が存在していたのです。
調査を行ったオトゥン・プルサー博士によれば、「カメラを曳航しても巣の終わりが見えないほどの広がりだった」とのことです。
この発見は、氷の下にこれほど巨大な繁殖コロニーが形成されうるという事実を初めて示したものであり、南極の海洋環境がこの魚たちにとってかけがえのない生息地であることを強く示しています。
欧州連合や南極の海洋生物資源保存委員会(CCAMLR)は、2016年からこの地域を海洋保護区に指定する提案を検討しており、国際的な保護の必要性が高まっています。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)





















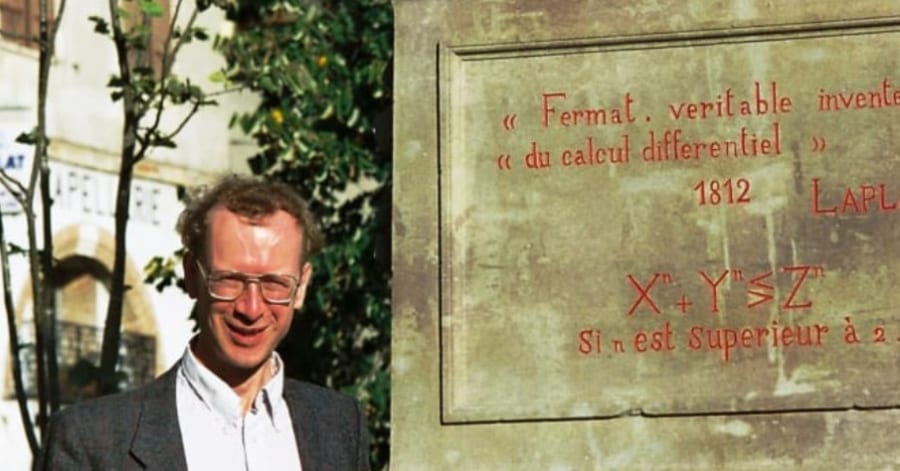






突然変異だったとしてもヘモグロビンを失ったのが生き残って種になったのはなんで?あった方が有利なんじゃないの?
ヘモグロビンが無い事は確かに生存競争の上で不利です。
ただ、「競争相手の少ない南極海だったから、そのような不利をもたらす突然変異が起きた血統でもなんとか生き残る事が出来た」と考えられているようです。
結構心臓に負担かかりそうな感じですね。
逆じゃなかったりしないのかな?
この魚だけ進化に取り残されて血液が透明なままとか
コオリウオは脊椎動物亜門条鰭綱スズキ目コオリウオ科に属する魚ですが、同じ条鰭綱に属する魚でも、コオリウオ科以外の魚はヘモグロビンを持っていますし、サメやエイといった条鰭綱とは進化の系統が異なる脊椎動物亜門軟骨魚綱の魚もヘモグロビンを持っていますから、脊椎動物亜門の動物が進化の過程でヘモグロビンを持つようになったのは、条鰭綱と軟骨魚綱が分化するよりも前の事だと考えられます。
従って、コオリウオの祖先も最初はヘモグロビンを持っていたと考えられますから、
>この魚だけ進化に取り残されて血液が透明なまま
なのではなく、元々はヘモグロビンを持っていたものが、進化の過程でヘモグロビンを失ったと考えられます。
科レベルで特徴を共有するということは、祖先種がヘモグロビンを失ってから、適応・放散が進んだという点で、生息域で競合する他種や捕食/被食の関係の中で、損失を上回る利益があるということですね。
(成魚には負担でも、成熟した卵・稚魚や幼魚の外観がほぼ透明になって視覚探査の捕食者からみつかりにくいとかあるかもしれません)
なぜなに物語が好きです。
ヘモグロビンがなく血液の酸素運搬量が低ければ、補うために血流を増やす必要があります。となると、血液ポンプの運動を強くする必要があり、逆説的に酸素消費量が増加します。また、血流量を増やせば血圧を上げねばならないので、抵抗血管を厚めに作らねばならず、その分酸素交換効率が落ちそうです。他方で有核の赤血球を毎日せっせと作る苦労や、鉄イオンの補給の手間を思えば損得を相殺できそうです。
筋肉での酸素消費についても底生性で待ち伏せ戦略を取るなら、白筋を無酸素的に稼働させればよく、ミオグロビンは不要で、後からゆっくりと酸素の補充ができそうです。