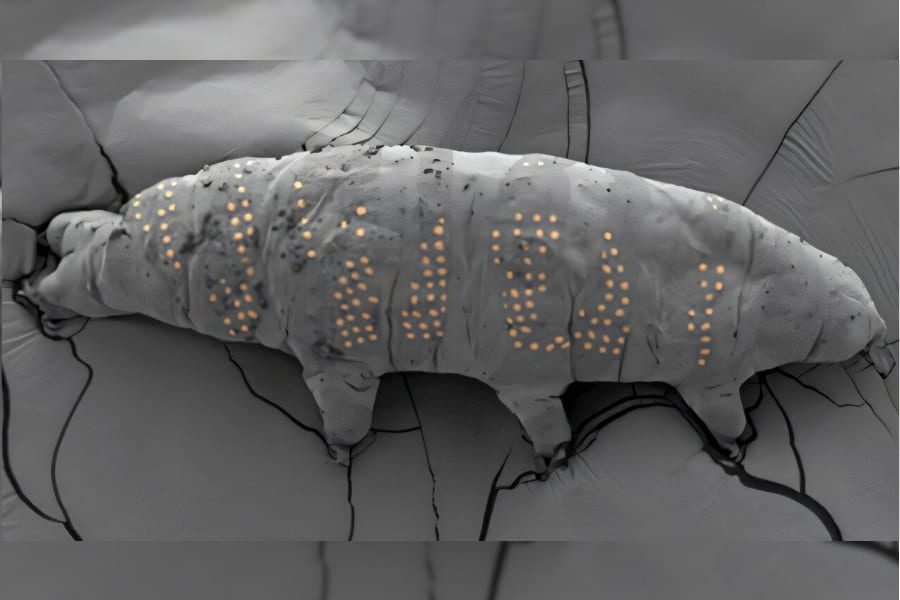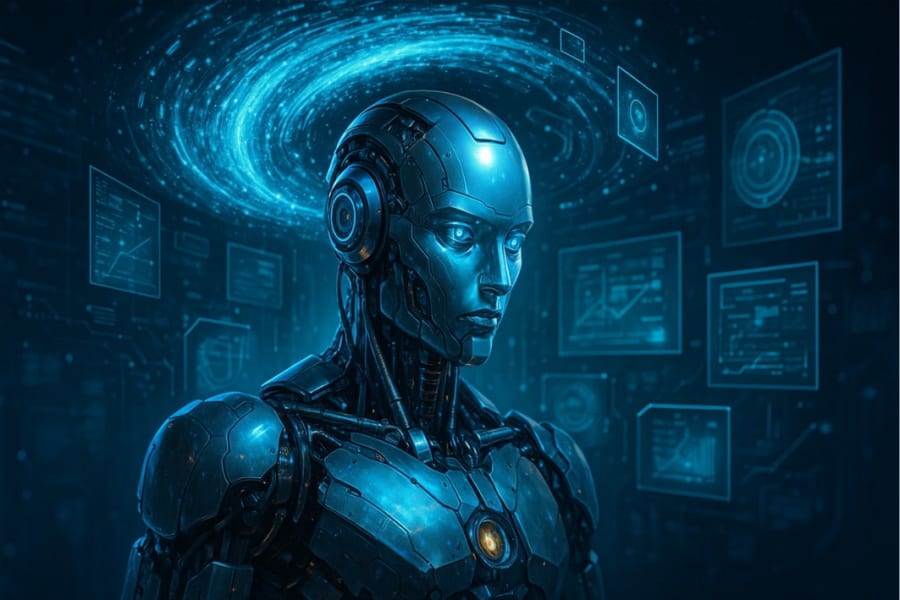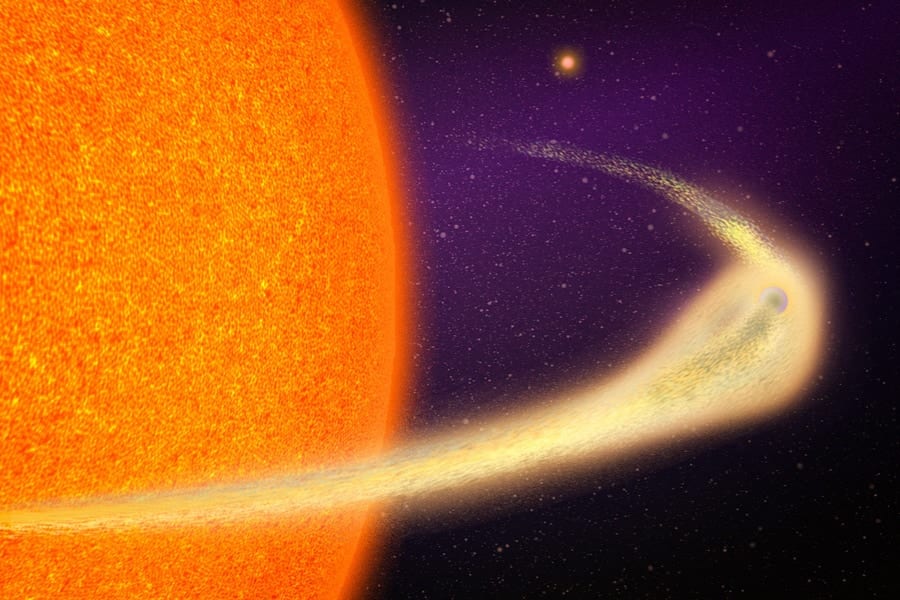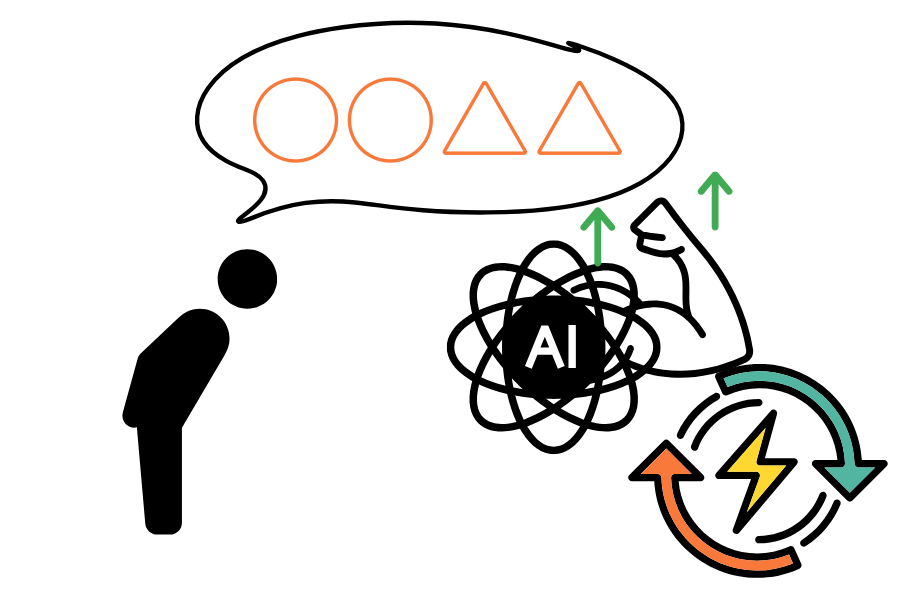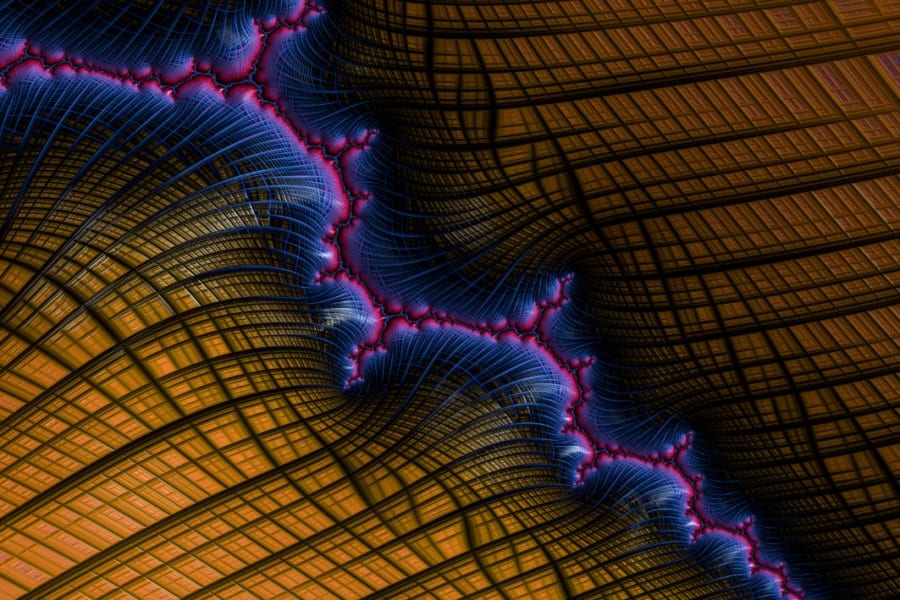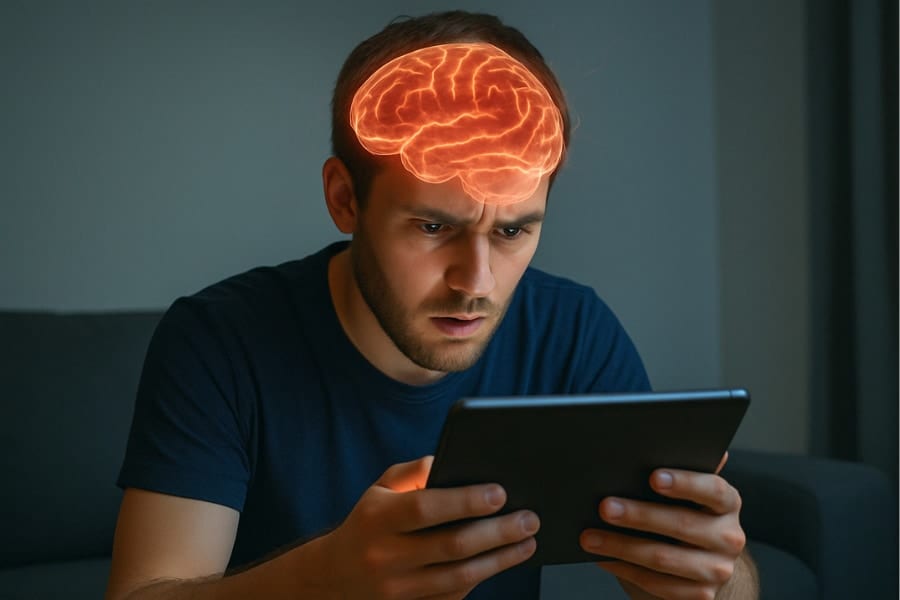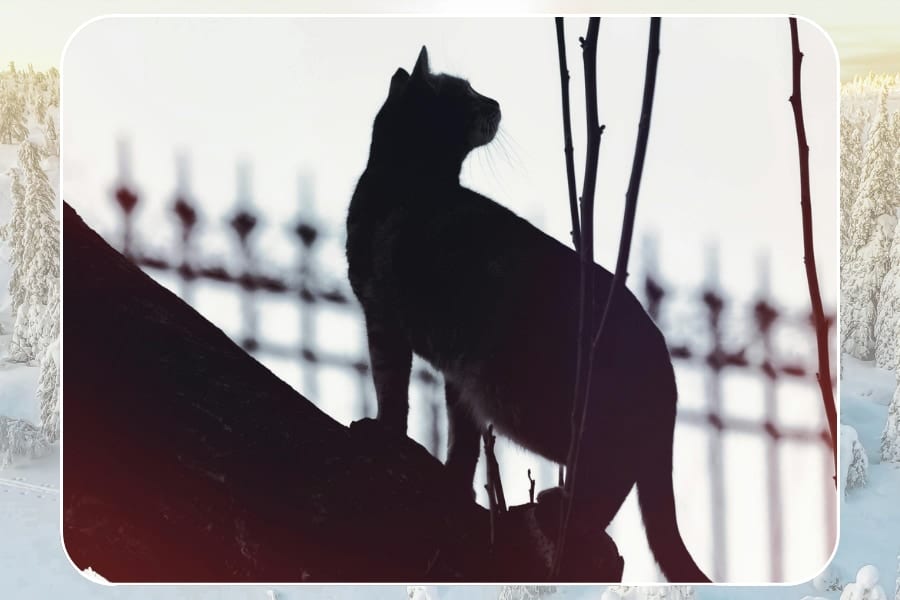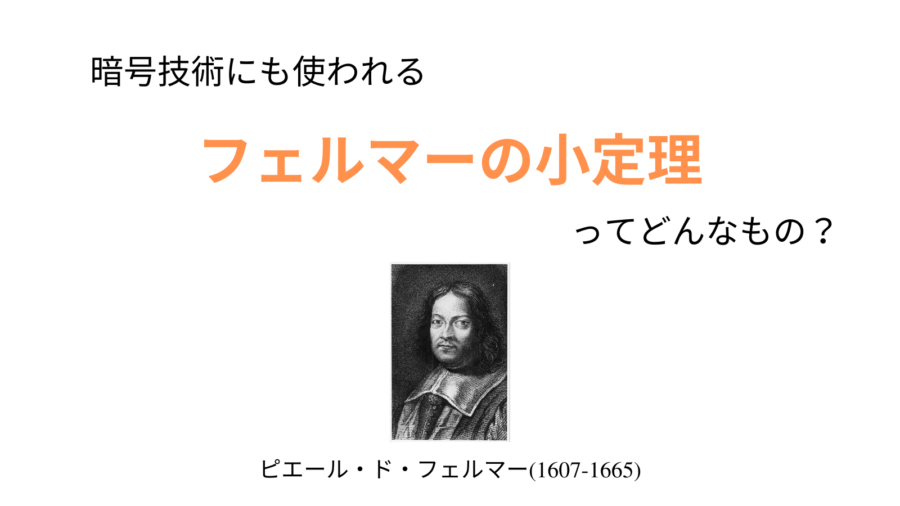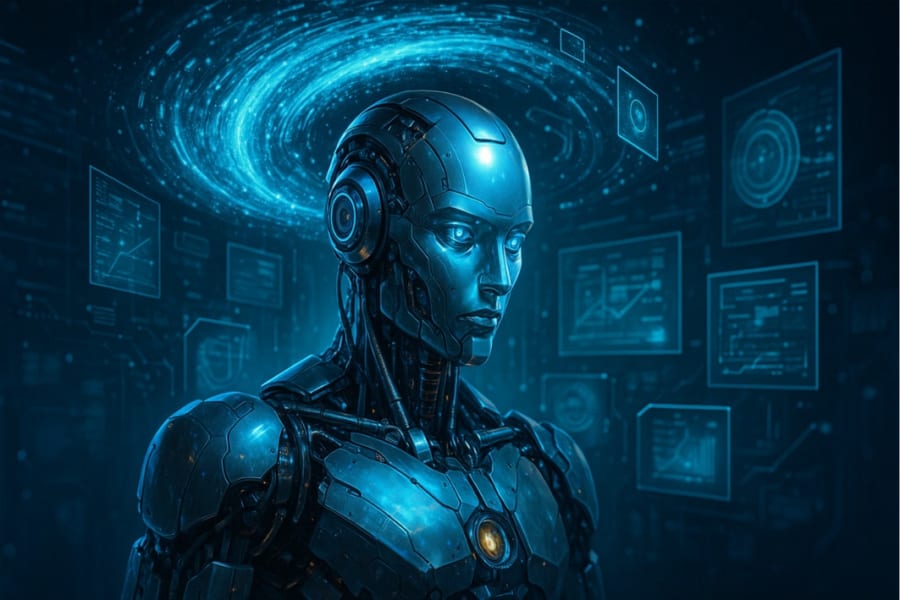素朴な疑問「投票率が高い国は政治がうまくいっているのか?」
アメリカは世界でも有数の高投票率国家のひとつです。特に大統領選では、2020年に66.8%という過去最高レベルの投票率を記録しました。これは同年の日本の衆議院選挙の投票率(約55%)よりはるかに高い数字です。
では、その結果としてアメリカの政治はより健全になったのでしょうか?
答えは、むしろ逆に見えるかもしれません。ドナルド・トランプ政権の誕生や再当選の動き、保守とリベラルの深刻な対立、格差の拡大、分断する世論。アメリカ政治はここ10年でかつてないほどの混乱と緊張を抱えるようになりました。
特にアメリカは社会保障などが市場任せになっていて、格差問題もかなり深刻な状況です。
こうしたアメリカの状況を見ると、投票率の高さというのは政治の質とはあまり関連しないように感じます。
しかし、実のところアメリカは、様々な理由から政治に民意が反映されにくい国なのです。
そのため投票率が高くてもあまり政治に影響を与えません。その最大の理由は、選挙制度と政治資金をめぐる“仕組み”にあります。
たとえば、大統領選挙で採用されている「選挙人制度」は、日本人にはなじみのない仕組みです。これは、各州に割り当てられた「選挙人」が代わりに大統領を選ぶというもので、しかも多くの州では得票数に関係なく、勝者がその州の全選挙人を獲得する“総取り方式です。
イメージとしては、47都道府県それぞれが選挙団体を持ち、東京都で51%の票を取った候補が100%の都民の意思として代表されるようなものです。これでは実際の総得票数と最終的な勝者が一致しない事態が起きて当然です。実際に2000年や2016年には、得票数で負けた候補が大統領になっています。
さらに問題を複雑にしているのが「ゲリマインダー(Gerrymander)」と呼ばれる制度です。これは政党に有利なように選挙区を恣意的に引き直すことができるもので、日本で例えるなら、自分の党を支持する市町村だけを寄せ集めて“勝てる選挙区”をつくるようなものです。
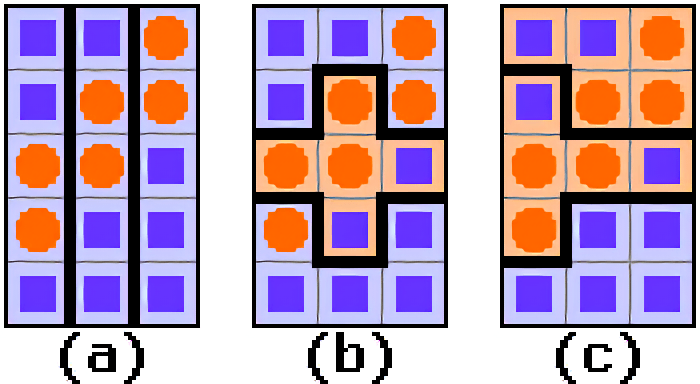
しかもこの区割りを、政権党が州単位で合法的にできてしまうという点がアメリカの構造的欠陥です。
また、アメリカでは企業や団体が政治家に巨額の資金を提供することが合法であり、制度的にも「言論の自由」として保護されています。選挙資金はPAC(政治行動委員会)やスーパーPACという仕組みを通じて動き、これによって政策の優先順位が「多くの有権者の声」ではなく、「大口献金者の意向」に沿って決まるという事態も少なくありません。
ロビイストは、こうした仕組みを通じて、「選挙資金を提供する代わりに、法案を有利に扱ってほしい」という圧力をかけます。日本にも政治献金がありますが、PACは候補者個人を支援できたり、スーパーPACは上限金額がないなど日本の場合とは異なります。
加えて、メディア環境の分断も大きな問題です。アメリカのメディアは、民主党支持層向け(CNN、MSNBCなど)と共和党支持層向け(Fox Newsなど)に完全に色分けされており、視聴者はそれぞれ「自分たちにとって心地よい情報」だけを受け取る環境に置かれています。
SNSのアルゴリズムもそれに拍車をかけています。興味関心に基づいて情報が選ばれるため、ユーザーは自分と同じ意見の人の発言ばかりを見るようになり、異なる立場を知る機会が減ります。結果として、**社会全体の“共通の現実”が崩壊し、「対話」よりも「敵意」で動く政治」**が生まれやすくなるのです。
こうした事情を考えると、アメリカは「投票率が高くても民意が反映されにくい制度」を数多く抱えた、ある意味“例外的に歪んだ民主主義”だということがわかります。
つまり、投票率が高くても政治がうまくいかないのは、「投票率が無意味だから」ではなく、「制度や環境が民意の受け皿として機能していないから」なのです。
したがって、日本のようにまだ制度が比較的中立で、メディアや選挙区割りにそこまでの党派的偏りがない国では、投票率の上昇が政治を良くする可能性があるのです。