上方で産声を上げた外食産業

日本に外食産業が根付きだしたのは、江戸時代です。
17世紀後半、京の街角には「二軒茶屋」と呼ばれる茶屋がひっそりと灯をともしていていました。
この茶屋は、八坂神社へ参詣する人々がふと一息つくための場であったのです。東の中村屋と西の藤屋、この二つが茶屋として名を馳せていたといいます。
豆腐を串に刺して焼き、味噌汁に浸して食べる「祇園豆腐」が名物で、その淡白で脆い味わいは他にはない風情であったと、黒川道祐の『雍州府志(ようしゅうふし)』には書かれているのです。
この「二軒茶屋」は単なる休憩所ではなく、軽食を供するという新たな形の茶屋であり、当時としては非常に斬新でした。
人々は豆腐を味わいながら、京の四季を謳った地唄を口ずさみ、日常の喧騒から一時解放されたことでしょう。
その頃、京都だけでなく、東山の円山付近の寺院でも料理屋が現れ始めていました。
特に、時宗の寺院が席貸しをしながら料理を提供するようになったことは、寺院の静謐な雰囲気の中での食事という一風変わった趣向であったのです。
そして、双林寺や長楽寺といった寺院が、宴会用の宿としても利用されるようになり、寺院そのものが料理を提供する役割を担うようになっていきました。
こうした背景には、庶民の外食に対する関心の高まりがあったことでしょう。
このような動きは何も京だけで起こったわけではなく、江戸でも似たような動きがありました。ただし17世紀の江戸では、まだ本格的な料理屋というものは存在していなかったのです。
江戸時代初期には、幕府が飢餓対策として五穀の無駄遣いを禁止し、うどんやそば、饅頭といったものの商売が一時的に制限されてさえいました。
食事といえば簡素なものが主流で、街中では煮売屋が煮物や簡単な料理を売り歩く形が一般的だったのです。
そのため京で見られるような「料理屋」と呼べるものはほとんでありませんでした。
しかし、江戸時代も中期に入ると、江戸においても食文化は次第に多様化していきました。
特に信州産のそばが江戸で評判を呼び、そば切りが庶民の間で人気を博したのです。
『本朝食鑑』によれば、信州や関東近郊では良質のそばが生産され、江戸の町では信州産のそばが広く使われるようになったといいます。
そば屋は18世紀に入ってようやく登場し、そばとともにうどんが江戸の食文化の一部として根付いていきました。
このように、江戸時代中期を境に、日本の食文化は少しずつ外食産業としての形を成し始めていきました。
都市の商人層を中心に、食事は日常の楽しみとして捉えられ、その需要に応える形で茶屋や料理屋が次第に発展していったのです。









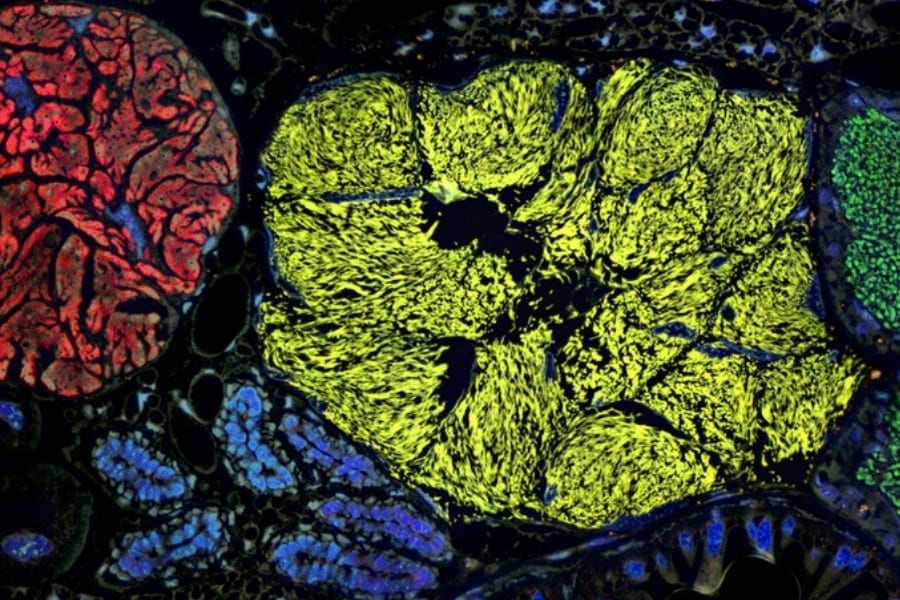











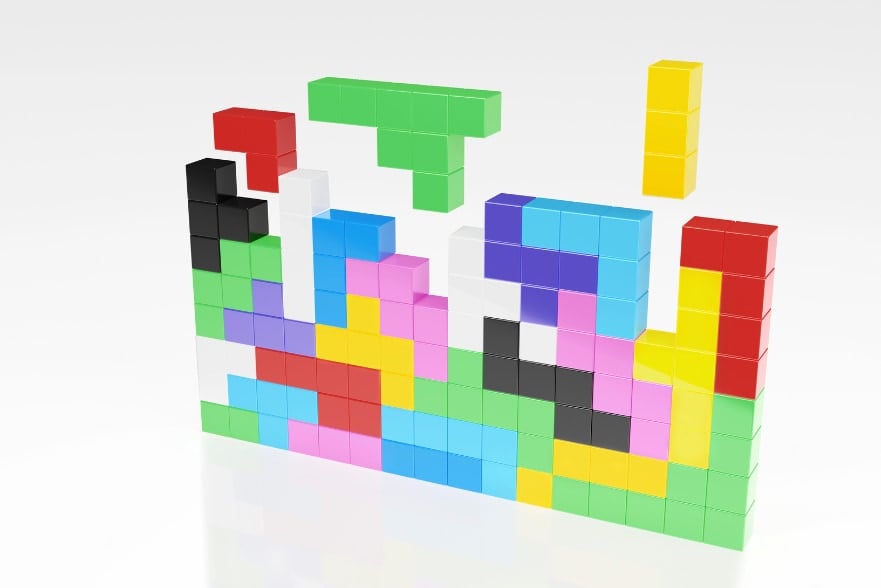

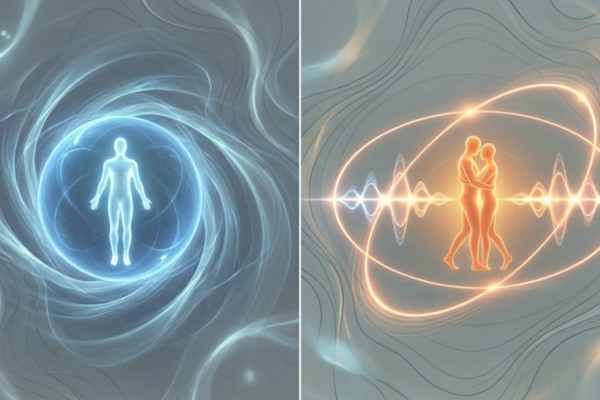









![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)



























