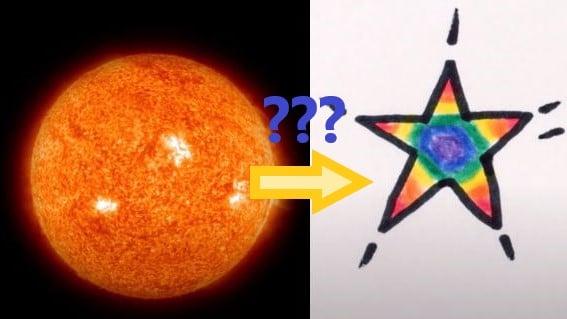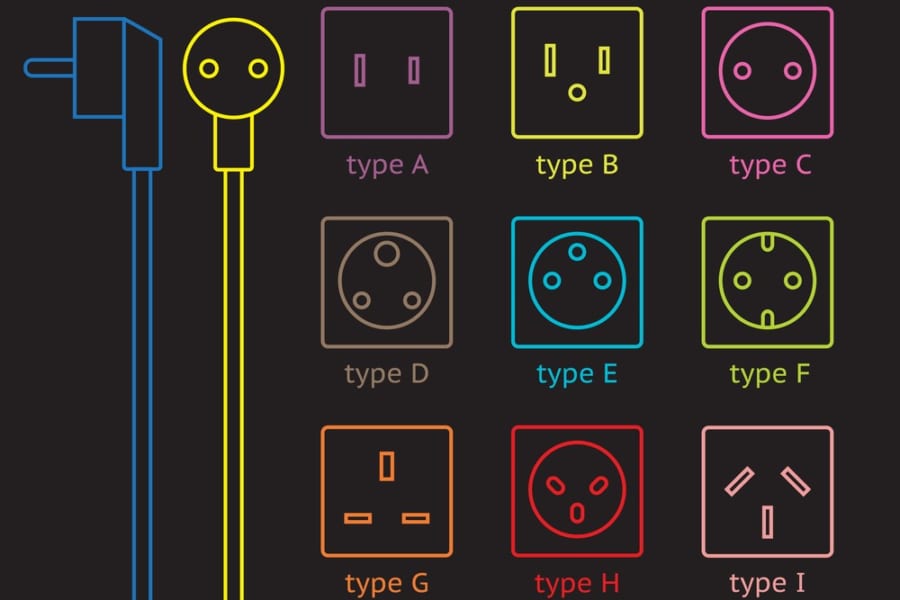当初は薬としてしか使われてこなかった砂糖

砂糖が日本にやってきたのは奈良時代です。
754年、名高い僧・鑑真がはるばる中国からやってきました。
その手には、神秘的な黒糖が握られていたといいます。
当時、砂糖は薬としてしか使われず、口に入ることは滅多にない高貴なものだったのです。
そのため古代・中世の日本人にとって、甘味といえば飴や甘酒、柿、樹液でした。
しかし、時は流れ、16世紀に大航海時代が到来し、日本にもヨーロッパから商人や宣教師がやってきます。
彼らはキリスト教だけではなく南蛮菓子も日本に伝え、カステラや金平糖といったお菓子が広まりました。
それにより砂糖はついにその甘味料としての真価を発揮することとなるのです。
琉球ではサトウキビの栽培が始まり、薩摩藩がこの黒い宝石を専売とし、財政の柱に据えるようになります。
そして、ついに1713年、薩摩の黒糖は大坂市場に堂々と姿を現し、日本中の市場を席巻していくのでした。砂糖の歴史はこうして本格的に動き出したのです。




























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)