時代が進むにつれて長期留学は減っていった

遣唐使は、最初からすべての唐の文化をそっくりそのまま移入したわけではありませんでした。
というのも遣唐使は先述したように10年に1度のペースで行われており、日本に伝わった唐文化には、時代や地域の限定があったのです。
実際、日本は唐の文化をすべて無条件に受け入れたわけではありません。
たとえば、道教はほとんど受け入れられず、書物に関しても、選択的に輸入されたものでした。
もちろん留学生が習得する学問も当人たちの選択した学者のもとで習得したこともあり、日本に伝わってきたのはごく一部でした。
また遣唐使の時代が進むにつれて、留学生たちも、唐に長く滞在する必要性を感じなくなっていきました。
たとえば奈良時代初期の716年に唐に渡った仲麻呂と真備の場合、真備は18年間唐に滞在し、仲麻呂に至ってはついに日本の土を踏むことなく唐で生涯を終えることとなりました。
それに対して平安時代初期の804年に唐に渡った空海と逸勢の場合は長期間唐に滞在することを予定していたものの、2人とも806年に帰国しています。
特に空海に至っては「唐での滞在はもはや無駄だ」とまで述べており、唐にて修行をすることよりも日本で成果を披露することを急いだのです。
また彼らとともに唐に渡った最澄は最初から短期滞在を予定しており、8カ月という短い期間で慌ただしく天台宗を学びました。

このように、唐文化の移入は徐々に「必要なものだけを得る」という選択的な姿勢に変わり、長期の留学は減少していきました。
その結果、日本は唐文化を包括的に吸収するのではなく、必要に応じて取り入れ、国内での伝習システムを構築していくことに成功したのです。
こうして、唐文化の移入は次第に完了し、日本は自らの文化を形成する道を歩み始めたのです。
遣唐使という一大事業が示したのは、単なる文化の受け入れではなく、日本がどのように外来文化と向き合い、選択し、独自のものへと昇華させていったかという物語であったことが伺えます。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















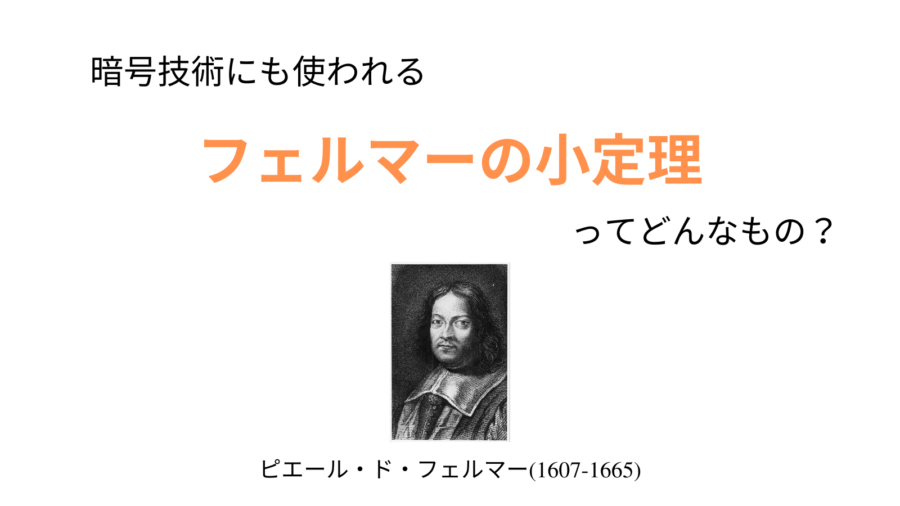
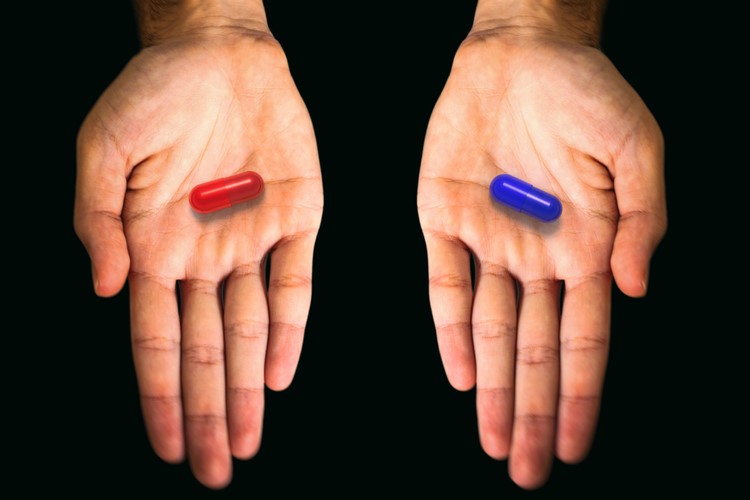






日本人の西洋人によく似た傲慢さはこの頃からあったわけですね。
必要ないと思ってもモニタリングは続けておくべきなのですよ、すべてを知ることはできないのですから。
油断したときから敗北は始まるのです。
何言ってんだか その傲慢さは日本人だけでないでしょ 見方によってはまだマシととらえることもできる
留学期間が長くなればお金も掛かるわけですし空海さんは国費じゃなく私費ですしたね。
日本には日本なりの文化があるわけで完全に中華化する必要も無いから当然ですね
留学じゃなく買い物が目的だったって意見を聞いたことある。
書籍その他を大量購入して持ち帰り、日本で研究をつづけたって。