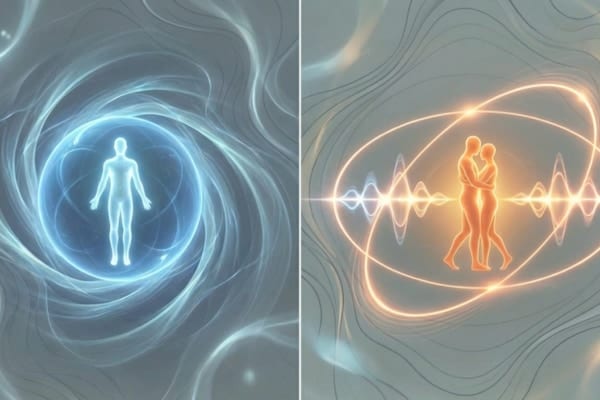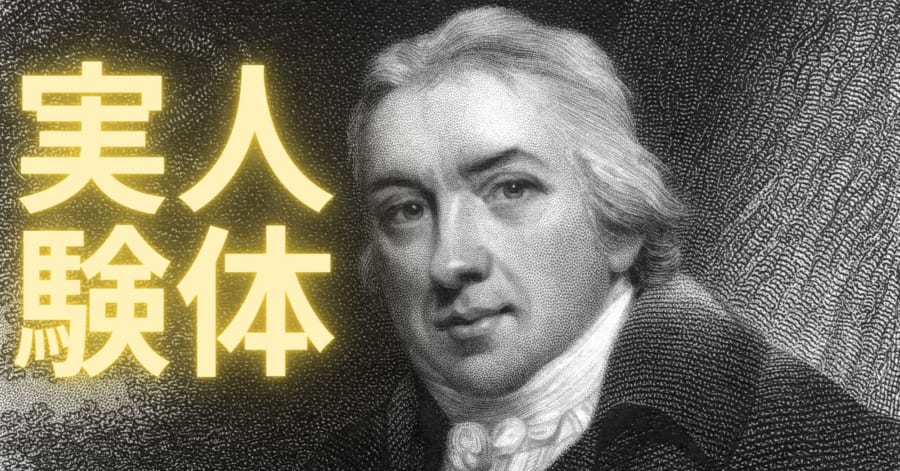「ファミコンから64まで──ノスタルジーはどこで生まれる?

昔、あなたが一番ワクワクしたゲーム機は何でしょうか。
家のテレビとケーブルをつないで家族や友達と一緒に遊んだファミコンかもしれませんし、学校の休み時間にポケットからこっそり取り出して遊んだゲームボーイかもしれません。
あるいはスーパーファミコンや初代プレイステーションの「画面がすごくきれいに見えた!」という衝撃を、いまも鮮明に覚えている人もいるでしょう。
こうした思い出は、まるで匂いのように、ふとしたきっかけで一気に蘇ってきます。
ボタンの配置やBGMのメロディ、友達と競い合ったときの興奮――ゲームはときに、人の記憶を一瞬にして「当時の空気感」へと連れ戻す不思議な力を持っています。
実は心理学やメディア研究の分野でも、音楽や映画と同じように「ビデオゲームによるノスタルジー」が人の気分を高めたり、人間関係をやわらかくしてくれるかもしれないという説がたびたび提案されてきました。
いわゆる“懐かしのドット絵”や当時の操作感を再現するレトロゲームを遊ぶことが、まるで“思い出のタイムマシン”に乗って過去の自分に会いに行くような感覚をもたらすのではないか、と。
一方で、ゲームは他のメディアに比べても操作や画面の臨場感が強く、体験としてより深く体にしみついている場合があります。
「気づいたら子どもの頃のゲームを延々とやっていた」「古いはずなのに遊ぶたびにワクワクする」など、多くの人がなんとなく感じてきた“記憶とゲームの強い結びつき”は、もしかしたらデータで説明できるかもしれません。
歴史を振り返ると、1983年のいわゆる“ゲーム産業の危機”をきっかけに、一度盛り下がりかけたビデオゲーム市場がファミコンの大ヒットで再起し、以降、次々と登場する新ハードが「今度はこんなに画面が綺麗!」「オンライン対戦ができる!」と私たちを驚かせてきました。
しかし、どんなに新しくリアルな映像を実現しても、当時触れた“思い入れのあるゲーム機”へこそ強い愛着を感じる人は多いようです。
もともと10代や20代前半に聴いた音楽や観た映画を一生忘れられない、という現象は研究界隈では「リミニッセンスバンプ」と呼ばれています。
ですがゲームの場合はコントローラの持ちやすさやキャラクターを操作する手ごたえ、ときには家族や友達との会話までセットになって記憶が封じ込められているので、より強いノスタルジーを引き出すのではないかという見解があるのです。
さらに興味深いのは、「自分が現役で遊んでいた時代のゲーム機」だけを懐かしむとは限らないという点です。
たとえば、平成生まれのはずなのに初代ファミコンよりもさらに古いハードをわざわざ探し出して遊んでいる人もいたりします。
彼らが惹かれるのは、いわゆる“個人的な思い出”だけではなく、「当時に生まれていなくても感じる昔の文化や歴史への憧れ」としての“歴史的ノスタルジー”ではないかとも言われています。
しかし、こうした話題はこれまでもファンコミュニティで熱く語られてきたものの、実際のプレイデータを大量に集めて年齢やライフスタイルなどと関連づけて解析した事例はあまりありませんでした。
そこで今回、研究者たちは任天堂の最新ハードであるNintendo Switchで遊ばれた過去の名作ライブラリ――俗にいう“レトロコンソール”群――のプレイログを入手し、どんな世代のプレイヤーが、いつ頃のゲーム機を、どれくらいの頻度で楽しんでいるのかを詳細に調べることにしました。
プレイログには、どのゲームを何時間遊んだのか、携帯モードで遊んだのかテレビにつないで遊んだのかなど、けっこう細かいデータが含まれています。
さらにアンケート調査を組み合わせることで、レトロゲームへの“熱中度”と日常の幸福感や懐かしさとの関係を分析できるというわけです。
いったい、どの年代の人がどんなレトロゲーム機に夢中になり、それがどのように心に影響しているのでしょうか。













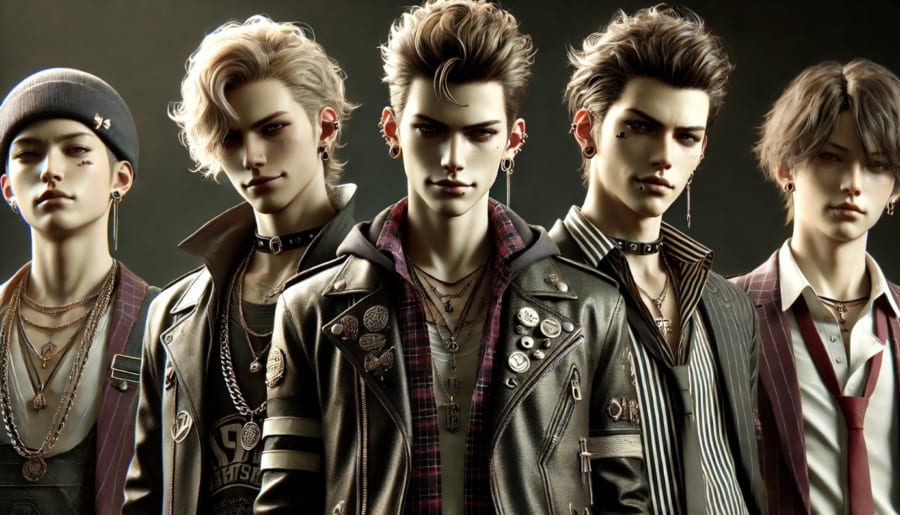


















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)