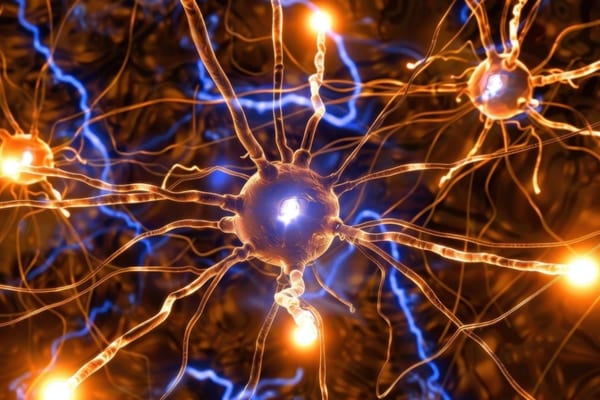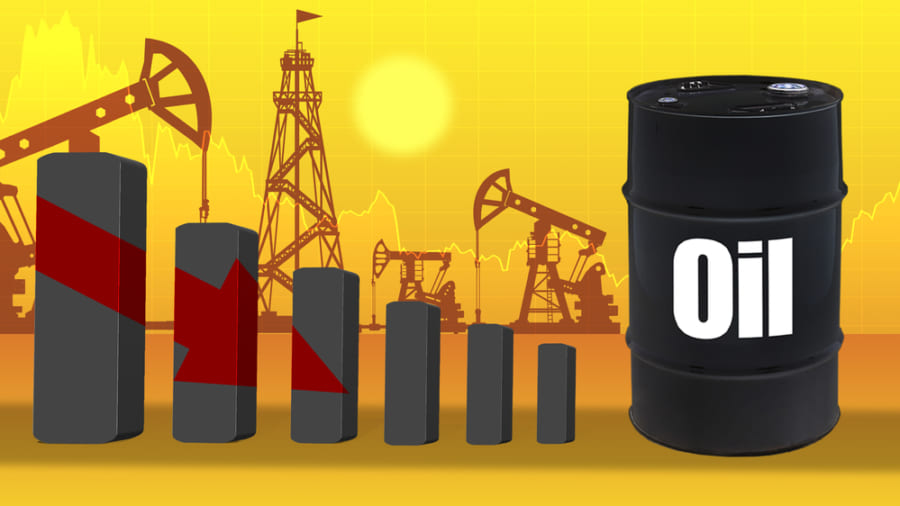まさかの関係:帯状疱疹ワクチンが認知症予防に

この研究でいちばんユニークなのは、「人によってワクチンを打つ・打たないの差が、ほとんど偶然で生まれている」という点を巧みに利用していることです。
たとえば、ウェールズでは1933年9月2日を境に、公費で帯状疱疹ワクチンを受けられる人と受けられない人がはっきりと分かれてしまう制度が存在します。
少し不思議に感じるかもしれませんが、これは同国の公的医療サービスが「今年◯歳になった人は○○ワクチンの対象」「来年からはさらに若い年齢の人が対象」といった段階的な接種プログラムを運用した結果、ちょうど1933年9月2日という日付で線引きをするかたちになったのです。
具体的には、2013年9月1日に始まった帯状疱疹ワクチンのプログラムが「80歳になったばかりの人は一定期間、公費で接種できるようにする。
すでに80歳を過ぎていた人は対象外」というルールを設けていました。
そのため「1933年9月2日以降に生まれた人」は2013年9月1日の時点でちょうど80歳またはまだ79歳だったので、ワクチンを打つ権利を得られたのです。
一方で「1933年9月1日以前に生まれた人」は、開始時点ですでに80歳を過ぎており、枠から外れてしまい、その後も一生涯“対象外”のままになりました。
こう聞くととても細かい区分ですが、実際には「たった1日違い」であっても政策の都合上、かたやワクチンを受けられる・かたや受けられない、という大きな違いが生まれてしまいます。
これが今回の研究で重要なポイントでした。
なぜなら「9月1日生まれ」と「9月2日生まれ」では、実質的にほぼ同い年で健康状態や生活習慣が似ているにもかかわらず、あるグループではワクチン接種率がほぼ0%、もう片方では約47%にまで跳ね上がるという極端な格差ができたからです。
研究者たちはこの“極端な格差”こそが自然実験に最適だと考え、大規模な電子カルテ情報を活用して「ワクチンを打った人ほど認知症のリスクが下がるのか」を調べました。
比較するのは「1933年9月2日より少しあとに生まれた人々」と「1933年9月2日より少し前に生まれた人々」。
年齢も住環境も似通った集団ですが、ワクチンの接種率だけが驚くほど異なる、そんな“ほぼ偶然”に近い差を利用して因果関係を検証したのです。
結果ははっきりしていて、接種資格を得たグループ(実際にワクチンを打った人たち)は、そうでない人たちと比べて新たに認知症と診断される確率が相対的に約20%低くなる傾向が見られました。
特に女性でより顕著な効果が示唆されています。
さらに、この分析を別の方法で試してみたり、イングランドの死亡証明書データを合わせてみたりしても、似たようなパターンが確認されました。
では、なぜこの研究がそんなに革新的なのか。
ポイントは、従来の「ワクチン接種群と非接種群を比べる」観察研究では拭いきれなかった「本当は、健康意識が高い人が接種するから違いが出ているのでは?」という疑問を、“生まれつきの誕生日”という偶然を利用することでほぼ解消していることにあります。
つまり、同じような条件下にある人たちの間で、誕生日の境界によって偶然に接種可否が変わるからこそ、「帯状疱疹ワクチンが認知症リスクを下げるかもしれない」という因果関係がより説得力をもって浮かび上がってきたのです。
結果として得られた「認知症リスク20%低減」という数字は、まさにこの画期的な自然実験の手法によって支えられていると言えるでしょう。
































![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)