おもちゃに見られる「空気とチューブ」を使って、高速移動する「脳を持たないロボット」が開発される

まず、私たちに馴染み深いおもちゃを思い出してみてください。
吹き戻しと呼ばれる紙の笛「吹き戻し(または巻き笛、ピーヒャラ笛)」や、イベントで見かける「チューブマン(またはエアダンサー)」です。
これらは、空気の流れによって柔らかい素材が動くという単純な物理現象を利用しています。
吹き戻しは、息を吹くと筒がスーッと伸びて、空気が抜けるとクルクルと巻き戻ります。
チューブマンは送風機の風で膨らみ、重力や不安定なバランスによって踊るような動きを見せます。
今回の研究チームは、この仕組みを利用して、構造物に「自律性」を持たせられるのではないかと考えました。
彼らは、エラストマーという柔らかくて弾力のある素材で作られた、くねくねしたチューブを用いました。

このチューブには、あらかじめ折れ曲がった部分「屈曲部」があり、そこに空気を送り込むと、その部分が移動します。
そして「屈曲部」の位置が変わると、空気の流れも変化し、それによって再び別の場所に「屈曲部」が現れるという振動が起こります。
チューブが一本だけだと、この振動はランダムです。
しかし、チューブを複数本組み合わせて「足」にすると、地面との摩擦や空気の流れによる物理的な影響だけで、それぞれの動作が自然と同期し始めます。
その結果、制御信号を一切使わずにロボットが歩き始めるのです。
コンピューターもセンサーも必要なく、空気と柔らかい素材と物理法則だけで動くのです。
こうして、「脳を持たない、足で考えるロボット」が誕生しました。
とくに注目すべきは、その柔軟性とスピードです。
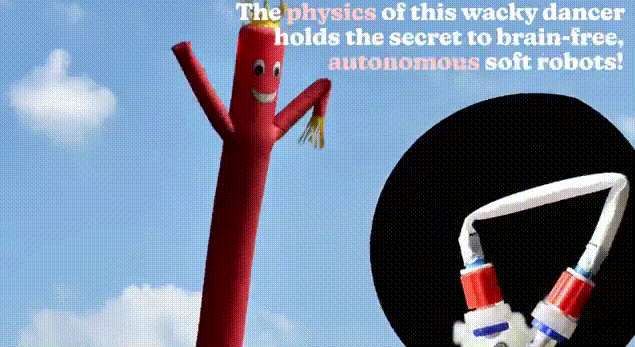
このロボットは、最大で1秒間に体長の30倍の距離を進むことができます。
動画で確認すると分かる通り、ソフトロボットとしては、恐ろしいほどの移動速度です。
フェラーリが1秒間に車体の20倍の距離を移動することを考えても、やはり常識外れの性能だと言えます。
そして続く部分では、このロボットが「足で考える」と言える理由をさらに考えていきます。





























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)

























