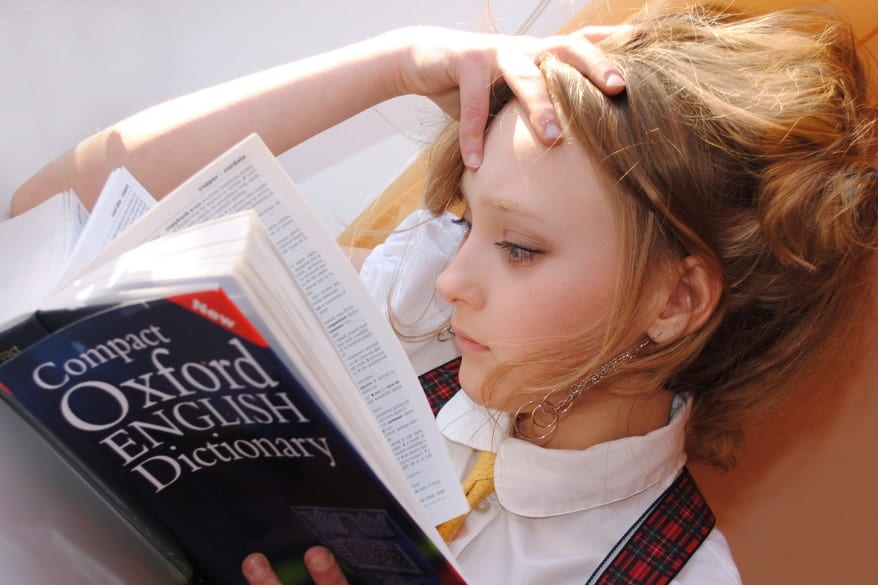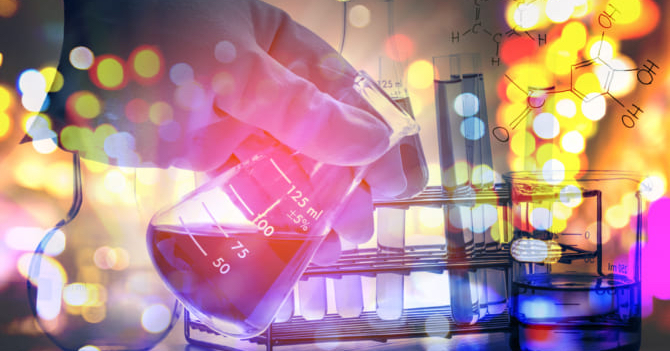働きすぎで脳に起きていた変化とは?
現代社会において「長時間労働」は、勤勉を示すものである反面、働き過ぎが心身に大きな負担をかけるとして問題視されています。
これまでも過労が心疾患やうつ病といった心や体への健康リスクを高めることは知られていました。
しかしその一方で、脳そのものの形にまで影響があるのかは、はっきりと分かっていませんでした。
「慢性的なストレスや回復の不足が脳の形態を変える可能性は以前から指摘されてきましたが、神経画像による実証的な証拠はまだ限られている」と研究者は話しています。

そこで今回、研究チームは韓国で行われた大規模な労働疫学調査「GROCS」の参加者から、MRI脳画像の取得に同意した医療従事者110人を対象に詳細な分析を行いました。
被験者は「週52時間以上働く過労群(32人)」と「通常労働時間群(78人)」に分けられ、脳の体積を詳細に比較。
その結果、過労群の脳では、「中前頭回」や「島皮質」「上前頭回」など、注意力や思考の柔軟性、感情制御に関わる領域で、灰白質(グレーマター)の体積が有意に増加していたことが分かりました。
特に中前頭回では、通常群と比べて約19%も体積が大きくなっており、これは非常に顕著な差といえます。
これらの変化は、週の労働時間が長いほど顕著になる傾向も見られました。
「灰白質の体積が増加している」と聞くと、脳にいい変化が起きているように聞こえるかもしれません。
しかし研究者らによると、決してそうではないようなのです。




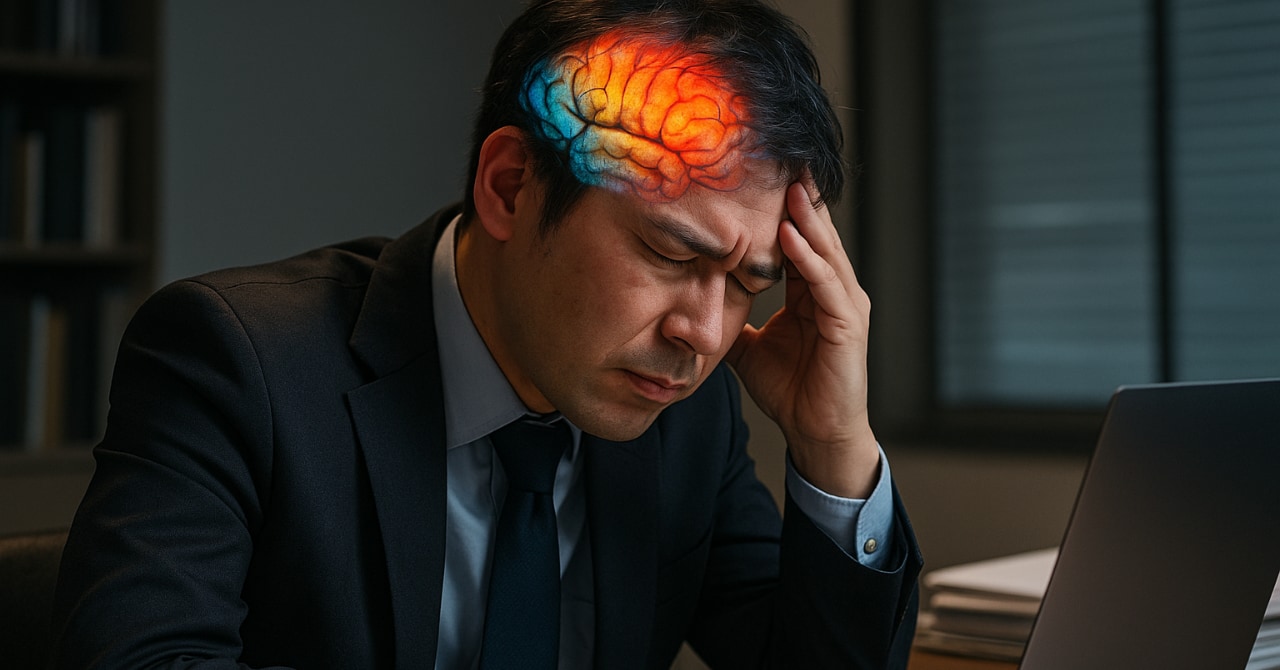




























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)