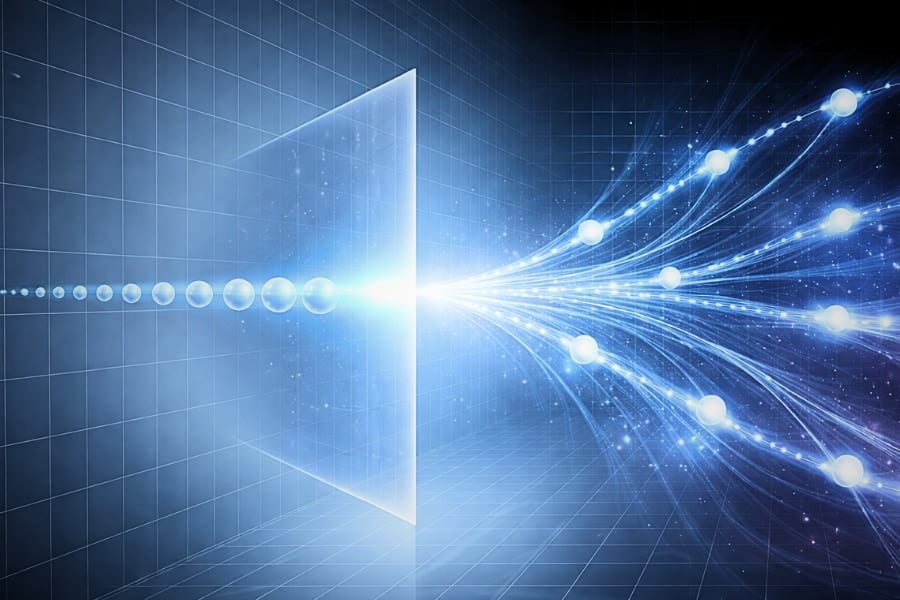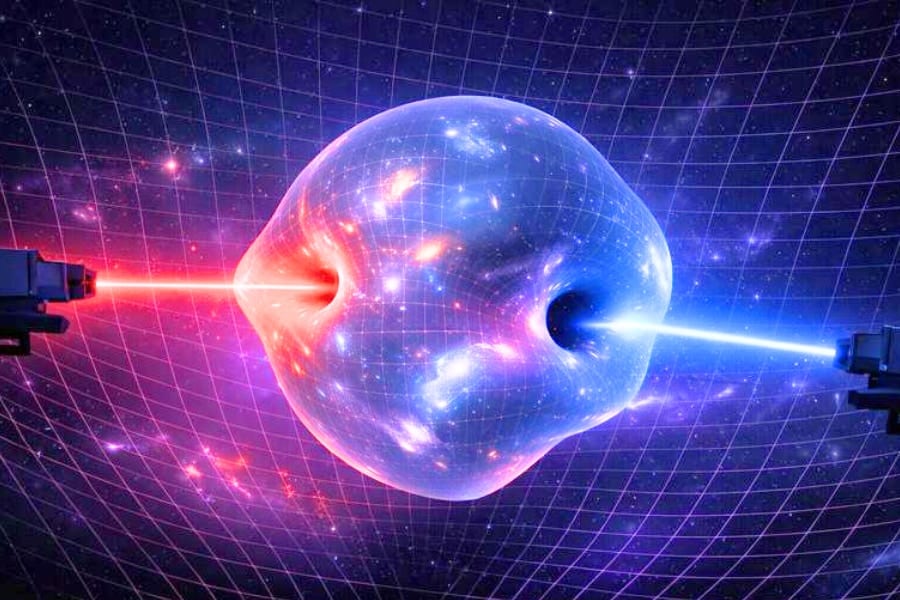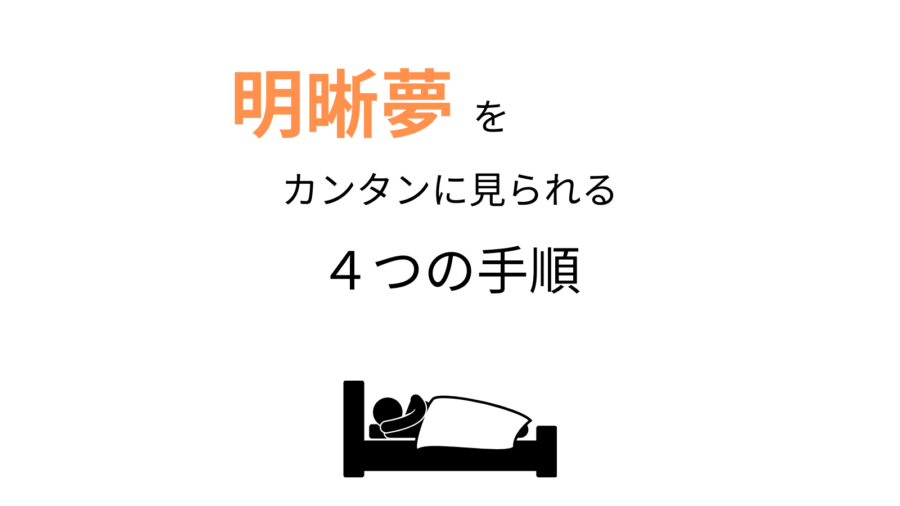「常温で量子現象」への長い道のり
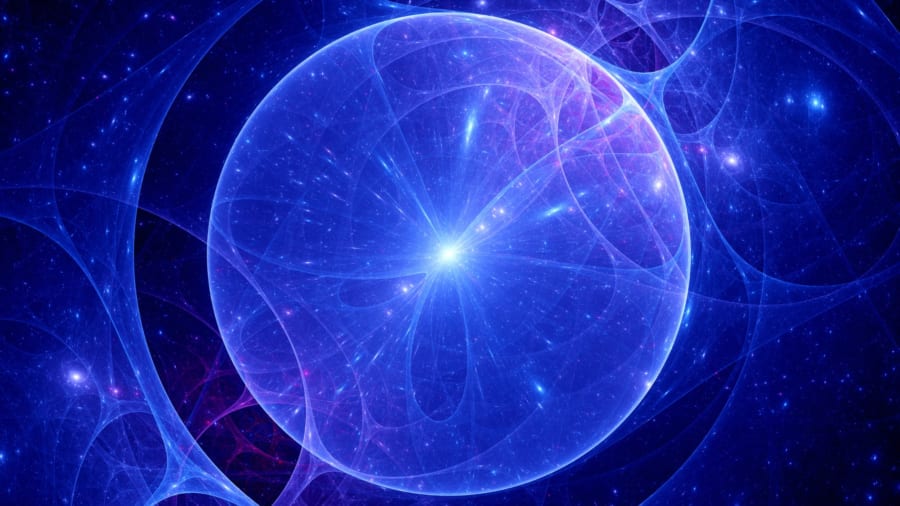
量子物理の不思議な現象は、ふつうは原子や分子のような、とても小さな世界でしか見られません。
しかし、それよりもずっと大きな物体でも、同じように量子のふるまいが起こるのかどうかは、長年にわたって多くの研究者の関心を集めてきました。
この疑問を解き明かすため、世界中で実験が続けられています。
当初は、ごく単純な分子を対象に実験が行われていましたが、その後、研究の対象は次第に大きな分子へと広がりました。
たとえば、炭素原子が60個集まったフラーレンという球状の分子では、量子の波のような性質が観測され、さらに数百個の原子からなる分子でも同様の現象が確認されています。
最近では、ナノサイズの微粒子や、非常に小さな「機械振動子」と呼ばれる装置を使った実験でも、量子的な揺らぎや「基底状態」(これ以上エネルギーを下げられない静かな状態)への冷却が少しずつ成功するようになってきました。
ただし、物体のサイズが大きくなったり温度が高くなったりすると、まわりの環境との相互作用が強くなり、量子の繊細な特徴はすぐに失われます。
このため、量子状態を作るには、粒子を外界からできるだけ切り離し、熱による揺らぎを抑える必要があります。
その手段として、真空中に粒子を浮かせて隔離し、さらに環境全体を絶対零度(−273.15℃)近くまで冷やす方法がよく使われてきました。
実際、比較的大きな「振動子(オシレーター)」を量子の基底状態に近づけるには、極低温冷却に加えて、レーザーやフィードバック制御などの高度な技術を組み合わせる必要があります。
そうした努力の結果として、極低温では非常に高い純度が得られていましたが、今回の室温実験はそれらを上回る純度に到達しました。
(※ここでいう「純度」は、基底状態にいる確率とは少し異なる、量子状態の混ざり具合を示す指標です。)
一方で、室温のままでこれを実現するのは非常に困難であり、これまでの記録では、粒子を光で浮かせて制御する「レヴィテーション系」で純度47%(n ≈ 0.6)、粒子を固定する「クランプ系」で純度34%が限界でした。
つまり、「常温で量子の静けさを引き出す」という挑戦は、長らく夢物語のように考えられてきたのです。
そんな中、今回の研究チームは画期的な方法を選びました。
それは、粒子全体を冷やすのではなく、特定の性質(たとえば回転などの自由度)だけにエネルギーを集中して抜き取るという戦略です。
粒子の他の部分は熱いままでも、その一部分だけを冷却すれば量子的な性質を引き出せると考えました。
実際の実験では、粒子の「回転運動」の揺れだけを狙って静め、量子的状態(基底状態)にすることを目指しました。




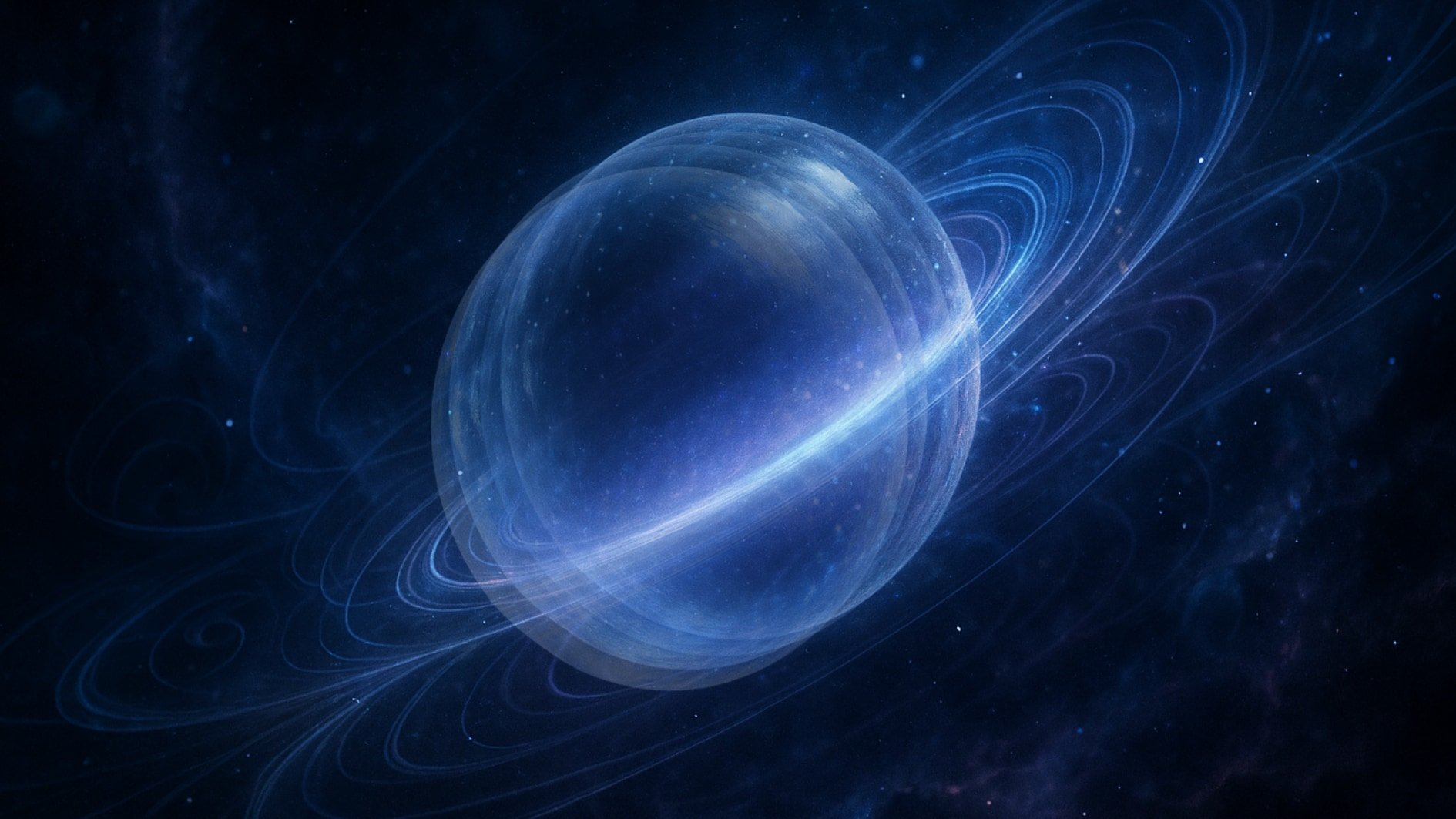









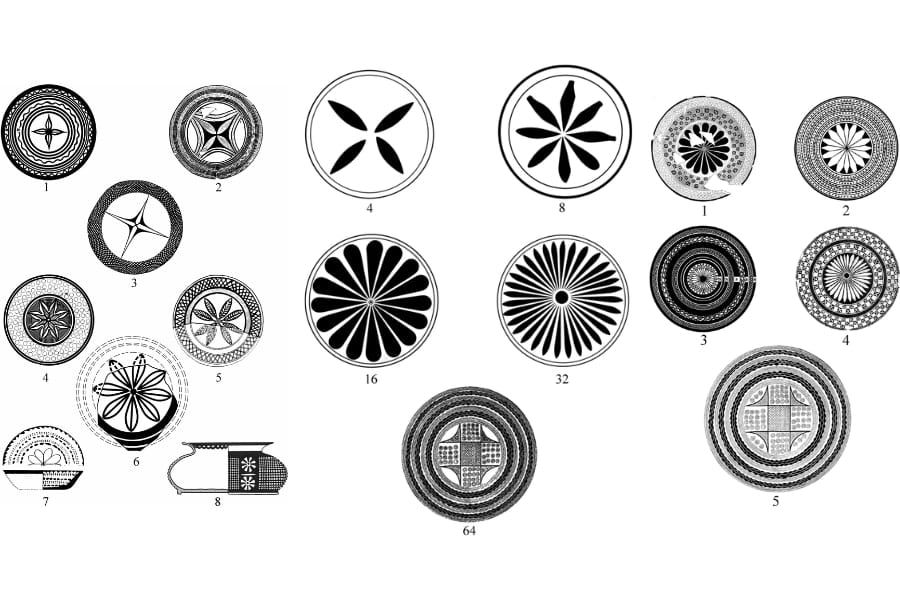

















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)