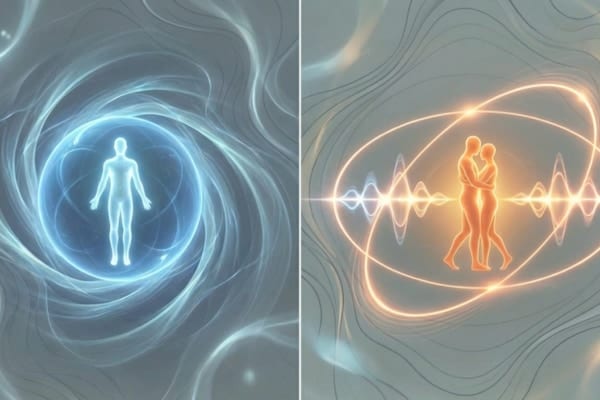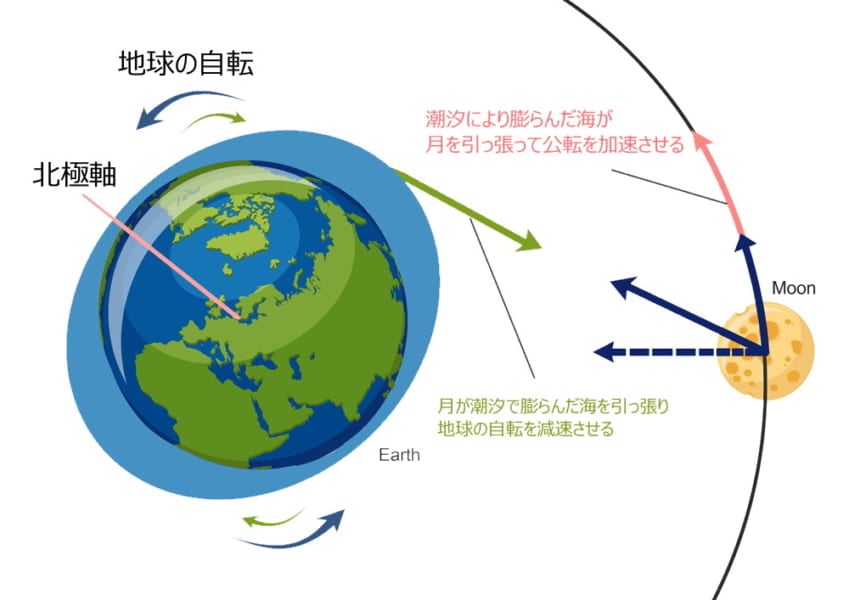決断は「助言」より「内なる声」? 世界規模で探った人類の意思決定のクセ
人生は選択の連続です。
転職すべきか、恋人と別れるべきか、引っ越すべきか、大きな投資をすべきか。
こうした重要な決断を前に、多くの人は「誰かに相談しようか」「一人で考えようか」と悩むでしょう。
このとき、私たちは本当に他人の助言に耳を傾けているのでしょうか?
それとも「やっぱり自分で決めたい」と思ってしまうのでしょうか?
この素朴な疑問に正面から取り組んだのが、今回の研究です。
主導したのはウォータールー大学の研究チームです。
彼らは北米・ヨーロッパ・アジア・南米にまたがる12か国(合計20地域)に住む成人3517人を対象にした、かつてない規模の国際比較調査を行いました。
対象者には、人生でありがちな決断の難しい6つのシナリオが提示されました。
例えば、大学をどこに進学するか、財産をどう使うか、隣人を助けるか自分の作業を優先するかといった具体的な場面が描かれています。
そして各場面について、次の4つの意思決定スタイルのうち自分ならどれを選ぶかを答えてもらいました。
1つ目は「直感」で、自分の第一印象や感覚に従って素早く決断する方法です。
2つ目は「熟慮」で、自分の頭の中でじっくりと利点・欠点を考えたうえで判断する方法です。
3つ目は「友人の助言」で、信頼できる友人に意見を求めてそのアドバイスに従うスタイルです。
4つ目は「群衆の知恵」で、複数人の意見を集めて多数意見や平均的な判断に従う方法です。
参加者は、これらのスタイルについて、どれを使いたいと思うか、どれが最も賢明だと思えるか、自分の文化の中でどれが一般的だと考えられているか、また実際に使ったらどれだけ満足感を得られそうか、といった複数の視点から評価しました。
調査はオンラインや紙ベース、また南米の先住民族に対してはインタビュー形式で実施され、データの信頼性を高める工夫がされています。
参加者の年齢や教育レベル、文化的背景も幅広く、まさに「人類全体の傾向」を探るにふさわしい設計となっていました。




















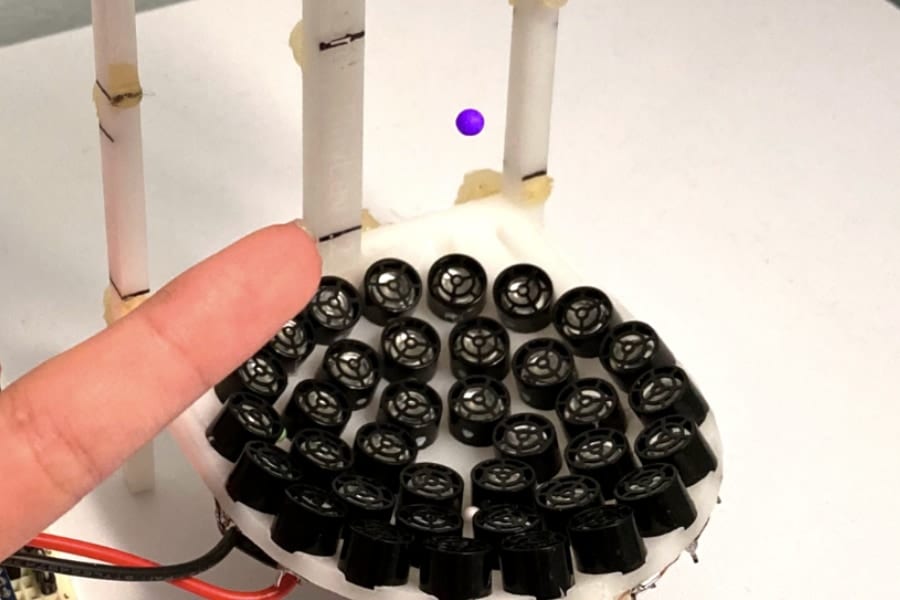









![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)