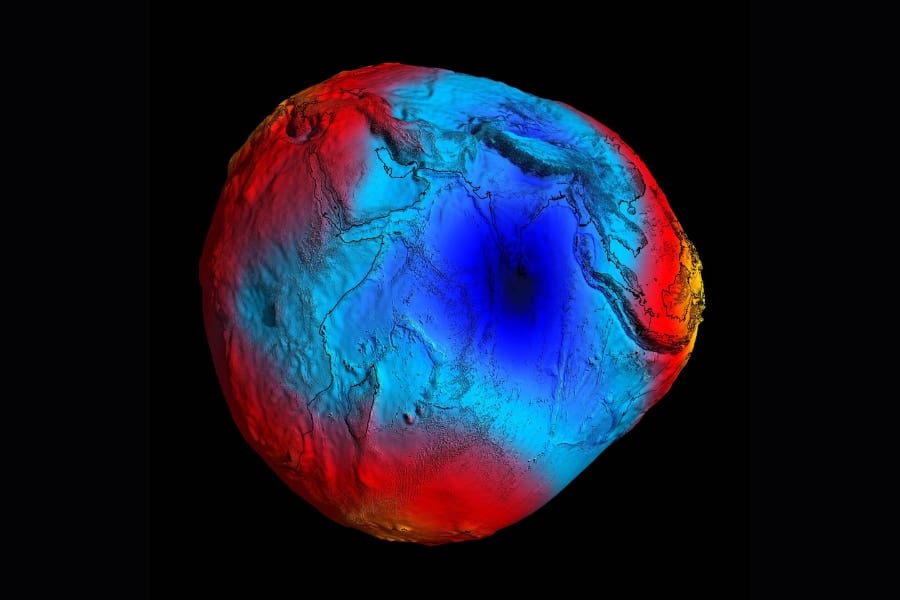「湯の花」が生態系を保存していた

研究チームはまず、国内の温泉地のなかから特に珪華(けいか:シリカを主成分とする湯の華)の調査に適した場所を探しました。
そこで選ばれたのが、長野県安曇野市にある「中房(なかぶさ)温泉」という温泉地です。
ここは北アルプスの燕岳(つばくろだけ)の山麓に位置し、急斜面の山あいにある「秘湯」としても知られる場所です。
1928年には、「中房温泉の膠状珪酸(こうじょうけいさん:ゼリー状のシリカ)および珪華」として国の天然記念物にも指定されていて、温泉成分が貴重な自然遺産として昔から大切に保護されています。
中房温泉の調査エリアは、ヒノキなど針葉樹が中心の豊かな森林に覆われていました。
研究チームが現地を詳しく調べてみると、約100メートル四方というそれほど広くない範囲に、直径がわずか数センチほどの小さな温泉の湧出口(お湯が地面からしみ出してくる場所)が、なんと32箇所も点在していることが確認されました。
それぞれの湧出口からは、摂氏80℃を超えるかなり高温の熱水が静かにしみ出し、森の中の斜面を細い流れとなってゆっくりと流れ下っていました。
この熱水には大量のシリカが溶け込んでいるため、地表に出て流れていく途中で温度が下がったり、水が蒸発したりすると、少しずつシリカが固まって珪華という白い層が出来上がります。
実際、中房温泉では、こうした珪華の堆積物が長さおよそ40〜56メートル、幅5メートル未満という帯状になって斜面に広がっていることが分かりました。
このような景色は、海外で知られるような巨大な間欠泉が噴き出す温泉地とはまったく異なり、熱水が静かに流れて豊かな森林と共存している、日本の島弧環境(とうこかんきょう:火山が連なる地帯)の特徴をよく表したものでした。
次に、研究チームはこの珪華の層をさらに詳しく調べるために、現地で実際にサンプルを採取して研究室で分析を行いました。
その結果、珪華の中には森に生えていたさまざまな植物の破片が数多く取り込まれていることが明らかになりました。
例えばヒノキのような針葉樹の葉や枝、小さな広葉樹の葉、木の実、そしてコケ植物のような小さな植物まで、本当に多彩な植物が珪華の中にそのままの形で封じ込められていました。
顕微鏡を使った詳しい観察から、これらの植物片の中には細胞のひとつひとつの構造までがはっきりと鮮明に残っているものもありました。
つまり珪華は植物を単に取り込むだけでなく、細胞レベルで植物の形をそのまま「石のアルバム」のように保存していたのです。
さらに植物だけでなく、小さな昆虫の体の一部や微生物までが珪華に取り込まれていることも今回確認されました。
このことから、中房温泉で作られた珪華は、周囲の森林に暮らす多様な生き物たちをそのまま閉じ込め、丸ごとパッケージ化した「天然の保存容器」のような役割を果たしていることが明確になりました。
また、研究チームは中房温泉の珪華がなぜこうした豊かな生物を保存できるのか、その環境条件にも着目しました。
調査エリアでは、斜面の上の方から多数の小さな湧き水がしみ出し、それらが細い流れとなって森の中を下っていきます。
湧出口付近ではお湯の温度が80℃以上と非常に高いため、この場所で形成された珪華には、主に熱に強い微生物の痕跡が多く残されていました。
しかし、熱水が斜面を下るにつれて徐々に温度が下がり始め、中流から下流に進むと水温が低下します。
するとそこには耐熱性の微生物だけでなく、コケ植物や森林の落ち葉、小枝など、多様な植物がシリカの沈殿によって次々に取り込まれていくようになりました。
つまり、熱水が流れる間に少しずつ温度が変化していくことによって、珪華が生き物を取り込む範囲や種類も変化していたのです。
とくに重要だったのは、熱水の流れの「縁(ふち)」の部分で珪華が特に厚く成長する一方で、水が常に流れている川底ではほとんど珪華が形成されなかったことです。
また、日当たりの良い南向きの斜面では太陽光で水がよく蒸発し、その結果シリカがより多く析出して珪華の成長がさらに活発になっていました。
このように、中房温泉の環境では、熱水の温度差や太陽光による蒸発といったさまざまな条件が絶妙に組み合わさって、植物や微生物を閉じ込めた珪華が形成されていることがはっきりと分かりました。
これらの結果は、海外の大規模な温泉地とは異なり、日本のような小規模な温泉環境だからこそ実現できる、多様な生物を化石として保存する新たなシステムを示した非常に重要な発見だと言えます。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)