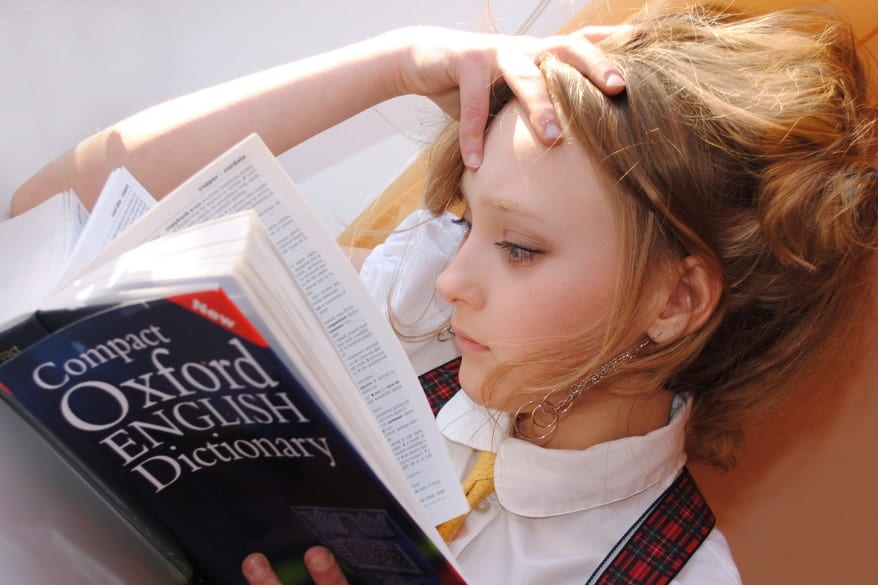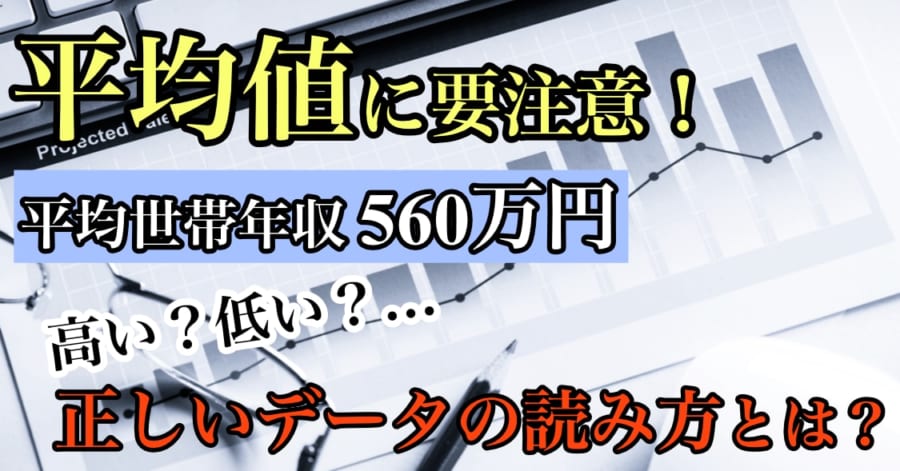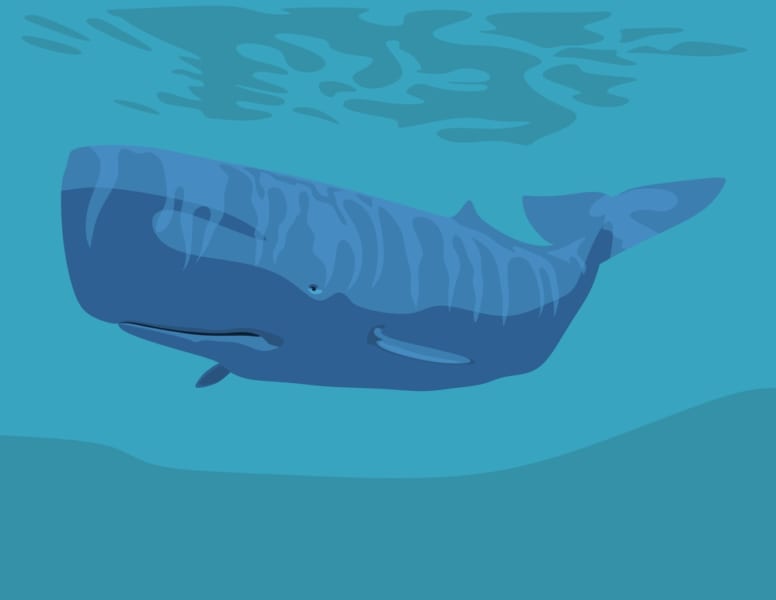感覚を増やしたら記憶はどうなるか

誰しも一度は「第六感」という言葉を耳にしたことがあるでしょう。
映画やマンガでも、「なんか嫌な予感がする!」と主人公が第六感を働かせるシーンはよくあります。
ただ、私たち人間は基本的に五感、つまり「視覚(目で見る)」、「聴覚(耳で聞く)」、「嗅覚(鼻で匂いを嗅ぐ)」、「味覚(舌で味わう)」、「触覚(肌で触れる)」で世界を記憶しています。
たとえば、リンゴについて考えてみましょう。
「赤くて丸い」という視覚的な情報、「シャリッとした歯ごたえ」という触覚や聴覚、「甘酸っぱい味」といった味覚。
こうした複数の感覚が組み合わさることで、リンゴという記憶は私たちの脳に強く鮮明に刻まれます。
では、もし「第六感」やさらにその上を行く「第七感」など、これまでの五感にはない全く新しい感覚が加わったらどうでしょうか。
たとえば、「磁場を感じることができる」「放射線を感知する」など、新しい感覚を人類が将来的に獲得したら、記憶力や学習能力が飛躍的にアップするのでしょうか。
一見すると「感覚が多いほど記憶は良くなる」と思いがちです。
ですが、ちょっと待ってください。
もし仮に感覚の種類が数十、数百、あるいは数千にもなったとしたらどうなるでしょうか。
たとえば、たった一つのリンゴという記憶にも、「重力の揺らぎ」や「紫外線の微妙な変化」といった、今はまったく感じ取れない情報が大量に付け加わるかもしれません。
そうなると、脳はそれだけの膨大な情報量を整理して記憶できるのでしょうか。
まるで片付けが苦手な人が、一気に大量の荷物を抱えてパニックになるように、脳も情報過多に耐えられなくなるかもしれません。
空想じみた話に聞こえるかもしれませんが、実はこうした「記憶に最適な感覚の数」は、科学の世界でも真剣に議論されています。
これまで、「記憶には多様な情報が含まれたほうが良い」という常識的な考え方がありましたが、それは本当に正しいのでしょうか。
もしかすると、記憶のシステムには最適な「ちょうど良い」感覚の数、つまり「臨界次元」が存在するのかもしれません。
これこそが、今回研究者が取り組んだテーマなのです。
ここで鍵になるのが、「エングラム(記憶の痕跡)」という、少し難しそうな言葉です。
エングラムとは、簡単に言えば「記憶が脳に刻まれる仕組み」のことを指します。
もう少し具体的に説明すると、「ある記憶に対応した特定のニューロンの集まり」です。
たとえばマンガのセリフを覚えている場合、そのセリフを記憶したときに活動したニューロンの集団が、あなたの脳に「エングラム」として残っているというイメージです。
実はこのエングラムという考え方は、最近出てきたものではありません。
なんと100年以上前から研究者たちが提唱してきた、歴史ある概念なのです。
とはいえ、私たちが普段エングラムという言葉を耳にすることはほとんどありません。
でも、「あのセリフを言っていたキャラ、なんて名前だっけ?」と思い出そうとするとき、私たちの脳ではこのエングラムがしっかり働いているのです。
さて、今回の研究チームは、このエングラムがどのように形成され、変化し、そして消えていくのかを詳しく調べることにしました。
といっても、人間の頭を割って中を調べることはできません。
そこで、研究者たちは脳内で起きているエングラムの働きをコンピュータ上のシミュレーション、いわば「仮想の脳」で再現することにしました。
具体的には、感覚の数(視覚や聴覚など)を「次元」という数学的な考え方で表現し、それを「概念空間」と呼ばれる記憶の世界に落とし込みました。
言い換えれば、「感覚が3つの世界」「5つの世界」「7つの世界」といった仮想空間をコンピューター上で作り、それぞれの世界で記憶の働き方を観察したのです。
この研究で明らかにしたかったのは、「感覚の数が増えると記憶できる概念(つまり脳内で区別できる記憶)は無限に増えていくのか?」という疑問でした。
それとも、「どこかに上限があり、それ以上は記憶能力が下がるのか?」という問いも重要でした。
こうして研究チームは、「記憶にとって最適な感覚の数=臨界次元」を求める冒険の旅に出たのです。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)