なぜ「7」が最適なのか?
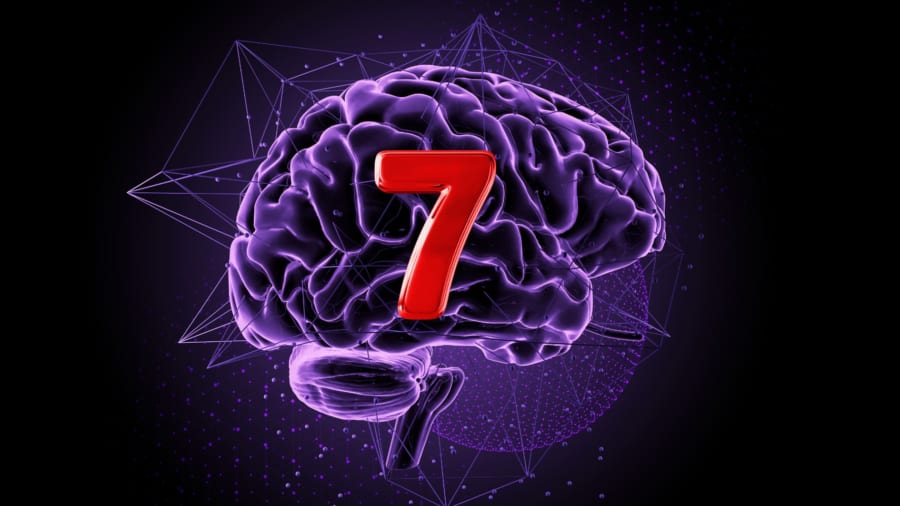
今回の研究が示した最大の発見は、「記憶には最適な情報量、つまり“臨界次元”が存在するかもしれない」ということです。
これまで、私たちは五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)をベースにして記憶を形成してきました。
しかし研究チームが示した数学モデルでは、感覚の種類が7つになったときに「記憶容量」、つまり区別して覚えられる記憶の数が最も多くなるという結果が出ました。
単純に「感覚が多いほど記憶力が良くなる」と思われがちですが、実際には増えすぎるとかえって逆効果になるという、ちょっと意外な結果です。
これは脳が「多すぎる情報」に振り回されず、「ちょうどよい複雑さ」を求めていることを示唆しているのかもしれません。
現実には、私たち人間がすぐに第六感や第七感といった新しい感覚を持つようになるわけではありません。
ただし、この研究の結果は「人工システム」や「ロボット」にとって大きなヒントになる可能性があります。
どういうことでしょうか?
例えばAIロボットにさまざまなセンサーを搭載する場合、「情報をたくさん取り入れれば賢くなる」と考えがちです。
ところがこの研究によると、情報を増やしすぎると逆に情報が混乱し、かえって頭が悪くなってしまう可能性があるというのです。
簡単に言うなら、「情報が多すぎて整理整頓が間に合わず、記憶がゴチャゴチャになる」というイメージです。
だからこそ、ロボットやAIを設計する人にとっては、「7種類くらいのセンサーで情報を集めるのが、実は最も効率が良い」と考えられるわけです。
研究者たちはこの「7」という数字が出現する背景として、エングラムの幾何的構造や空間詰めの問題など数学的な部分要因としています。
記憶をエングラムに頼るシステムを採用していると、7という数字がモデルの数式から自然に導かれるのかもしれません。
また、研究者たちはあくまで慎重に述べていますが、人間の感覚そのものが今後どう変わっていくのかにも、この研究は示唆を与えています。
つまり「未来の人類が磁場や放射線のような新しい感覚を身につける可能性もゼロではない」と考えられます。
この研究結果は、脳の仕組みをより深く理解するための今後の研究にもつながるでしょう。
脳が扱える情報の限界や「最適な複雑さ」を明らかにすることで、記憶を効率よくするヒントが得られるかもしれません。
例えば、異なる動物で「記憶できる情報量」を比較する研究や、人間が新しい感覚を学習したとき認知能力がどう変わるかを調べる新しいテーマも生まれそうです。
もちろん、この研究にも限界はあります。
最大の限界は、この結果が「数理モデル(コンピュータ上の仮想世界)」に基づいている点です。
現実の人間の脳が本当に同じように働くかどうかは、まだ証明されていません。
それでも、異なる条件でも一貫して同じ結果が得られている点は十分に価値があります。
また、今後の実験で検証されるべき大事な仮説を示したことにも意味があります。
最後に、この研究が投げかける意外な教訓をまとめてみましょう。
「感覚や情報は増やせば増やすほど良い」というのは思い込みで、むしろ「適度な複雑さと適切な情報量を効率よく整理すること」こそが大切かもしれません。
料理で材料を入れすぎると美味しくならないように、記憶や学習にも“ちょうどいい材料の数”がある、というイメージです。
この「ちょうどよい情報量」の追求が、今後の脳科学やAI研究の新しい目標となっていくでしょう。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)




















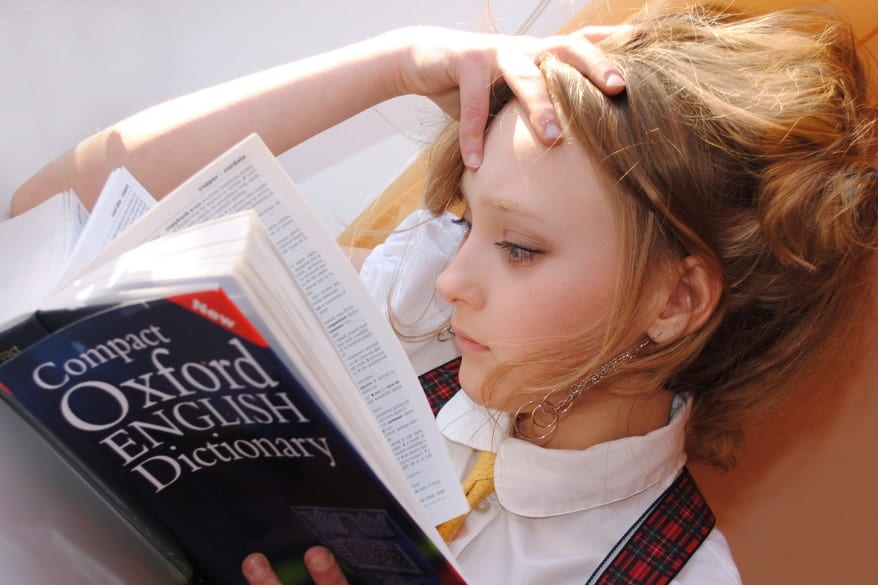
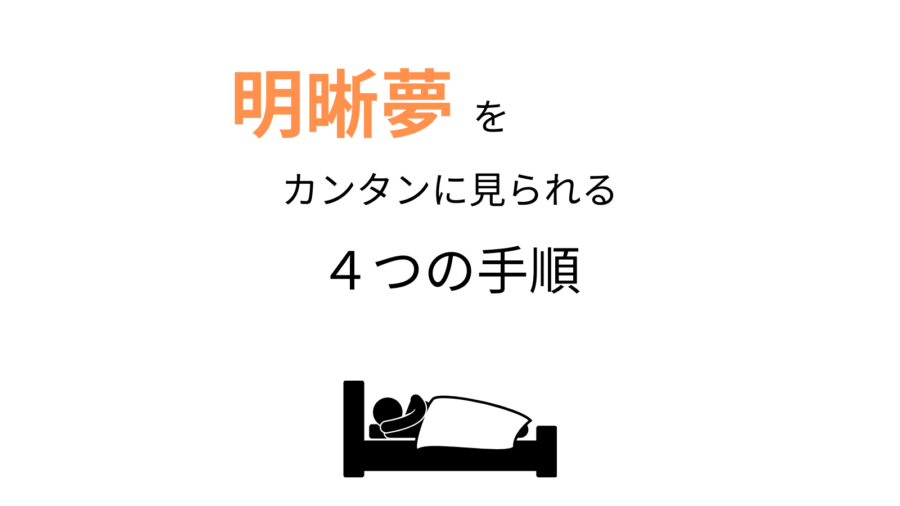







五感(視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚)の中の「触覚」は
皮膚感覚(触覚、圧覚、痛覚、温度覚)の中の一つにすぎません。
記憶の中には「あの時は暑かった/寒かったね~」というような温度と結びついたものもあります。
ジェットコースターに乗って「怖かった~」記憶には耳の中にある平衡感覚器も関連しているでしょう。
「昨日の練習はきつかった~」という記憶はには、骨格筋・腱・関節などで関知する固有感覚も関連しています。
…すると、もう7次元使ってない?
大変納得 思った
同感です。
視覚は網膜上の任意の一点が赤、緑、青の3色からなる色覚に、明るさに関する感覚を加えた4次元の情報を持っていて、それが上下左右の2次元に並んでいるから6次元です。
味覚も、一般的には甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の5味と言われているものの、それらに加えて「痛み」が混じった「辛味」もあるし、食べた物の温かさや冷たさ、歯触り、舌触りも関係します。更に言えば一括りに苦味とされている刺激も、詳しく見れば苦味を感じる受容体は25種類程存在しているので、味覚だけでも全部で30次元以上はあるのでは?
痛覚も針で刺された時のような「鋭い痛み」を感じる「一次痛」と、一次痛が感じられなくなった後も続く「鈍い痛み」を感じる「二次痛」の2種類がありますし、温度感覚も43℃以上の温度で活性化するTRPV1受容体による「(痛みを伴うような)熱さ」の感覚、30℃以上の温度で活性化するTRPV3受容体による「温かさ」の感覚、30℃以下の温度で活性化するTRPM8受容体による「冷たさ、冷涼感」の感覚、等々、温度感覚に関わる受容体が10種類程知られています。
平衡感覚も、内耳の耳石器で感知する「直線方向の加速度」や「頭部の傾き」は前後左右上下の3次元だし、同じく三半規管で感知する「頭部の回転」の感覚も前後左右上下の3次元だから合わせて6次元。
体外からの刺激だけではなく、空腹感、満腹感、「筋肉がどのくらいの力を出しているのか」や「筋肉や関節の伸び縮み具合」を感じる感覚に代表される「固有感覚」(こちらは筋肉や関節の数だけ次元がある事になります)や、空腹感、のどの渇き、尿意、内臓の痛み等の内臓感覚などもあります。
書いてはいませんが、感覚の種類は上記のもの以外にもあります。
すべての感覚を同時に記憶する必要があるという前提が間違っているのでは?
上の方々が指摘する「感覚が7つより多くある」という事実は記憶に際して「7つの感覚を利用する」ことと何も矛盾しないように思われる。
例えば人間にとってあまり鋭敏ではない味覚や嗅覚などの情報は食や音楽などよほどダイレクトにその感覚に直結しない限り記憶しておく必要はない。とすると、当然そこには情報の取捨選択があるはずだということになるわけで、必要のない感覚情報は「忘れる」という方法で切り捨てられているのではないだろうか。
>すべての感覚を同時に記憶する必要があるという前提が間違っているのでは?
別に誰も「すべての感覚を同時に記憶する」などという前提はしていないのように見えますが?
他のコメントでは「使っている感覚の数」の事しか問題にしておらず、「同時に覚える感覚の数」の話などしていません。
同様に記事においても
>感覚の種類が7つになったときに「記憶容量」、つまり区別して覚えられる記憶の数が最も多くなるという結果が出ました
>簡単に言うなら、「情報が多すぎて整理整頓が間に合わず、記憶がゴチャゴチャになる」というイメージです。
と述べています。
つまり
>情報の取捨選択があるはずだということになるわけで、必要のない感覚情報は「忘れる」という方法で切り捨てられている
という事が起きていると仮定した場合、「使用している感覚の数」が多すぎると、その「必要のない感覚情報を切り捨てる」という処理が上手く行かなくなると述べられているわけです。
だから問題になるのは「覚える感覚情報の数」ではなく、「(「必要のない感覚情報を切り捨てる」前の段階で)使っている感覚の数」という事になります。
確かに現状でも感覚は五つに留まらないな。記事では五つに限っているが、論文ではその点をどのように記述しているか気になるところ。しかし他の方が言うように、7つが最適という話とも矛盾はしないな。
感覚には強度もあり、その順位の低いものは切り捨てられたり、複数がひとつの感覚に統合される可能性もあり、エネルギーコストも加味した上で最適化されてるのかもしれない。
聖闘士星矢のセブンセンシズか
小宇宙(コスモ)を燃やすことが、記憶容量アップにつながるのか!
すると阿頼耶識に覚醒している乙女座のシャカは他の黄金聖闘士よりも記憶力が悪くなっているのか!
「でしょうか」「ですが、ちょっと待ってください」を連発するようになったね。AIかな?
投げかけるのは効果的だと思うけど多用しすぎて逆に読みづらい。
1ページ目の「でしょうか」二連発からの「と思いがちです」→「ですが、ちょっと待ってください」が特に。
間の無根拠な「と思いがちです」も疑問。
俗説なのか定説なのか筆者の主観なのか。
科学的な論文をもとにした記事なのに曖昧でノイズになっている。
記憶には色々な感情も絡んでいるはず、もしそうなら感情の次元も考慮すべき。全ての記憶に感情が絡むのではないかもしるないが、だからといって感情を全く考慮しない記憶の考察は意味がない。また同時に複数の感情も感じられるとするなら、(余り使わなそうな感覚は無視しても)記憶に関する基本的次元数は基本的にもっと多いのでは。最適次元数が幾つかはそこから考えられそうだ。