「運動」と「座りっぱなし」は、骨の健康にそれぞれ独立して影響を及ぼす
レビューの結論は明快で、運動と座りっぱなしは骨の健康にそれぞれ独立して影響するということでした。
つまり、運動をしていても長時間の座位が続けば骨にはマイナスが残り、逆に激しい運動が難しくても座る時間を減らしてこまめに動けば骨にはプラスが積み上がります。
子どもや思春期では、テレビやスマホなどのスクリーンタイムが長いほど、体重を支える部位の骨密度が低くなる傾向が示されました。
一方で、走る、跳ぶ、筋トレなどの負荷のかかる活動は、成長期の骨量をしっかり増やすことに役立つと報告されています。
成人期では、中〜高強度の体重負荷運動やレジスタンストレーニングが骨密度の維持に有効で、骨折リスクの低減とも結びつきます。
しかし、日中の多くを座って過ごす生活により、股関節や大腿骨など体重を支える部位の骨密度が下がりやすいことも明らかになりました。
高齢者や閉経後女性では、たとえ軽い活動であっても、座っている時間を動きに置き換えることが骨の維持に意味を持つことが示されました。
家の中の移動や家事、短い散歩などの積み重ねでも、座りっぱなしを続けるより骨には有利に働いていたのです。
今回の結果からすると、骨の健康を守るために日常で私たちが実践すべきことはシンプルであり、それはWHOのガイドラインとかなり一致していました。
子どもは1日60分以上の身体活動を確保し、スクリーンタイムをだらだら延ばさないようにすべきです。
成人は週に150〜300分の身体活動、そして全世代に共通して、長時間の座りっぱなしを避け、こまめに立ち上がって体を動かすべきです。
この「運動を増やす」と「座る時間を減らす」を両立させる視点こそが、骨を守るための新しい基本になるでしょう。
この知見は、職場や学校、地域でも反映させられるかもしれません。
例えば、立って話し合える場や、歩きやすい動線、気軽に体を動かせる環境があれば、座りっぱなしを自然に減らせるでしょう。
一方で、今回のレビューには限界もあります。
多くの研究が自己申告データに依存しており、食事内容や体重、性差、社会的要因を完全にコントロールできない場合があります。
座位のどれくらいを、どの活動に、どの年齢層で置き換えると最も有効かという「最適処方」も、今後の検証課題として残っています。
それでも、運動の恩恵と座りっぱなしの害が別々の軸で骨に作用するという全体像は揺らぎません。
骨は一生ものの資産なので、今日からできる小さな置き換えを積み重ねることが将来の骨折リスクを減らします。
運動だけではなく、まずは座りっぱなしの時間を見直すことから、骨を守る新しい一歩を始めましょう。



























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)


![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)
![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




















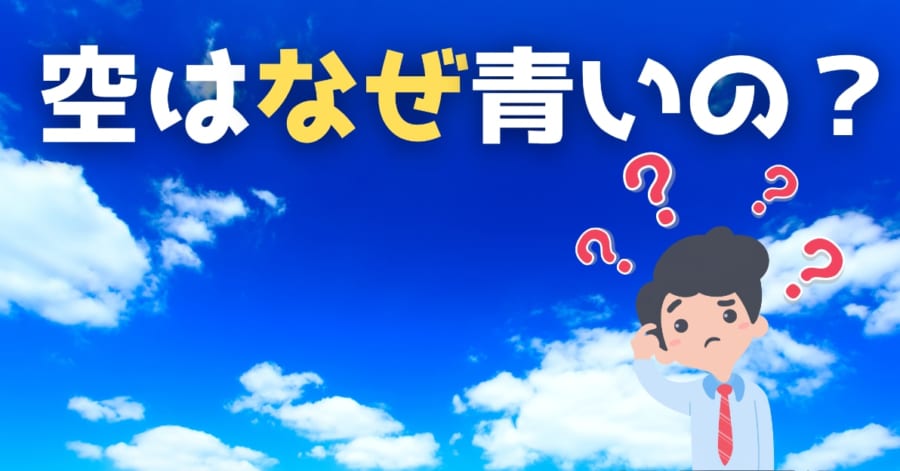







これよく言われてるけど、どう考えても座りっぱなしより休日に一日中寝転がってるヤツのほうが体に悪いだろ。
少なくとも姿勢よく座っていれば脊椎やその周囲の脊柱起立筋にも重力による負荷はかかってる。もちろん下肢や大腿骨の骨董関節にも。
寝たきりによるフレイルの害は常識なのに、そっちを強調しないのは筋違いだ。
じゃあ立っていればいいかというとそんなこともないって研究もあるようですし、なんとも難しい。
過ぎたるは及ばざるがごとしでしょ
どのあたりでバランスとるのがいいかは知らないけど
ドイツにいたとき、路面電車やバスで、親は座席に掛けてもその子どもは立たせておくことをよく見かけました。日本では子どもだけでも座らせる場面をよく見かけます。
大人の骨密度維持は座位を短くすべきとして、子どもの発達はどうなんでしょう。