いじめ被害者の脳は子ども時代に敏感化し、成人後は鈍感化する
研究チームの解析では、いじめ被害の有無に対して、「友だちとの好意的やりとり」などの場面に対する脳反応には、特に優位な差が見られませんでした。
しかし、いじめ場面を見たときは、いじめ被害にあった人は異なる脳反応を見せたのです。また興味深いことに、大人と子どもの間でもまるで異なる反応を見せたのです。
思春期の脳は、いじめ場面に対して強い反応を示し、体の感覚や運動に関わる領域まで活動が高まっていました。これは「言葉や態度によるからかい」であっても、まるで「殴られたり押さえつけられる」ような脅威として脳が過敏に反応していることを意味します。
一方、成人ではいじめ場面に対する反応は限定的で、特に注意や警戒に関わる領域では活動が弱まっており、思春期に見られた体の感覚なども低下していました。つまり成人になると、いじめの場面を見ても“危ないぞ”と知らせる脳の警報が弱まっていたのです。
著者らは、このような傾向が、繰り返しのストレスにさらされたことで「過度に反応しないように鈍くなった」可能性を考察しています。
また成人グループでは子どもの頃にいじめを受けていた期間が長い人ほど、この影響が強くでていたという。
いじめによる脳の変化は、社会生活にどう影響するのか?
思春期は仲間からの評価や立ち位置に敏感で、攻撃的な刺激に対して脳が「過敏化」しやすい時期です。そのため、いじめ被害者の子ども時代の脳の反応は、短期的には自己防衛につながるかもしれませんが、強すぎる警報が続くことで、心身に負担を積み重ねてしまいます。
これは想像以上に強いストレスになる恐れがあり、また新たな人間関係を築くことを困難にしてしまいます。
一方、大人になってから子どもの頃のいじめを思い出す人では、反応が鈍化する「脱感作」の可能性が示唆されました。これは一見すると「慣れ」にも見えますが、実際には脅威を正しく察知できなくなるリスクを示しています。
この結果、社会生活や職場で受ける攻撃的な他者の態度を過小評価し、問題への対処や周りに相談するなどの行動が遅れる恐れがあります。そして、再びいじめ被害に巻き込まれる危険性を高める可能性があるのです。
また今回はいじめを再現した主観映像から、脳の反応を見ていますが、脅威に関する脳反応が低下するということは、いじめ以外の脅威に対しても反応が低下する可能性も考えられます。
もしこの影響が非常に強く出た場合、物理的な脅威がある場面でも反応が低下して命を守る行動が適切に取れないという問題にも繋がるかもしれません。
この研究は、いじめが単なる心理的な嫌な思い出ではなく、脳の反応パターンそのものを変えてしまう可能性を示しました。
ただ、この研究は「相関」を示したものであり、いじめが直接的に脳を変化させたという因果関係を証明しているわけではありません。発達障害など、子ども時代にいじめにつながりやすい特性を本人が持っており、その特性が脳に現れていただけという可能性も考えられます。
また、いじめに対してどれだけ外部の支援(家族、友人、専門家)があったかによっても、その後の影響の大きさが変わる可能性があります。
いじめの被害にあったとしても、安心して回復できる環境が整えば、脳に刻まれた影響も和らげることができるかもしれません。
いじめの経験が長く脳に影響を残す可能性があるのなら、そのケアはより重要な問題となっていくでしょう。
































![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



















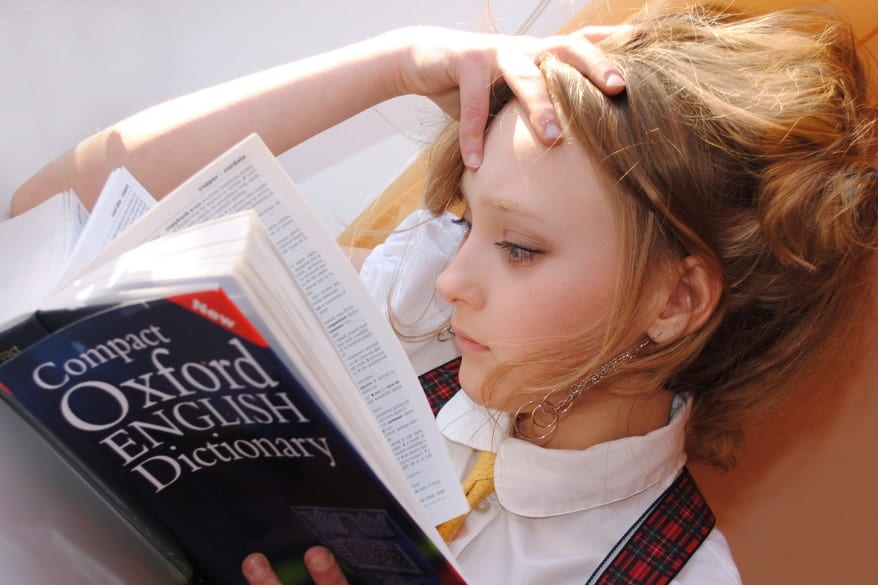


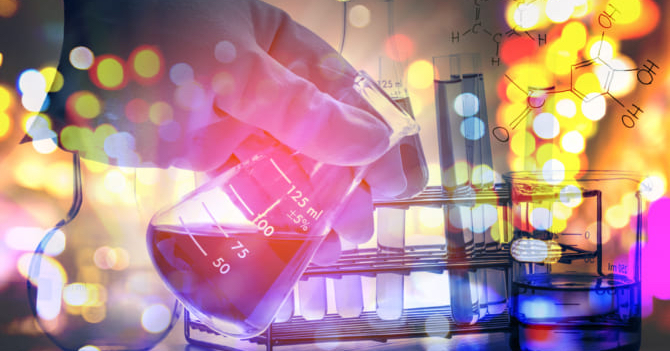






いじめを受けると脅威に対する感覚が破壊されてしまうのだろうか?
あるいは脅威から逃れることを諦めやすくなるとか
アオイが鬼に怯んでも、カナヲが家子として鬼狩りをしている背景に、このメカニズムがあったりしますか?
福井大学の友田先生の著書で、児童虐待を受けた子どもの海馬や扁桃体が年齢とともに非可逆に体積変容するとしたご自身の留学先での研究を紹介されていました。これをもとに想像するなら、いじめを受けた児童についても、被害年齢や継続期間、態様によって可逆・非可逆な形態的変化が起こる文脈でスンと受け入れることができそうです。
経験的現象として、いじめられっ子が年長になっていじめっ子に転じたり、被虐待児が大人になって虐待親になる事例があるようです。これらは、純粋に心理的要因なのか、形態的・生理的要因が背後にあるのかは、治療やハイリスク家庭の予防の観点で興味があります。
コールセンターで客よりも理不尽なお局さんのせいで、感覚ぶっ壊れて転職先で叱られても何も感じなくなった