静電気を味方にする生き物たち

私たちがドアノブやセーターに触れたとき、よく「パチッ!」とくるイヤなあの感覚、ありますよね。
あの正体は「静電気」と呼ばれる、体に帯びた電気が瞬間的に放電される現象です。
私たち人間にとって静電気は、冬場のちょっとしたイライラの種くらいの存在ですが、自然界に暮らす小さな生き物たちにとっては、まったく違った役割を持っています。
じつは、この静電気は、生き物たちが生き延びるための「便利な道具」になっていることが、最近の研究でわかってきたのです。
たとえばミツバチ。
ミツバチは羽を高速で動かすことで、体にプラスの電気を帯びます。
一方、花粉の粒はマイナスの電気を帯びていて、プラスとマイナスの電気がお互いに引き寄せ合うことで、ミツバチは効率よく花粉を集めることができます。
また、クモもこの静電気をうまく利用しています。
クモの巣はマイナスの電気を帯びており、空を飛ぶ昆虫が羽ばたきによってプラスの電気を帯びているため、クモの巣に引き寄せられてしまいます。
いわば、昆虫を捕まえるための「静電気トラップ」になっているわけですね。
さらに意外なことに、ダニのような小さな虫も、静電気をうまく活用しています。
動物の毛皮はこすれ合うことで静電気を発生し、小さなダニはその静電気に引き寄せられることで、動物の体に簡単に飛び移ることができます。
つまり、小さなダニにとって静電気は、自動的にエレベーターのように吸い上げてくれる便利な存在なのです。
さて、こうした静電気をうまく使う生き物のなかで、今回の研究の主役となったのが「線虫(せんちゅう)」という小さな生き物です。
「線虫」という言葉は聞きなれないかもしれませんが、イメージとしてはミミズをものすごく細く短くしたような生き物だと思ってください。
主に土の中に生息し、体は非常に小さく、多くは0.4ミリほどのサイズで、肉眼ではギリギリ見えるかどうかという小ささです。
この線虫の中でも特に今回取り上げられているのが、「シュタイネルネマ・カーポカプサエ」という種類の線虫です。
名前は難しいですが、やっていることはかなりワイルド。
なんと昆虫に寄生して、それを殺してしまう寄生性の線虫なのです。
こう聞くと怖そうなイメージを持つかもしれませんが、実際にはこの線虫は人間の農業を助けてくれるありがたい存在です。
害虫を殺すことから、生物農薬(生きた生き物を使った害虫駆除法)として世界中で広く使われています。
では、体長わずか0.4ミリほどしかないこの線虫が、いったいどうやって自分より遥かに大きな昆虫を捕まえるのでしょうか?
この方法が、実にユニークなのです。
この線虫は土の表面にじっと待ち伏せしており、頭上を昆虫が通りかかるのを察知すると、体をクルリと輪っかのように丸めます。
まるでゼンマイ仕掛けのおもちゃが跳ねるように、強力なバネのように体を伸ばし、一気に空中へジャンプします。
そのジャンプ力は自分の体長のなんと約20〜25倍。
これを人間に例えるなら、10階建てビルを一気に飛び越えるような驚異的なパワーです。
ただし、この大ジャンプにはとても大きなリスクが伴います。
狙った昆虫にしっかり命中しなければ、空中に放り出されて天敵に捕まるか、干からびて死んでしまうという、まさに命懸けのギャンブルジャンプなのです。
それにしても、そんな大ジャンプをして高速で移動する昆虫にピタリと命中するのは、常識的に考えても至難の業ですよね。
線虫はいったいどのような方法で、この「命懸けの空中キャッチ」を成功させているのでしょうか。




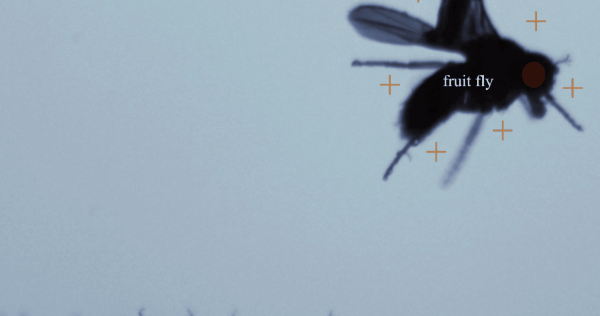























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[コロンブス] キレイな状態をキープ 長時間撥水 アメダス 防水・防汚スプレー420mL](https://m.media-amazon.com/images/I/31-OcmTs2LL._SL500_.jpg)
![シルバーバック【カンタン!たのしい!水の生きもの砂絵セット】 幼稚園 小学校 入園 入学 お祝い プレゼント 準備 ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/515gZ4F-QYL._SL500_.jpg)



























