気温が高いとヘビが活発になる?
ヘビの体温は外部の気温に依存しており、寒ければ体温も低下し、暑ければ体も熱くなります。
実際、ヘビの活動量は気候によって大きく変動することが知られ、冬場は冬眠をするのでほとんど動きません。
反対に、春〜夏にかけての暖かい時期はヘビも活発になり、繁殖シーズンに入ります。
現に今回の調査によると、ヘビに噛まれた総件数は夏場が最も多くなっていましたが、特に気温とヘビ咬傷の関連性が強かったのは春でした。
スコブロニック氏によると、春はヘビが寒さから目覚める季節であり、気温の上昇に伴ってより活動的になりやすいと説明。
一方で、夏場の気温が高くなりすぎる日はヘビの体が火照りすぎて、逆に動きが鈍くなる可能性もあると話しています。
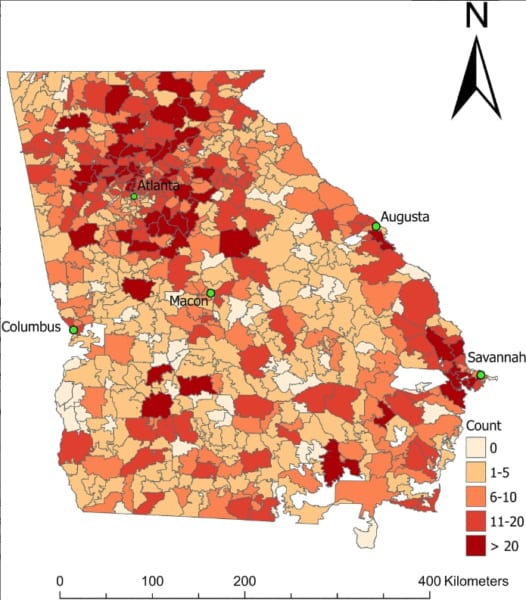
それからチームは、同じ関連性が他の危険生物にも見られるかを調べてみました。
ここでは身近にいるクモ、サソリ、スズメバチを対象としましたが、気温と被害件数との間に強い関連性は見られず、ヘビに特有の現象であることが示されています。
また研究者らは、土地開発や都市部の拡大によりヘビと遭遇する確率が高まっているため、今後さらに被害が増加するかもしれないと指摘しました。
日本でも気をつけるべき?
世界保健機関(WHO)の推計によると、ヘビによる咬傷は世界で年間500万件を超え、毎年13万8000人が死亡しています。
同チームのローレンス・ウィルソン(Lawrence Wilson)氏は「ヘビとの遭遇を減らすために必要なのは公的な教育です」と話します。
「ヘビが好む生息地(例えば茂みが密集しているような場所など)を広く知ってもらうことで、危険な遭遇を回避することができるでしょう。
ヘビと人間は、たとえ毒ヘビであっても、彼らの生息地とニーズを尊重し理解すれば、十分に共存できるのです」

また今回の結果は、私たち日本人にとっても決して無関係ではありません。
日本の野生にガラガラヘビはいませんが、毒ヘビはニホンマムシ、ヤマカガシ、ハブの主に3種類が存在します。
このうち、ハブは沖縄のみに分布しますが、マムシとヤマカガシは日本全国に広く分布しています。
茂みの中にむやみに手を突っ込んで、ヘビに噛まれるケースも少なくありません。
これからの熱くなる季節、草むらや藪に近づく際は「ヘビの噛みつき」を念頭に置いておくべきでしょう。






























![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)

![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)



























