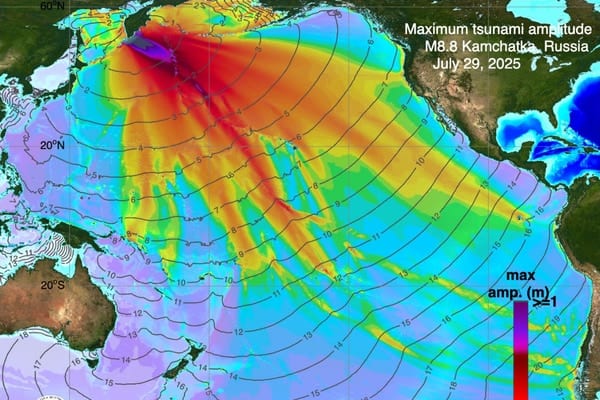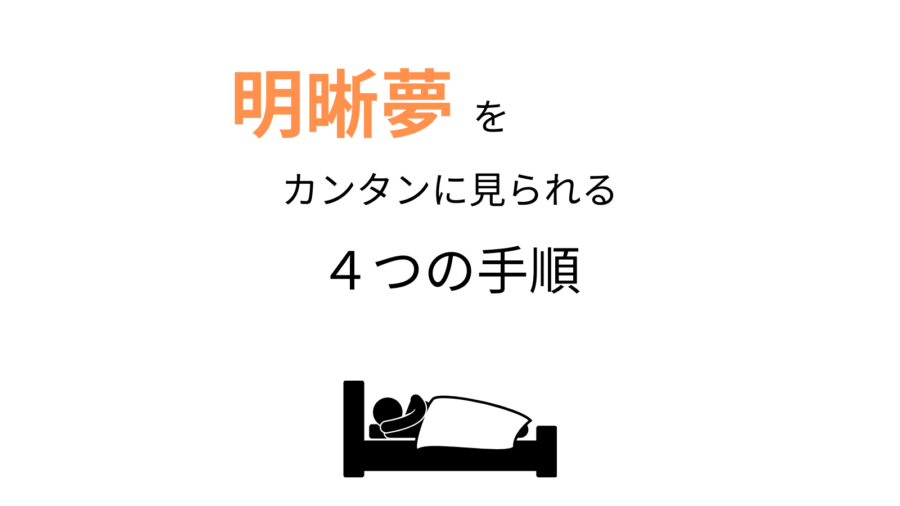極寒の南極生活は過酷だけど楽しい
――南極にはどのくらい滞在されたんですか?
板木:南極観測は、夏の3カ月間滞在する夏隊と、1年を通して滞在する越冬隊に分かれているんですが、私が参加したのは夏隊だったので、2019年11月に南極に向けて出発して2020年3月に帰国しました。
――南極の滞在場所というと昭和基地が有名ですが、ずっとそこを拠点にする感じなんですか?
板木:昭和基地にも数日間滞在しましたが、基本的には基地から出て調査をしていたので、キャンプをしながら野外で3週間ほど過ごしました。
昭和基地に滞在した時は、夏隊用の宿舎で過ごしました。居心地が良いとはいえませんが、無人の山小屋に似たような雰囲気がなんとなく懐かしい感じがして私は好きでしたね。
キャンプでは、ミーティングや食事スペース用の大きなテントの他に個人用のテントが割り当てられていて、そこで生活していました。

――南極のキャンプってどんな感じなんですか?
板木:発電機とかガスコンロは持参してました。食料と水は減ったら、無線の定時交信で“しらせ”からヘリで運んでもらっていました。
ただレタスなんかの新鮮な生野菜は手に入らないので恋しくなりましたね。そんな時に有り難かったのがリンゴで、「ふじ」のように長期保存に適した品種があって、4カ月経っても美味しく食べられました。これにはちょっと感動しました。
あと、個人的にビールを1日3本換算として360本くらい持ち込んだんですけど、仲間にも分けたりしているうちに思ったより早く減っていって、最後の1カ月あたりは枯渇したのが地味に困りましたね(笑)
――そう聞くとほんと登山やキャンプの延長みたいで楽しそうですね。
南極って通信環境はどうなっているんですか? 滞在中、家族と連絡は取ったりすることはできるんですか?
板木:家族と連絡はほぼ取れなかったです。僕が行った当時、衛星電話はありましたけど結構お金がかかりましたし、インターネットもつながりはしましたが、かなり制限があってネットで動画の再生は厳しい状況でした。
――先程の映画の話もそうですが、南極基地では閉鎖された環境で隊員が精神的に参ってしまうという問題を見かけますが、外部との通信も限られていると、精神的にキツくなったりしませんでしたか?
板木:私は楽しかった記憶しかないですね。
越冬隊だと一年半と期間が長い上に、冬は極夜で太陽が昇らないので、かなり精神的に辛い状況になるようですが、私は夏に行ったので白夜で太陽も一日中出ていたし、毎晩仲間と飲んで、まるで大学の寮生活みたいですごく楽しかったです。
それから、ペンギンにはかなり癒されました。南極のペンギンは人を知らないから怖がらずに好奇心で近づいてくるんです。作業している横に10羽くらいでゾロゾロやってくるのがもう可愛くて。
群れで移動中に1羽遅れたらそいつをきちんと待ってから進んだり、親ペンギンが子ペンギンの世話を一生懸命したりしている姿を見ると、こうやって彼らは厳しい自然の中で生きているんだなと感心して、一気にペンギンのファンになりました。
ただ、営巣地付近は糞がものすごくて凄まじい臭いでしたね。それはちょっと幻滅しました(笑)
――動物園ですらすごく臭いですし、それは確かに現地に行かないと感じられない事実ですね。他にも南極ならではのエピソードや珍事件ってありましたか?
板木:そうですね、アザラシのミイラが陸上の至る所に転がっていた……とかでしょうか。
アザラシは体に油が多いことに加え、南極が低温かつ乾燥しているため、分解者となる微生物が少ない環境なのでミイラ化しやすいんです。陸上の調査で歩き回っていると、あちこちでアザラシのミイラを見かけるんです。
以前にこれらのミイラがいつのものか調べた研究者がいるそうですが、ほとんどが2,000〜3,000年前のものだったそうです。私たちが見たミイラもそのくらい古かったのかもしれません。びっくりですよね。















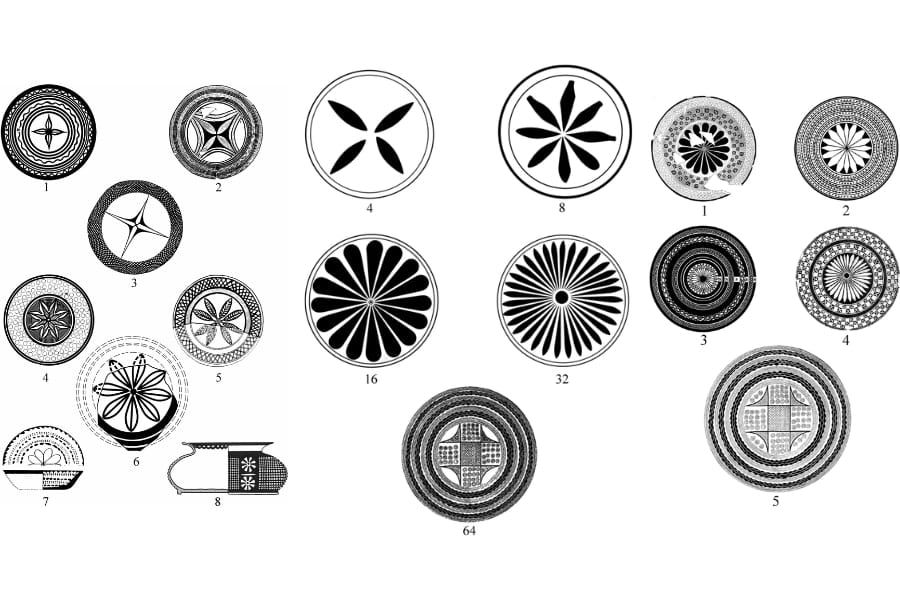


















![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)
![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)
![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)