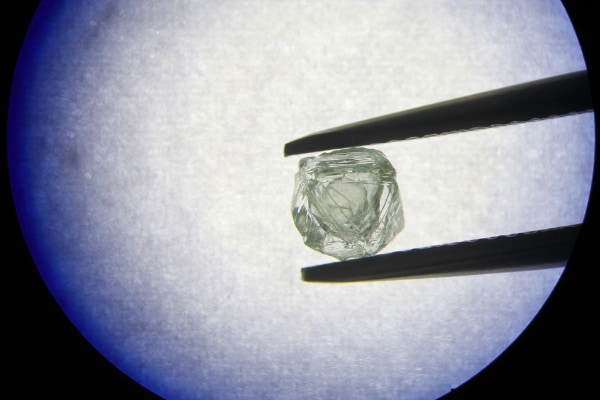小説内の描写から始まった女相撲

江戸時代というもの、なんとも面妖な時代でございます。
浮世の喧騒に紛れ、奇妙奇天烈な文化が花咲いたことは数多あれど、「見世物女相撲」なる一興もまたそのひとつ。
これを語らずして江戸の風情を語るなかれ、と言いたくなるものです。
さて、この女相撲、まずは文芸の世界にひょっこり顔を出しました。
天和2年(1682年)の井原西鶴『好色一代男』や、貞享5年(1688年)の『色里三所世帯』には、絢爛豪華な庭先で繰り広げられる女相撲が描かれております。
さらには近松門左衛門の浄瑠璃『關八州繋馬』にも、金太郎伝説をもじった趣向で、女相撲の場面が登場いたします。
されど、この時代における女相撲はあくまでフィクションの産物で、実際に興行として催された記録は皆無。
いわば絵空事の遊びでございました。
時は延享年間(1744年頃)に移り、ついに江戸・両国にて見世物としての女相撲が興行されるようになります。
当時の史料によれば、江戸の町では、「おお、男相撲よりも面白いかもしれぬ」と囁かれるほどに評判を呼びました。
これが単なる私催ではなく、興行として多くの見物客を集めたことは明白。
しかし、これが単なる品のない見世物だったのかと言えばそうとも言い切れず、「美しさと力強さの対比」が特筆されたことも興味深い点です。
続く明和年間(1768年頃)には、上方(京や大坂)でも女相撲が大いに流行します。
中には、力強さで知られる「板額」という名の力士が登場し、その勇姿が町人の間で語り草となるほどでした。
ところが、禁制の足音もまた速やかに迫り、この風潮は一転して抑圧される運命に。
京や大坂では、わずか数日のうちに興行が禁止されるという具合でございました。
それでも人々は工夫を凝らし、動物相手の相撲や盲人との組み合わせなど、より奇抜な形式で娯楽を追い求めました。
文政9年(1826年)の両国では盲人と女力士が土俵で交わる様子が記録され、そのユニークさはまた別の熱狂を呼び起こしました。
嘉永年間(1848年頃)には、女力士たちが美声を披露しつつ踊りまで加え、観客を沸かせる新たな形式も登場。
もはやこれが相撲と呼べるのか、という疑問を抱かせるほどに華美で、演芸的な要素が色濃くなったのでございます。
こうして時代の波に揉まれながら、女相撲という風俗は一種の娯楽として受け継がれていきました。
時に華やかで、時に物悲しく、それでもなお人々の心を掴み続けた姿は、まさしく江戸文化の一端を彩る光景であったと言えましょう。












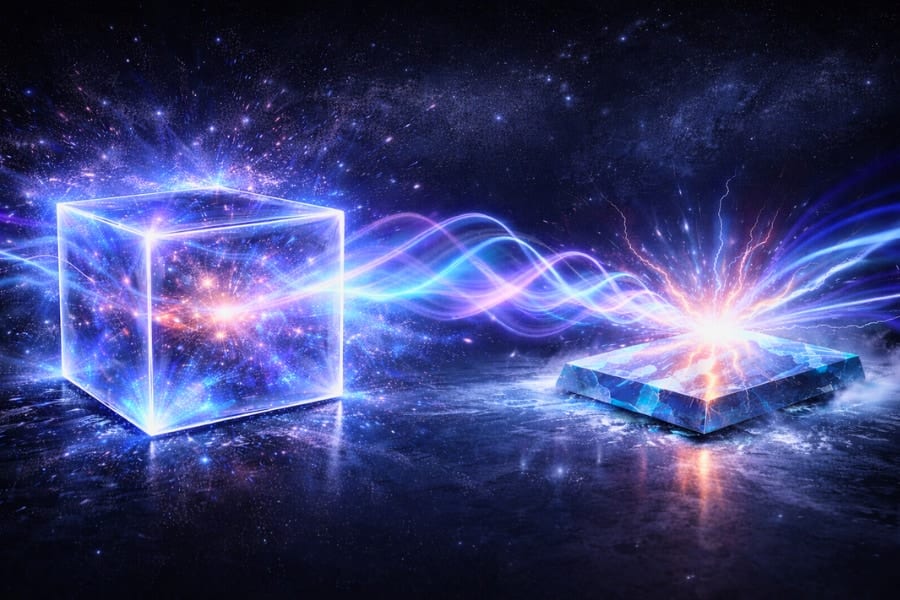








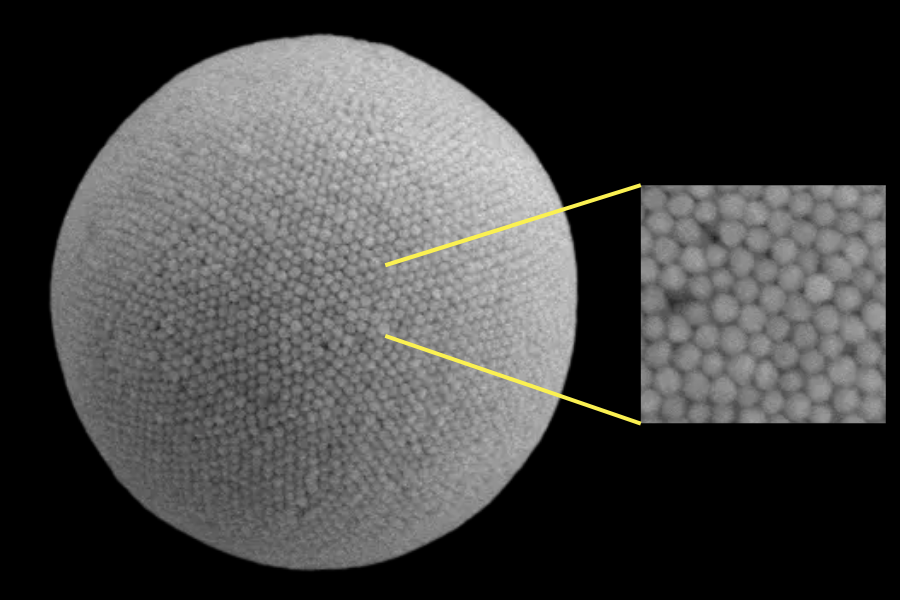





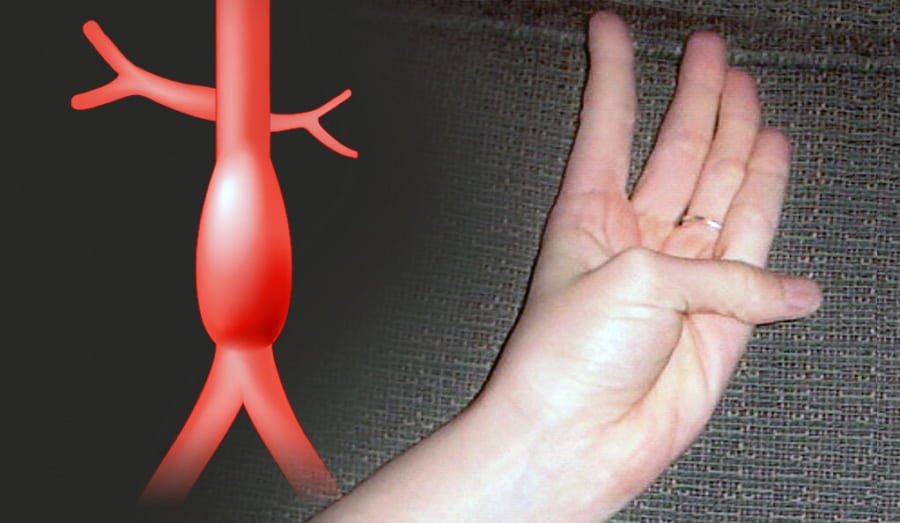



![よーく聞いてね!3つのヒントで学ぶ!どうぶつカード ([バラエティ])](https://m.media-amazon.com/images/I/51zT3OcliFL._SL500_.jpg)