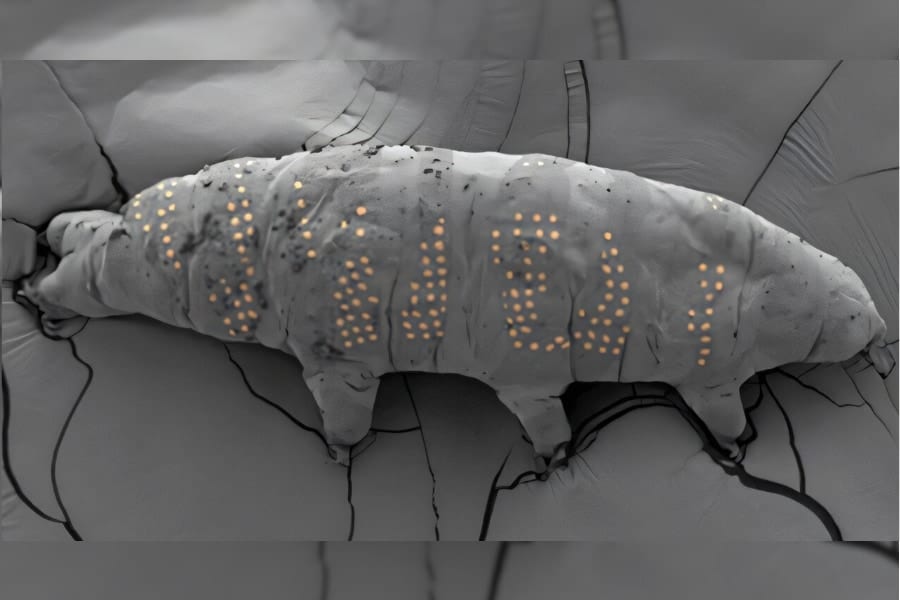暴力はDNAに刻まれるのか? シリア難民が示す世代間のトラウマ遺伝

今回の調査には、シリアからヨルダンへと逃れた三世代の家族48組・合計131名が参加しました。
1980年代に起きた暴力を体験しながら妊娠していた祖母世代、2011年以降の紛争で直接暴力にさらされた母と子ども世代、そして暴力にさらされなかった対照群(16家族)の三つのグループに分けて比較したのが大きな特徴です。
しかも、血液ではなく口腔内の細胞(ほほの内側の粘膜)からDNAを採取したという点もユニークです。
難民キャンプや移動先の地域で、何度も血液を採取するのは難しい場合が多いですが、この方法なら比較的手軽かつ安全に検体を集められます。
研究チームは、そこに含まれるDNAを“くまなく捜査”するように約85万カ所のメチル化パターンを解析し、暴力の経験やタイミング(直接・胎内・生殖細胞レベル)による違いを徹底的に調べました。
結果として、まず見つかったのは“直接暴力を体験した人々”のDNAにおける、いわば「特有の足跡」です。
ここには21もの部位で特徴的なメチル化変化が認められ、子ども世代と母親世代の双方に現れていました。
一方で、1980年代の暴力を目撃した祖母と、その娘、さらに孫にも共通して14カ所の変化が残っていたことも見逃せません。
これは“祖母が妊娠中に感じたストレス”が、まだ受精前の「生殖細胞」にまで影響を与えた可能性を示唆するものです。
興味深いのは、いずれの暴力期を体験していない対照群には、こうした変化が見られなかったという点です。
まるで砂浜に残る足跡のように、特定のDNA領域が「暴力を経験したかどうか」を指し示しているようにも思えます。
また、妊娠期(胎内)曝露については、他の二つのグループほど顕著な差分メチル化は検出されなかったと報告されています。
この点について研究者たちは、「生殖細胞レベル」や「直接暴力」ほどの大きなインパクトが胎内曝露には見られなかった可能性があり、詳細をさらに調べる必要があると指摘しています。
さらに、子ども世代の一部にはエピジェネティック上の“年齢加速”とも言える変化が確認されました。
これは、実際の年齢よりも早く細胞が“老化”しているように見える指標のことで、特に妊娠期に暴力を浴びた母体から生まれた子どもで顕著だったといいます。
こうした細胞レベルの“老化促進”は、将来的な健康リスクやストレス耐性の変化などに結びつく可能性が指摘されており、大きな関心を集めています。
エピジェネティック上の“年齢加速”とは、実際の誕生日で示される年齢よりも、細胞が“老けている”ように見える現象です。
年齢を重ねるにつれて私たちの体内ではさまざまな変化が起こりますが、そのペースが予想より速い人がいる、というイメージです。
いわば、年齢という名のカレンダーを半年早回しにめくっているような状態と考えるとわかりやすいかもしれません。
ではなぜ、その“早回し”が起こるのでしょうか。
ここで関わってくるのが「エピジェネティック(表現型可塑性)」という仕組みです。
DNAの配列自体には変化がなくても、そのDNAにくっつく化学的なタグ――メチル基(メチル化)など――が付いたり外れたりすることで、ある遺伝子が活性化したり、逆に抑え込まれたりします。
こうしたエピジェネティックな変化は、例えるなら本の文章そのもの(DNA配列)は書き換えずに、欄外に付箋やマーカーでメモを書き足すようなもの。
大掃除や衣替えのように、外部環境やストレスによって付箋が増えたり貼り替えられることで、細胞の働きが変化しやすい仕組みなのです。
実際には、エピジェネティックな年齢を測る「エピジェネティッククロック」という方法があり、ここではDNAにおける特定のメチル化箇所を指標にして、“細胞の老化度”を数値化します。
もしこの指標が同じ年齢層の平均より高ければ、「生物学的には実年齢より先に進んでいるかもしれない」と推測されるわけです。
人によっては、過度のストレスや栄養状態、生活習慣などの影響で、この“時計の針”が速く進む場合があります。
逆に、健康的な暮らしや運動習慣が、時計の針をゆっくりにする可能性も報告されています。
エピジェネティックな変化の面白いところは、DNAの配列自体を大掛かりに作り替えることなく(これは進化的には時間がかかる工程です)、比較的短期間で細胞の状態を変えられる点にあります。
いわば、遺伝子レベルの「緊急モード」や「高速モード」が働いて、環境に合わせた素早い対処が可能になるのです。
ところが、この素早い適応がうまく働かない場合や、逆に過剰に働きすぎた場合には、細胞が必要以上に“老化”へと進んでしまうリスクが高まるのではないか――ここに注目することで、私たちはストレスや生活環境がもたらす健康リスクを、従来の“カレンダー年齢”以上に正確に測れるかもしれないと期待されています。
なぜこの研究が革新的なのか?
第一に、多世代にわたる追跡は人間社会では非常に難しく、大規模な家族集団を対象に「直接的・妊娠期・生殖細胞レベル」という異なる暴力曝露を比較した事例はきわめて珍しいからです。
第二に、DNAのメチル化は“リセット”されると考えられてきたのに、祖母が体験したトラウマが娘や孫の世代で同じ部位に刻まれていたことは大きな驚きでした。
これらの結果は、「遺伝子配列が変わるわけではないのに、環境からのシグナルが世代を超えて遺伝のように伝わり得る」という新しい仮説を、より強く支持するものとなっています。
これまで「脳や心理の問題」として捉えられてきたトラウマが、DNAの化学的なタグを通じて次世代に受け継がれていくかもしれない――その可能性を、実証的に示した点こそが、本研究の最も革新的なポイントなのです。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)