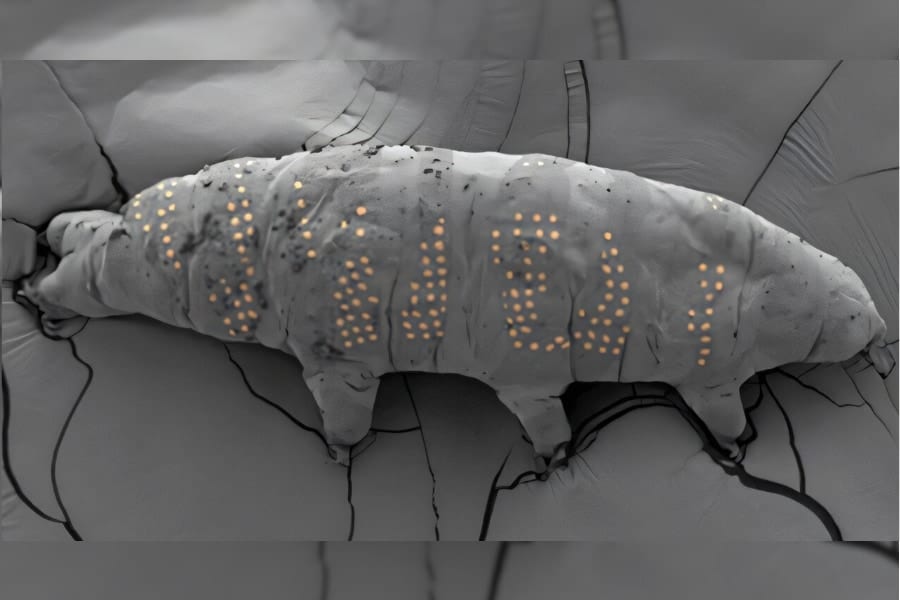人間でも暴力体験の遺伝を示唆する研究が増えている

トラウマと呼ばれる心の傷は、しばしば「忘れられない記憶」として語られます。
しかし近年の研究によれば、その“記憶”は脳だけでなく、私たちの遺伝情報を読み取る仕組みにも刻まれている可能性が示唆されています。
こうした考え方を支えるのが、胎児期の環境が将来の疾患リスクや発達に影響を与えるとするDOHaD(Developmental Origins of Health and Disease)仮説です。
もともとは栄養不足や毒素への曝露などが取り沙汰されてきましたが、暴力や虐待といった心理的ストレスもまた、DNAの「メチル化」という化学的タグを通じて“体に刻まれる”のではないかというわけです。
実際、ホロコーストの生存者やルワンダ虐殺の生存者とその子孫を対象にした研究では、親世代の恐怖体験が子どもの遺伝子上のメチル化パターンに反映されている可能性が報告されています。
DNAの配列自体は変わらなくても、あたかも「ノートに貼られた付箋」のようなメチル化の変更が、遺伝子のオンオフを左右するのです。
ただ、ヒトの受精や妊娠の初期段階では、いったん多くのエピジェネティック修飾が“リセット”されるとされており、「いったいどうやってトラウマの痕跡が次の世代へと渡るのか?」という疑問は長らく残っていました。
動物を使った研究では、母親が極度のストレス下にあると、子ども世代どころか孫世代までも振る舞いや体質に変化が生じるケースがあるといいます。
ごく一部のDNA領域は“リセット”の網をかいくぐるという報告もあり、人間の場合にも同様のメカニズムが存在するのではないかと予想されています。
こうした視点から見ると、シリアの状況はまさに“エピジェネティックの長期的影響”を確かめるのに、ある意味で悲しいほど適した条件をそろえています。
1979年の反乱鎮圧から1982年のHama市攻撃、さらに2011年以降の政情不安と内戦――国全体が四十年以上、ほぼ途切れることなく暴力と恐怖の中にあり、何世代にもわたって家族が避難を余儀なくされてきました。
そんな苦難の歴史をくぐり抜けた人々は、「心の痛み」を超えて、もしかすると「体にこびりつく傷痕」をも抱えているのかもしれません。
そこで今回研究者たちは、シリア難民三世代の家族を対象に、直接的な暴力体験・妊娠期の胎内暴力曝露・祖母の妊娠時期における生殖細胞レベルでの暴力曝露を比較し、DNAメチル化パターンを網羅的に解析することにしました。





























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)