トラウマ遺伝の衝撃と限界:私たちは何を学ぶべきか

今回の研究結果は、暴力によるトラウマが次世代へと受け継がれ得るという考えを、具体的なDNAメチル化の変化として示唆するものです。
とはいえ、この発見がすぐに「トラウマは必ず遺伝する」と断言する根拠になるわけではありません。
たとえば、“祖母の体験した恐怖が孫に伝わる”ことを説明する上で、メチル化による世代間継承が唯一のメカニズムとは限らないのです。
親世代の子育てスタイルや生活環境、社会的影響もまた、子どもの精神状態や体の反応に大きく関わります。
さらに、DNAの配列自体が変化したわけではないため、トラウマの痕跡がどこまで健康や行動に影響を及ぼすのかは、まだ見通せません。
実際、動物実験では「ストレスに強くなる」方向に働く場合があるとも報告されており、メチル化の変化は“悪い結果”だけを意味するわけではありません。
つまり、エピジェネティックな変化は環境への素早い適応策である可能性も否定できないのです。
また、サンプルサイズの限界や、すべての家族が同じ条件で育ったわけではないことを考えると、結果の再現性については今後の研究での検証が不可欠となるでしょう。
比較的少人数の難民コミュニティを対象に行われた本研究は、「大きな謎に挑むための第一歩」という位置づけと見るのが妥当かもしれません。
実際、研究者の中には今回の発見を歓迎しつつも、口腔粘膜以外の組織でも同様の変化が起きるのかや、子孫に及ぶメチル化パターンがどれほどの期間持続するのかなど、多くの疑問点を指摘する声があります。
それでも、本研究が投げかけた問いの重みは小さくありません。
ホロコーストやルワンダ虐殺の事例と照らし合わせても、人間の体は「心が受けた傷」をただの記憶として残すだけではなく、遺伝子レベルの書き込みとして保持している可能性が改めて浮上してきたからです。
私たちがストレスやトラウマと呼ぶものの本質に、まだ未知の領域が広がっていることを示す――そこにこそ、この研究の最大の意義があります。
次に何が起きるのか、私たちの遺伝情報がどのように“環境”と対話しているのかは、これからのさらなる調査と検証が明らかにしていくでしょう。






























![[WILL CLENS] シューズパウダー 日本製 無香料 シューケアキット 靴 消臭 パウダー (1本)](https://m.media-amazon.com/images/I/41m8Ig2XigL._SL500_.jpg)

![[W.P.S.] 防水スプレー 除菌 抗菌 防汚 機能付き 大容量420ml 日本製](https://m.media-amazon.com/images/I/41aHfy9uuZL._SL500_.jpg)




















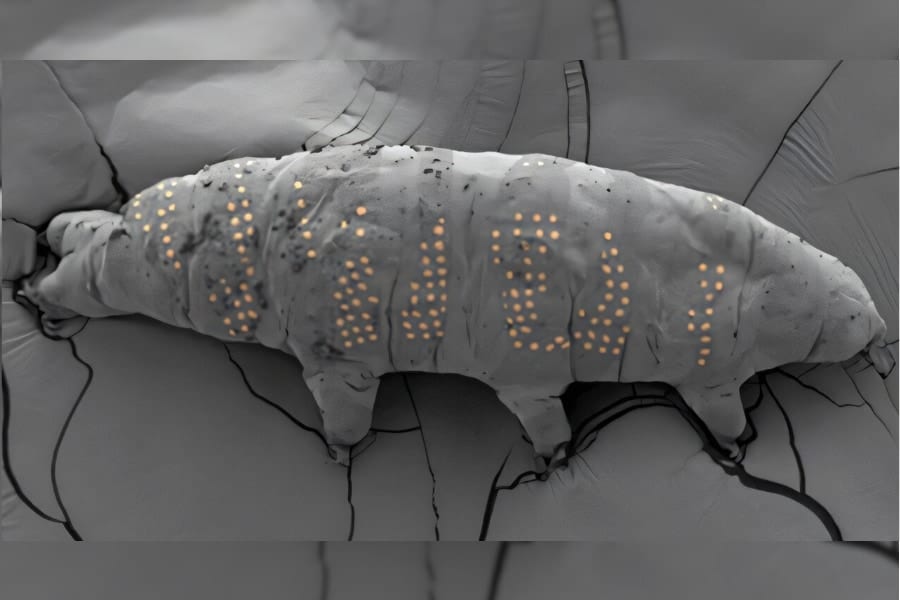








ストレスやトラウマだけじゃなく貴族の生活してきたやつも絶対に違うよね
母体からの遺伝しかしないのかな?
紛争地域で出生率が上がる傾向とかありますよね。心の傷が日常化したら、出生率上がるんですかね?
スマホのデータが何度も吹っ飛んだ人は出生率高まる説とか、どうですかね?飛躍しすぎ?